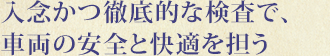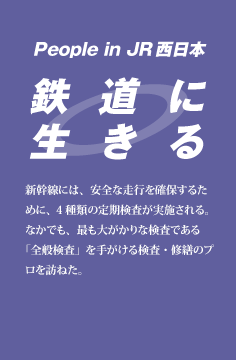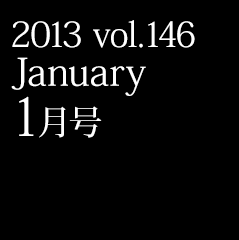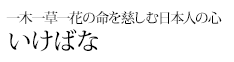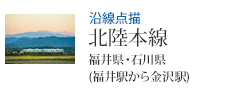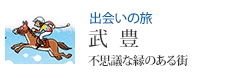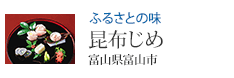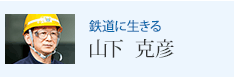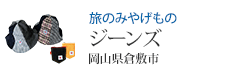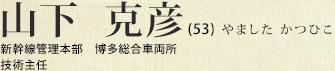

先頭車両に搭載された連結器のメンテナンスを若手社員に指導。
1974(昭和49)年の開設以来、山陽新幹線の検査・修繕拠点として重要な役割を担ってきた博多総合車両所。往年の0系から最新のN700系まで、時代とともに走り続けてきた新幹線の安全性と快適な運行を技術の面で守り続けている、いわば新幹線のホームドクターである。
新幹線の検査には、2日に一度行われる「仕業検査」をはじめ、走行距離が3万kmに達した場合または30日以内に行う「交番検査」、走行装置となる台車を主に検査する「台車検査」、そして120万kmまたは36カ月以内に行う「全般検査」がある。
「全般検査は、自家用車の車検みたいなものだと考えてください」。そう語るのは、山下克彦技術主任。1979(昭和54)年の入社以来、30年以上にわたって新幹線の全般検査を担ってきた、新幹線のホームドクターを体現する技術者である。
全般検査では、車体・台車および搭載機器などについて徹底した機能の検査と修繕が行われる。検査と修繕を終えた機器は、塗装し新車時の輝きを取り戻した車両に搭載されて、120万kmの旅へと再び出発していく。
「一度全般検査を受けた車両は、次の全般検査まで走り続けます。手がけた車両が安全かつ快適に走れるよう、新車に近い状態で送り出すのが我々の仕事です」。
全般検査に入庫する車両に対しては、修繕の際に必要となる部品や材料などをあらかじめ手配しておくために、「全般検査入場5カ月前点検」と呼ばれるプレ全般検査が行われる。
「個々にコンディションの異なる車両を丹念に調べ、全般検査の際には何が必要になるのかその見定めを行い、ガラス、カーペットなど、すぐに調達できない材料は手配しておきます。全般検査の中で作業を完璧に終えるために、この事前の準備が重要です」。
全般検査を完璧に遂行する見定めと準備が山下と施工チームの手腕にかかる。
「5カ月前点検の項目だけでなく、私たちは、常に“最善の車両を提供する”という意識を持っています。今後、発生するかもしれないトラブルを全般検査の中で直しておくのが大事なのです」。山下の言う“最善の車両を提供する”とは、具体的にどういうことなのか。
「たとえば車両のカーペットがはがれる可能性があれば、事前に直しておきます。お客様がつまずいて怪我につながる恐れがあるからです。テーブルにガタつきが発生しそうなら、ガタが出ないように直しておきます。飲み物がこぼれてお客様の服を汚してしまうかもしれないからです。また、安全な走行を担う計器の作動や配線の絶縁、パンタグラフなど室内から屋根上まで将来を見越して徹底的に検査・修繕します」。

車両に高圧の電流を流し、配線に異常がないかをチェックする耐圧試験。試験前に、搭載されている機器の取り外しを指導。

配線の導通および絶縁をチェックする配線試験装置で、車両に巡らされた全ての配線を調べ上げる。
お客様にご迷惑をおかけしたくない。山下をはじめ作業にあたるチーム全員がその思いを共有している。
「見えている故障や不具合はその場で直せますが、隠れたところにこそ危険がある。全般検査はお客様のために、あらゆる危険を排除するところに大きな意味があるのです」。
事故やトラブルを予防する取り組みは、自分たちの職場にも浸透している。ある日、作業場では検査で使用するために、高圧の電流が流れるケーブルを床に置いたまま作業が行われていた。その場にいた若手技術者から「なぜこんなやり方をするのか?」という疑問の声があがった。
「これまで慣例的にやっていたこと、ベテランたちが常識と思っていたことが、別の視点から見れば非常識ということもある。若手技術者から『なぜ?』という声を聞いた時、ハッとしました」。
より安全を求めるなら、常識を疑い、常識を改善していかなければならない。そう痛感した山下は、意見が言いやすい環境作りと若手社員の育成がリーダーである自分の使命だと気付かされた。
「若手たちが積極的に発言できる環境や関係を大切にしたい。さらに仕事に対する責任感や向上心がなければ改善は生まれません。与えられた仕事をこなすだけでなく、ここは自分に任せろ、そう胸を張って言ってくれるスペシャリストを育成したいのです」。
30年以上新幹線と向き合ってきた新幹線のホームドクターは今、スペシャリストの育成という新たな目標に向かって若手たちと向き合っている。

作業工程表をもとに作業分担の確認を行う。綿密なコミュニケーションを図ることでチーム力を高める。