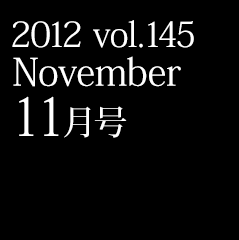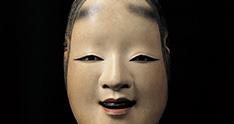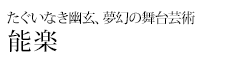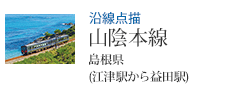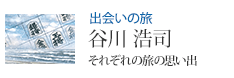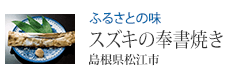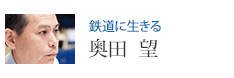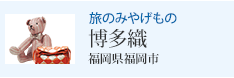約770年という歴史を誇る「博多織」。たくさんの細いタテ糸に太いヨコ糸を力強く打ち込むことで、タテ糸を浮かせて柄を出すのが特徴だ。また、他の織物に比べて厚みや張りがあるため、帯としての用途に適しており、締めたら緩まないことから古くは武士の帯として重用されていた。
博多織の歴史は鎌倉時代、博多商人の満田弥三右衛門[みつだやそうえもん]が宋へ渡り、織物などの技法を習得したのがルーツだといわれる。さらにその約250年後、室町時代に弥三右衛門の子孫・彦三郎が明へと渡り、最新の織物技法を習得。
帰国後、改良に励み、生地が厚く、浮線紋や柳条などの模様が浮き出た織物を生み出す。これを博多の地名を取って「覇家台織[はかたおり]」と称したと伝えられる。その後江戸時代に福岡藩主の黒田長政が幕府への献上品に指定し、「献上博多」として広く知られるようになった。
今なお、質の良さと美しさから博多織の帯は高い評価を受けているが、伝統の柄を取り入れたバッグや靴、小物が作られており、伝統とモダンが融合した新しい博多織が国内外で注目されている。