 |
 |
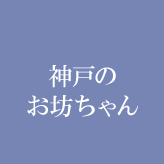 |
 |
神戸に行くときは胸が高鳴る。先日もJR神戸駅近くであったある文化講座に出かけたが、家を出たときからどきどきしていた。講座にかかわってどきどきするのではなく、神戸に行くこと自体に胸が鳴るのだ。

あれは確か、小学校四年生の時だった。郵便局に勤めていた父が、職場の旅行に私を伴ってくれることになった。県庁のある市(松山)への一泊旅行だ。

その旅行の朝、私はお坊ちゃんになって出発した。松山と言えば、夏目漱石の名作「坊っちゃん」の舞台になった町だが、私のお坊ちゃんは漱石には関係がない。私は神戸のお坊ちゃんになったのだ。

母は娘時代、行儀見習いのために神戸の某家に奉公していた。母の姉や妹もその家に奉公していた。その家にはお坊ちゃんがいた。

私が父に連れられて初めて旅行することになったとき、母はにわかに神戸のお坊ちゃんを思い出した。それで、急遽、スーツと革靴をあつらえた。スーツは洋裁をしていた叔母が作ってくれた。

|
|
 |
 |
旅行の朝、そのスーツを着用したが、残念なことに袖や裾が少し長い。折り込んで着たのだが、今から考えると、それはわざと長くしていたのだろう。身長がすぐに伸びることを見越し、長めに作ったのだ。

皮靴もまた大きかった。新聞紙を詰めて履いたが、ぶかぶかの感じはいなめない。

なんだか恥ずかしかった。友だちはまだ藁草履を履いている時代であった。もちろん、スーツの子はいない。せいぜいがお古の学生服で、しかも袖口が鼻汁でぴかぴかしていた。昭和二十年代の末、まだ戦後の貧しさが続いており、その象徴のように子どもはだれも鼻汁を二本垂らし、しかもそれを袖口で拭いたのだ。

つまり、私はとびきりモダンなお坊ちゃんになったのである。若い母が世話した神戸のお坊ちゃんに。でも、松山に行ったら、なんだかつらくなった。あまりにもぶかぶかのスーツだったし、足にはマメができてしまった。神戸のお坊ちゃんが恨めしかった。

それから、数年後、私が中学生になったある日、台所革命がわが家にやってきた。村の婦人会活動の一環として、朝食の洋食化が推奨され、わが家も朝はパンになった。これはうれしかった。パンが珍しかったし、洋食というものにあこがれていたから。

|
|
 |
 |
さて、初めての洋食の日。パンの焼ける匂いが食欲をかきたてた。一枚の食パンを食べ終え、二枚目に手を出そうとしたら、母がぴしゃっと手の甲を叩いて言った。「パンは一枚よ。神戸のお坊ちゃんも一枚でした」。

一斤を五等分した一枚である。それだけでは中学生の私にはつらかった。弟たちも不平を言ったが、「足らなかったらサツマイモを食べてなさい。お坊ちゃんはパン一枚です」と母は譲らなかった。

結局、パンの朝食は長続きしなかった。母を除く家族の全員がお坊ちゃんを理解できなかったのである。

以上のようなことがあって、神戸は私の特別な場所になった。お坊ちゃんが住んでいる町なのだ。

そのことはきのうのように夏蜜柑

これは私の俳句。「お坊ちゃんは夏蜜柑が好きでした。すっぱい!と言いながら、でも一個をまるまる食べましたよ」。母の口にしたこんな話のせいか、夏蜜柑だけは私も好き。春に神戸に行くと、果物屋を覗いて夏蜜柑を探す習性になっている。もちろん、そのときの気分は少し神戸のお坊ちゃん。
|
 |
 |
|
|
 |