 |
 |
 |
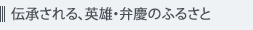 |
田辺は「口熊野」と呼ばれた。熊野詣が盛んな頃の、熊野への入り口という意味だ。現在でも京阪神方面からは紀伊田辺駅が熊野詣への玄関口になる。中辺路を経て熊野三山に向かう人はここで降りる。

駅前で出迎えるのは、薙刀を構えた立派な弁慶像だ。京の五条大橋での牛若丸との出会い、源平合戦での武勇伝、主人である源義経とともに非運の最期を遂げた怪力無双の荒法師。今なお数々の英雄伝説が語り継がれている弁慶の生誕地が田辺だと言い伝えられている。弁慶が産湯に使ったという井戸や産湯釜も残っているが、史実としての弁慶には謎が多く、生誕地は他にも諸説ある。

田辺説の根拠は、室町時代に書かれた『義経記』で、その中で弁慶は熊野別当の嫡子だとされている。また『御伽草子』の「橋弁慶」では熊野別当湛僧[たんぞう]の子であると記されている。別当は熊野詣を采配した修験者たちの頭で、湛増は歴史上実在の人物。壇ノ浦の合戦で源氏に勝利をもたらした熊野水軍の長だ。そして『義経記』によれば、熊野詣途中の都の姫君との間にできた子だと伝えている。

怪僧らしく、弁慶は母の胎内に18カ月、生まれた時すでに髪は長く歯が生えそろっていたという。話の信憑性はともかく、弁慶が田辺のシンボルである事実は疑いようがない。 |
 |
 |
 |
 |
| 天神崎の岩礁にぽっこりと立つ丸山は田辺の代表的な景観。ナショナルトラスト運動により自然が守られた天神崎一帯では、陸と磯と海が一体となった貴重な生態系を形成している。 |
 |
 |
|
 |
 |
電車を降り駅を出ると弁慶像が勇壮な姿で出迎えてくれる。 |
 |
 |
町中には弁慶にまつわる史跡が点在する。写真上は田辺市役所の脇にある弁慶産湯の井戸、下は扇が浜公園にある熊野水軍出陣之地の石碑。 |
 |
 |
町中に残る道分け石。田辺は熊野詣・中辺路の起点であり、旅籠が建ち並び、参拝者で賑わった。 |
 |
 |
町の北西にある出立王子はここから深い山へと向かう参拝者が潮で身を清める潮垢離[しおごり]の儀式が行われていた場所。 |
 |
 |
| 古来より交通の要衝として栄えた田辺。熊野詣、中辺路の起点となる紀伊田辺駅は、今も多くの参詣者で賑わう。 |
 |