 |
 |
「美しき川は流れたり
そのほとりに我は住みぬ」
生涯ふるさとを愛惜した詩人
室生犀星[むろうさいせい]は、
「多彩な作家」といわれる。
俳句においても鋭く視覚的な表現で、
独自の作風を築いている。
暑さの盛りの季節感を、
犀星の句にたどってみた。 |
 |
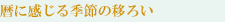 |
冒頭の句は、とんぼの様子に「大暑[たいしょ]」の季節感を詠ったものである。「暑気いたりつまりたるゆえんなれば也」と暦便覧に記されるように、大暑は一年のうちで最も暑さの厳しい時期。二十四節気[にじゅうしせっき]のひとつで新暦の7月23日頃にあたり、天文学的には太陽が黄経120度に達したことをいう。二十四節気とは、古代中国で考案されたもので、太陽年を二十四に等分し、それによって季節の移ろいを知らせるものである。古くから日本の四季の生活習慣や行事と深くかかわり、俳句の季語に詠まれるなど、日本人の感覚に根付いてきた。

犀星のこの句は、『犀星発句集』〈1943(昭和18)年〉におさめられているが、いつ、どこで詠まれたかは定かではない。大暑の頃、北陸ではちょうど梅雨が明け、一気に夏本番へと向かう。句作に励む中で磨かれた季節や自然への鋭い観察眼で、ふるさとの夏の情景を十七文字に表現したのであろうか。 |
 |
 |
| 白山山脈を源流に持ち、金沢市内を東西に流れる犀川。犀星が故郷という時、まず浮かんでくるのは犀川の流れだったという。(写真提供:金沢市) |
 |
 |
| 犀星が幼少年期を過ごした、高野山真言宗雨宝院。小説『性に眼覚める頃』の舞台でもある。(写真提供:室生犀星記念館) |
 |
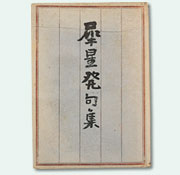 |
| 1943(昭和18)年8月に刊行された『犀星発句集』。犀星は、生涯約1750句を詠み、4冊の句集を刊行した。(写真提供:室生犀星記念館) |
|
|
|
 |
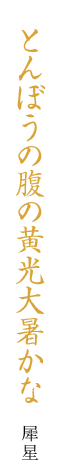 |
 |
 |
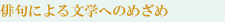 |
犀星文学の原点は、金沢での生いたちにあるといわれる。1889(明治22)年8月、加賀藩にて足軽組頭を勤めた小畠[こばたけ]弥左衛門吉種を父とし、ハルという小畠家に奉公していた女中を母として誕生するが、生後まもなく生母から離され、犀川の畔に建つ雨宝院[うほういん]に引き取られる。住職室生真乗[しんじょう]の内縁の妻、赤井ハツによって育てられ、7歳より真乗の養子となって室生姓を名乗る。このような幼い頃の経験が、後の文豪と称えられる力を育んだとも言われる。

抒情詩だけでなく、小説や童話、自伝的エッセイなど数多くの著作を残した犀星。その出発点は、13歳で高等小学校を中退し、給仕として勤めていた金沢地方裁判所時代に、俳句の世界に触れたことによる。金沢は、芭蕉が訪れた元禄の頃から、日本でも有数の俳諧の町であった。職場の先輩の手ほどきや旧派俳句の宗匠の添削を受けながら、若くして俳人としての頭角をあらわすようになる。投句が「北國新聞」にはじめて掲載されたのは、1904(明治37)年犀星15歳の時。その後1910(明治43)年の上京までに、約550句が入選している。年少とはいえ、どの俳句も季題をわきまえ、語の選び方は正確、豊富であるという。独学で歳時記を読みこなし、句作の知識を身につけていったのであろう。

土用餅あづきのべにの冴ゆるかな

大暑の数日前から始まる土用の風習を視覚に訴えた句もまた、犀星ならではの作風といえる。土用とは雑節のひとつで、立春を起点として1年を4つの季節に分けた、各季節の終わりの約18日間をさす。土用は年4回あるが、立秋前の暑さの最盛期である夏の土用が一番なじみ深いだろう。土用の丑の日には精のつく鰻を食し、また、夏季の悪病災難を退けるため、餅を餡[あん]で包んだ和菓子を食べる習わしなどが今も各地に残っている。 |
 |
 |
 |
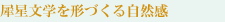 |
犀星は、自然の中で出会った植物や昆虫、魚などの小動物への慈しみの心を、その創作の世界に表現している。このような自然に対する感受性は、周囲からの疎外感や孤独の中にあって、身近な野の生きものに心を寄せ、慰めを求めていた幼少期に育まれたと考えられる。雨宝院からの犀川の眺めや河原での動植物とのふれあいという原体験が、俳人としての季節感を養い、“いとおしい生きもの”としてのとんぼの飛翔を、夏の盛りの情景として、鮮やかに詠ったのである。

句作から文学の道を歩み出した犀星は、近代抒情詩の一つの高峰を成し、小説家としても確固たる地位を築いていく。作家としての名を高めた特異な感覚的表現は、俳句という短詩型によって培われ、故郷の風土と生活に磨かれた感性に他ならない。その感性はまた、四季折々の自然をきめ細かな情感でとらえ、暮らしに根付かせてきた、日本人ならではの美意識へとつながっている。 |
 |
 |
|
|
 |