|
早朝の倉吉の町を歩けば、しんと静まり返った家々の情景が時計の針を逆転させるようだ。右手に、こんもりした打吹山が並んでついてくる。街道筋に広い敷地の屋敷がある。現在は空き家で、旧牧田家という江戸期に稲扱千刃や倉吉絣を扱った大商人の屋敷なのだが、じつはここに倉吉と大坂との意外な秘話がある。「牧田淀屋」ともいう屋敷のかつての当主は、「淀屋」を再興した人物だという。

淀屋といえば大阪の「淀屋橋」にいまも足跡を残す江戸初期の大豪商で、百万石の大名をもしのぐ富力を持っていたといわれる。初代は淀屋常安[じょうあん]、数えて五代目の淀屋辰五郎の豪放な放蕩ぶりは目にあまるものがあった。「驕奢僭上[きょうしゃせんじょう]の振る舞い」は井原西鶴の『日本永代蔵』にも描かれ、幕府の「奢侈[しゃし]禁止令」をあざ笑うようで、ついに幕府の逆鱗にふれお家は取り潰し。淀屋5代の栄華は潰えてしまう。しかし歴史の秘話はその先があった。淀屋の大番頭であった牧田仁右衛門は故郷の倉吉に戻り、密かに淀屋を再興した。それ以降を後期淀屋といい、さらに多田屋という屋号で大坂の淀屋がもとあった場所に再建する。その淀屋の復興を促したものが「稲扱千刃」や「倉吉絣」であったと考えられているが、まだ研究の途上である。

玉川沿いの大連寺には淀屋一族が眠る墓所がある。そして寺の東側に隣接する一画が打吹玉川地区と呼ばれる、商家と白壁の土蔵が並んで江戸時代そのままの情趣を残す古い町並みだ。川幅の狭小な玉川だが夏には鮎も遡上する。

その清く静かなせせらぎをまたぎ幾つもの小さな石橋が架かる。川筋に沿って建ち並ぶ漆喰の白壁と、黒く焼いた杉板のコントラストはいかにも、倉の姿がじつに良しである。ここは表通りに店を構える屋敷の北側にあたる。家の主人によると「冬には倉が北風を防ぎ、夏には木戸を開けて風を取り入れます」という。生活上の工夫である。

この一画のその多くが江戸時代以降に建てられたものだが、界隈でもっとも古い町家で、いまも造り酒屋を営む高田酒造は、築170年。どれもみな時の経過を競う建物で、醤油や味噌や酒の蔵などである。「稲扱千刃」の往時を偲ぶものは町に残る1軒の鍛冶屋と、「倉吉千刃」と「倉吉絣」の歴史と繁栄を伝承する資料館や工芸館だけとなっている。

現在の倉吉の経済の中心は、天神川を渡った倉吉駅周辺に移り、旧市街はその役割を終えたかのように、商家や蔵も空き家が多く、利用されることも少なく放置されるままになっていた。このままでは歴史の証人である文化遺産の遺失が危ぶまれたのだが、倉吉の人びとは使われなくなった一部の酒蔵や醤油蔵などを改造し、さまざまな物産店として活用し、町に再び生命を吹き込んだ。そうして甦った古い町並みに、いまは大勢の人びとが足を運ぶ。

赤い瓦の屋根の白壁の土蔵、軒の低い歴史の空気を吸い込んだ商家…倉吉の町並みは時代の向こうに忘れかけている情景を思い出させてくれる、懐かしい日本の風景である。 |
|
 |
|

玉川沿いの白壁土蔵群。それぞれの裏門からは石橋が架かる。窓は、裏門倉・土蔵・醸造蔵では角窓を切り、塗格子や鉄格子をはめる。
玉川沿いの土蔵は、基礎の石垣は安山岩、外壁の腰周りは杉焼きの板の縦目張り、上方を漆喰壁とする。白と黒の対比が鮮やかだ。 |
|

赤瓦五号館「久楽[くら]」の2階から白壁土蔵群を眺める。 |
|

豪商淀屋清兵衛とその一族の墓がある大蓮寺。モダンな外観の本堂は昭和30年に再建されたもので、山陰地方初の鉄筋コンクリート造り。 |
|
|
|
|
|
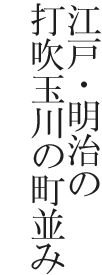 |
|
 |
|
 |
|

高田酒造・高田家主屋。倉吉の町家の中で最も古く1843(天保14)年に建てられた造酒屋。暖簾をくぐり奥に入ると、天井が高く大きな神棚を祀っている。玄関には地元の仏師の手による福狸が鎮座する。主屋は国登録有形文化財。 |
|

倉吉の最も古い町家である高田酒造の店の奥の吹抜け。明かり取りの丸窓が空間に優しさを与えている。 |
|

玉川に石橋を渡した桑田醤油醸造場の裏手門。 |
|

備後屋6代目はこた人形師三好明さん。素朴でかわいい張り子のはこた人形。女の子の遊び相手であり、お守りがわりだった。 |
|
|