 |
 |
 |
 |
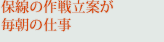 |
兵庫県の北部・和田山から円山川沿いを北に走り、城崎から竹野を経て日本海沿いに鳥取県の東端・東浜まで続く約86.4kmの線路。豊岡駅に隣接する豊岡鉄道部は、この区間を保守管理している。

“元気と真心”の但馬人と自らを称する下田誠一は、線路の保守(=保線)を専門に34年間にわたって業務を行っている大ベテランだ。

「人と話をするのが大好きでしたから、もともとは駅での業務を希望していたのですが(笑)、いまとなっては保線の仕事以外は考えられませんね」と語る下田は、現場での保線作業だけでなく、工務科長として科員を管理する立場でもある。

「朝はまず、前日の係長からの報告と保線計画を基に、その日の作業の作戦を立てます。これが、現在の大切な日課ですね」と下田。「限られたスタッフをいかに効率良く配し、完璧な結果を導き出すかが重要です」と語る。 |
 |
 |
 |
 |
| 検査報告書を厳しくチェック。毎日の大切な業務だ。 |
|
 |
 |
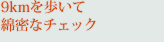 |
高速で走行する列車を支える線路。列車の安全を守るため、保線作業は重要な業務であり、日々のチェックが欠かせない。

「線路の向こうには、お客様がいらっしゃいます。毎日の点検はすべて完璧に行わなければなりません。私たちが素早く的確に動くことで、お客様の安全が保たれているのですから」と下田。保線に関わる業務には、綿密な年間計画が立てられており、チェック項目は年間50項目にも及ぶ。毎日欠かすことなく点検を行う下田たち保線作業員には、乗客の安全を守るという責任と誇りがみなぎっている。

「検査機械やマヤ車(高速軌道検測車)などを使っての点検も行いますが、基本は人の目と手による点検です。軌道上を歩いて線路の傷や摩耗、歪みなどをチェックし、シートに記入していきます」と下田。軌道上を歩く距離は、一度に9kmにも及ぶ。ハンマーで線路を叩いて音でチェックし、スパナでボルトの緩みを直しながらの検査。作業の安全確保のため、これを見張係と1チームとなって行う。 |
 |
 |
 |
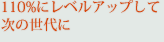 |
保線には、安全性の他に列車の乗り心地をチェックするという仕事もある。線路に起因する列車の揺れや振動などを防ぎ、乗客に快適な乗り心地を提供するというのも目的のひとつで、週に1度列車に乗務し、乗客がどのような乗り心地を味わっているのかを体感する。

「列車の動揺を測定する機械がありますが、乗車していて違和感を感じた部分と、測定結果の波形の乱れとがピタッと一致するんです」と下田。検査機器の進歩は目覚ましいが、永年培ってきた職人の経験とカンは、それに優るとも劣らない。

「私はいずれこの職場を去りますが、ここの現在の保線レベルを100%としたら、110%にして次に引き継ぐのが目標です」と、常に保線のレベルアップをめざす下田。「設備が可愛く思えるんですよ。自分が守ってやらないと…ってね。レールにキスだってできます(笑)」保線に賭けた男の究極のメッセージを聞いた。 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 線路の高さに目線を合わせ、線路の歪みをチェックする。。 |
 |
 |
| 分岐器のボルト点検。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 軌道上を歩き、ハンマーで部品を叩きながら線路やポイントを点検。ボルトの緩みなど、その場で保守できる部分は行う。 |
 |
 |
| 豊岡鉄道部の部内報「こうのとり」。保線に関するエピソードや思いなどを綴った下田の手記も掲載されている。 |
 |
 |
|
|
 |