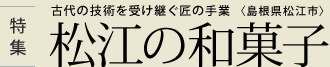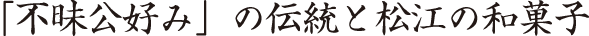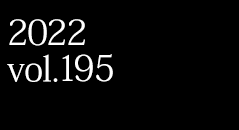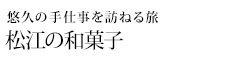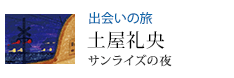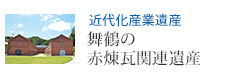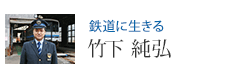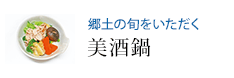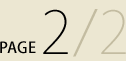
日本の菓子の始まりは木の実や果物だと考えられている。記紀神話によると、垂仁[すいにん]天皇の命を受けた田道間守[たじまもり]が常世国へ非時香菓[ときじくのかくのこのみ]を求め、持ち帰った香菓が柑橘類だったという。また、棗[なつめ]や栗、無花果[いちじく]、葡萄などを乾燥させた乾果、そして柿や西瓜[すいか]、胡桃[くるみ]なども茶菓子として供されてきた。加工された菓子は、奈良時代に唐菓子[からくだもの]が日本に入り、その後の和菓子の発展に大きな影響を与えたといわれる。
松江市内(旧城下町)に現存する最も古い歴史を誇る御菓子司「一力堂[いちりきどう]」は、創業から約270年。城の外堀を少し南に下った末次本町に店を構える。その始まりは、参勤交代のお供で江戸に入った創業者の惣七、作兵衛兄弟が餡[あん]練り屋で修行を重ね、その技術を松江に持ち帰って「三津屋」の屋号で開業した。やがて、不昧公の好みとして指名を受けて作ったとされるのが、一力堂を代表する現在の銘菓「姫小袖」だ。紅白に染め分けた可憐な和菓子は、サトウキビが原材料の和三盆糖と、原材料がもち米の寒梅粉の干菓子で、当時の銘は「沖の月」。それは松江藩主のためにだけ作ることを許され、一般に出回ることのない藩主御用達の「お留め菓子」と呼ばれた。見た目にも気品のある干菓子で、後まで引きずらない上品な甘さが口の中でほどけるようにスッと溶けていく。
松江藩のお留め菓子「沖の月」を再現した姫小袖。和三盆糖と寒梅粉の角形干菓子。


菓子の製法が記されている『御菓子直伝帳』は江戸時代のもので、一力堂に伝わる貴重な資料。写真右の三つ葉葵の紋入り漆塗りの箱は、城にお菓子を納めるために使用されたもので、藩御用達の御菓子司としての歴史を物語る。


老舗「一力堂」9代目当主の高見さんは、「ある小学生が下校時に店に来るんです。試食用の和菓子を食べて、お腹が満たされると帰って行く。大人になって、思い出してくれるとうれしいですね」と笑顔で話す。菓子処ならではのエピソード。

春をイメージした彩雲堂の上生菓子。看板商品の若草だけではなく、彩雲堂では季節と旬の行事に応じた意匠の上生菓子を創意工夫している。

彩雲堂の初代が復活させた「若草」。良質のもち米を石臼で水挽きし、銅鍋でじっくり練り上げる。切り分けた求肥に手作業で一つひとつ寒梅粉をまぶして仕上げていく。



製造部の部長を務める和菓子職人の田中さんは、「後継者問題はどこもありますが、私どもはゆっくりですが職人が育っています。昔に比べると女性も増えました」と話す。工場内では40名ほどが働いている。
「明治に入り藩がなくなって後ろだてがなくなりましたが、歴史や老舗にこだわるというよりも、私にとって和菓子屋は常の“いとなみ”です。だから、手を抜かず素材や美味しさにはこだわっています」と話すのは、一力堂9代目当主の高見雅章さん。
店内には「錦小倉(小倉餡の棹菓子)」や「松江葵(葵紋の最中)」などがショーケースを飾り、松江ゆかりの文豪 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)も好んで食べたとされる羊羹も並んでいる。製法はハーンも口にした当時のものと同じにしてあるそうだ。
そして、大橋川に架かる松江大橋を南に下り天神町に入ると、瓢箪[ひょうたん]をあしらった窓が目を引く彩雲堂がある。不昧公好みの銘菓「若草」を復元した、1874(明治7)年創業の和菓子店だ。春の茶会に主菓子[おもがし]としてよく使われていたとされる若草は、もち米を練り上げた求肥[ぎゅうひ]を木枠に流し固め、若草色の寒梅粉をまぶした和菓子だ。他店でも扱いのある銘菓だが、彩雲堂の若草にかける想いは格別だ。一日約5,000個も作られる若草は全て菓子職人の手作業で作られている。その製造拠点である工場が中海の中央に浮かぶ大根島にあり、見学させてもらった。
工場内には多くの菓子が作られているが、その一角に「若草仕上げ室」が設けられ、菓子職人が丁寧に一つひとつ仕上げていく。でき上がった若草の食感はコシが強く、それでいて容易に求肥が噛み切れる。程よい甘さで、何より粉末状の淡い緑色が美しい。「見た目はもちろん、味や食感も重要です。若草に限らず、何度も試食を繰り返し、季節に応じた新たな意匠を考え、その中から選抜して商品となります」と工場責任者の田中紀幸さん。玉状の白餡を手に取ると、慣れた手つきで三角ベラを巧みに用い、あっという間に丸い餡が桜の生菓子に姿を変えた。驚くほどの手ぎわのよさで日々、5種類の和菓子を各300個ほど作るという。もちろん、仕上げは手作業のみだ。松江の和菓子は、不昧公由来の伝統を守りながら革新を続けている。
旅の終わりに松江城の西方の宍道湖へ向かった。松江を愛でた小泉八雲は『神々の国の首都』で、「仄かに淡い夕暮れの色は五分ごとに変わっていく。(中略)色という色が不思議なほどに目まぐるしく移り変わる」と描写している。茜色に染まる宍道湖は刻一刻と色を変えていき、その風景は今も昔も変わらない。

冬の宍道湖の夕景。夕陽は出雲大社の方角に沈んでいき、嫁ケ島と袖師地蔵のシルエットが浮かび上がる。宍道湖は「日本の夕陽百選」にも選ばれ、夕陽の景勝地で知られる。