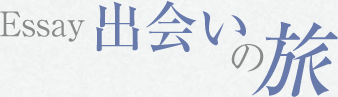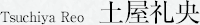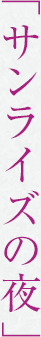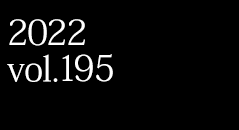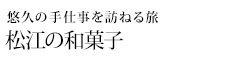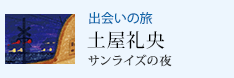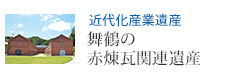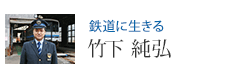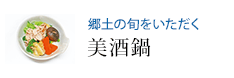1976年生まれ。東京都出身。ミュージシャン。株式会社ワタナベエンターテインメント所属。2001年RAGFAIRのメンバーとして、サングラスと白いファーを巻いた印象的なスタイルでデビューし、全国各地でアカペラ史上最高の観客動員数を記録。紅白歌合戦出場、オリコンシングル1、2位独占、ゴールデンアロー新人賞受賞など、アカペラブームの立役者に。現在はRAGFAIRのほかソロの弾き語りツアーなどでも音楽活動を展開。トークセンスの高さにも定評があるほか、「企業努力鉄」というジャンルの鉄道好きとしても知られ、関連のテレビやラジオ番組に数多く出演中。
ツアーやライブで西日本を行き来する際、帰りはサンライズに乗るのを楽しみにしている。サンライズは山陰エリア・四国エリアと東京を結ぶ寝台特急で、「サンライズ出雲」「サンライズ瀬戸」を岡山駅で分割・連結して運転している。今や日本で定期運行している寝台列車は唯一サンライズだけ、という貴重な存在だ。
メンバーに呆れられながらも、会社が用意してくれた新幹線のチケットを払い戻して、一人だけサンライズに乗って東京に戻る、ということを昔からよくやっている。そうすると、現地に少しでも長く留まれ、現地のイベンターさんと誰よりも親睦を深められる。そういう意味でも、サンライズがなければ出会えなかった仕事がいっぱいある、と言っても言い過ぎではない。
実際、こんなことがあった。金曜の夜に高松でライブ、翌日の夜に大阪でライブというスケジュールのところに、土曜の朝、東京での「タモリ倶楽部」の2本録り収録のオファーが入った。「さすがに無理」と思ったものの、スケジュールの都合でそれまでに1度お断りしていた経緯もあり、なんとか行けないものかと時刻表を調べた。22時までにライブを終えてステージ衣装のまま高松駅発のサンライズに一人飛び乗れば、翌早朝には東京に着く。収録を終えてすぐ新幹線で大阪に向かえば、ぎりぎりライブ本番には間に合う。この緻密なタイムスケジュールを捻出してマネージャーとメンバーを説得し、高松→東京→大阪という綱渡りのスケジュールを敢行したのが2007年のこと。結果、この時の放送がその年の「タモリ倶楽部」の中での1年間視聴率王を獲得し、以降、番組への出演は50回に迫る勢いだ。とんぼ返りした大阪でのライブでは前夜の高松以上によく声が出た。今でも語り草になる最高の2日間になった。それを成し遂げられたのもサンライズの存在あればこそ。日本の鉄道網が正確に目的地に僕らを届けてくれるという奇跡のおかげと感謝している。
寝台列車というのはドラえもんのポケットの道具のようなものだと思う。ベッドに寝て目を閉じる。目が覚めたら目的地についている。サンライズの車内は住宅メーカーと共同で設計されているので居住性も快適そのものだ。時速100キロのスピードの中で、ぐっすり眠れる。これも奇跡だ。
その間に列車はいろいろな管轄をまたいで走行している。JR四国、JR西日本、JR東海、JR東日本がみんなで手を取り合ってサンライズを走らせている。これはある意味、世界平和のミニチュア版みたいなことではないか? なのに、われわれは1回きっぷを買うだけだ。僕たちはそれをあたりまえに享受しているけれど、これはすごいことだ。そのあたりまえの後ろに、どれほど多くの人たちの努力と歴史の積み重ねがあるのかと想像しながら乗るその鉄道の運賃が、なんて安いんだと…。「企業努力鉄」という特殊なジャンルに属する鉄道好きとしては、そんなことを考えながら乗車するのも感謝と至福のひとときだ。
サンライズは、大きな車窓からの夜景も趣きがある。それまで室内灯に照らされて反射していた車窓が、一瞬にして月明かりの夜景に変わるさまはまるで魔法のようで、個室の電気を消す瞬間が何よりも好きだ。世の中が寝静まっている中、働いている人たちが僕らを運んでいく。深夜の車窓を眺めていると、踏切の点滅がホタルの光のように尾を引いていく。ぽつんと明かりがついている民家、あそこには受験生がいるのかもしれない。深夜の踏切でサンライズの通過待ちをしている軽トラは…。車窓にはどんな映画よりも情報が溢れていて想像の物語が際限なくふくらむ。もちろん、目的地にもさまざまな出会いはあるけれど、僕は車窓と会話をする時間そのものを旅の出会いとして楽しんでいる。ちなみに、サンライズのシャワーは6分間。一度計ってみたことがあるのだが、さすがに早発遅延いっさいなく、きっかり正確だった。
もっぱら仕事で使うばかりだったサンライズに数年前、子どもを連れて家族3人で乗り、出雲の観光を楽しむことができたのもいい思い出になっている。僕の教育の甲斐なく、子どもは鉄道にあまり興味を示さないのだが、サンライズにだけは「また乗りたい」と言っている。やはり何かしら他では味わえない「特別感」があるのだろう。次は、まだ寝台列車に一度も乗ったことがないという両親に親孝行の旅を贈りたいと密かに考えている。