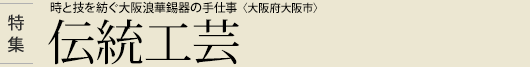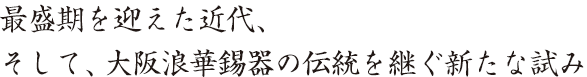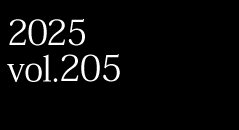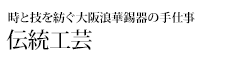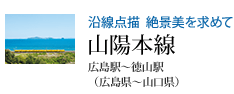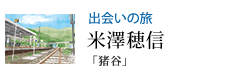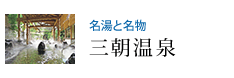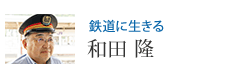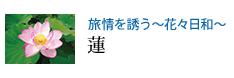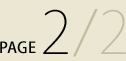

大阪錫器2階のロクロの作業場。壁にはハメギやカンナなどの道具がずらりと並ぶ。

「鋳込み」をする伝統工芸士の今井達昌さん。「手になじむ感覚があるのが、錫のおもしろいところ。水が腐りにくくなるのも特徴で、錫器に花をいけるとガラスや焼きものより2〜3日は長持ちしますよ」と話す。
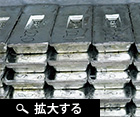

写真左は、錫の地金の丁(ちょう)。写真上は、製作における最も重要な鋳型。全て手づくりで、その数は数千個。
伝統的工芸品「大阪浪華錫器」が、国の指定を受けたのは1983(昭和58)年。当時の錫器製造企業は9社だった。最盛期の大正末期から昭和初期には大阪だけでも300人を超える職人が腕を競い、戦前の大阪では錫器製造業者は40社前後を数えたという。しかし、先の大戦によって職人が招集され、統制で金属の入手も困難となった。工場が焼失し、材料不足や職人不足に伴い、戦後は約半数にまで減少した。そうした厳しい時代を乗り越えて、その伝統を現代に伝えているのが大阪錫器(株)だ。現在、伝統的な技術を用いて生産される国内の錫器製造量の約70%を占めている。
大阪錫器の設立は1949(昭和24)年で、その後、現在の東住吉区田辺に社屋を構えた。その技術のルーツは、江戸時代後期に心斎橋で錫屋を創業した芝伊兵衛に遡る。現在は伝統工芸士5名を抱え、男女20名の職人がものづくりに励んでいる。ここで代表を務める伝統工芸士の今井達昌[たつまさ]さんは、「伝統工芸品は、止まったら終わりや。趣味や道楽ではなく、生活をしているわけやからね」と語る。時代の声に耳を傾け、提案を含めた新たな需要を開拓する。錫器製造業界を牽引する今井さんにとって、それは必要不可欠なのだという。

ぐい呑の表面仕上げをする伝統工芸士。微妙な凸凹を削り表面を滑らかにする。写真右は、ロクロを挽く工程。カンナの切れ味が仕事の仕上がりを左右するため、刃先の調整も職人の重要な仕事。



大阪錫器の作品。左から、吉祥錫タンブラー白(中)、富士山タンブラー朱(小)、タンブラー冷香 白上、タンブラーマニベール(中)、千呂利 六花。

仕事に厳しく、社内で最も信頼が厚いと評判の伝統工芸士 北橋一郎(69)さん。職人歴50年の匠は「中仕事」を担当している。

伝統工芸士の山本宏美さん。現在は加飾を担当している。「錫独特の艶やその柔らかさに、ほかの金属にない魅力を感じます」と話す。
大阪錫器の新作は、伝統工芸品「備前焼」とのコラボ。あたたかみのある土肌とまろやかな口あたりになる錫が合わさった前衛作品。


おでん店「たこ梅」で使われる大阪錫器のタンポと上燗コップ。

「錫にお酒を注ぐと冷めにくく、口あたりが滑らかになります。昔から錫のタンポと上燗コップで熱燗を提供しています」と話すのは、店長の上川菜々実さん。
平成の世は大阪錫器にとって極めて厳しい状況だったという。だからこそその言葉は重い。現在の錫器製造業者の数は4社にとどまるが、今井さんは新たな需要づくりに奔走している。その取り組みの一つが、「焼きもの」との共作だ。日本六古窯[ろっこよう]の備前焼をはじめ信楽焼、伊万里焼など全国の伝統工芸品との共同作で、これまでにない新たな試みを実践している。
大阪錫器の製造工程は、大きく5つに分けられる。工場の1階で行われる「鋳込[いこ]み」は、鍋に錫地金を溶かした「ユ」(液状の錫)を鋳型に注ぐ。鋳型の温度が低ければユがすぐに固まるため、何度も型に注いで鍋に戻す。適切な温度調節を行い、タイミングを見極めながら鋳型を外す。2階では、「ロクロ」を使って切削し形を整える。茶筒などは正確に筒口と蓋を合わせる職人の精緻な技が求められる。壁には無数のカンナが整然と並び、用途によって使い分けられている。隣の部屋では、「中仕事」と「加飾」、そして「仕上げ」の工程が行われる。中仕事では、持ち手や注ぎ口などの付属部分をロウで取り付けるほか、切る、曲げるなどの加工もここで施される。加飾では、ロクロで仕上がったものに絵付けや漆による着色を行う。酸による腐食後に漆を塗っては拭く作業を繰り返す。そうすることで、絵柄は光って浮き出す繊細な作業だ。最後に、仕上げの工程によって艷を出し、大阪浪華錫器が完成する。
大阪道頓堀におでん店を構える創業約180年の老舗「たこ梅」では、大阪錫器の製品が使用されている。美食家でも知られた作家の開高健や池波正太郎も好んだ上燗[じょうかん]は、店の名物の一つだ。底の厚い錫製の上燗コップで嗜むと、口あたりは実にまろやかだ。
大阪浪華錫器はイオン効果が高く、水を浄化するといわれる。だから、酒の雑味が抜けてまろやかになるそうだ。それは、連綿と続く錫ならではの魅力に他ならない。
参考文献/『イラスト図解 世界史を変えた金属』(田中和明 著/秀和システム)、
『なにわ・大阪文化遺産学叢書 8 大阪の伝統工芸ー茶湯釜と大阪浪華錫器』(吉田晶子・宮元正博・千葉太郎 編集/関西大学 なにわ・大阪文化遺産学研究センター)