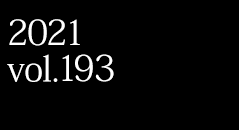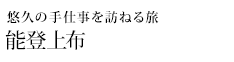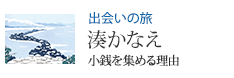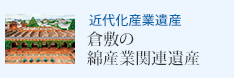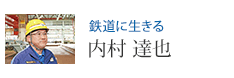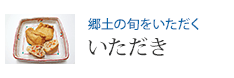江戸時代に幕府直轄地、いわゆる「天領」として、綿やイ草など地域の特産品の集散地として栄えた倉敷。 明治期には、干拓地を利用した綿花栽培の歴史を背景に紡績産業が起こり、その隆盛は町の発展に大きく寄与した。倉敷美観地区の一角、倉敷紡績所の往時の名残を留める赤煉瓦の威容に、近代化に向けた綿産業発展の足跡を辿る。

倉敷アイビースクエアへは、山陽本線「倉敷」駅南口から徒歩約15分。

古くは高梁川流域の物資を積んだ川舟の往来で賑わった倉敷川。山陽本線が開通する以前の倉敷紡績所本社工場の建設にあたっては、木材や煉瓦、板石など多くの資材の輸送は倉敷川の舟運が支えたという。今は、観光客を乗せた「くらしき川舟流し」の舟が、風に揺れる柳並木の川面をゆったりと進んでいる。

創業時の工場全景。北向きに窓を設けた英国式のこぎり屋根は、1日を通して安定的に自然光を取り入れるための建築様式であった。
倉敷川の掘割沿いに並ぶ白壁土蔵や豪壮な造りの商家。美しく、整然とした佇まいで訪れる人々を魅了する町は、およそ400年前までは「吉備[きび]の穴海[あなうみ]」と呼ばれ、大小の島々が点在する浅海であったという。そこへ高梁[たかはし]川上流からの土砂が堆積して干潟をつくり、岡山藩による干拓事業が進められるなど、しだいに陸地へと姿を変えた。干拓された新田には、塩分に強い綿花やイ草が栽培されるようになる。とりわけ、市場で販売できる綿花栽培が盛んで、運河として利用された倉敷川の両岸には、綿をはじめ米やイ草などの問屋が立ち並び、仲買人で賑わったという。富を得た豪商たちが構えた蔵屋敷は、今、美観地区を代表する景観となっている。
江戸時代の綿花栽培の素地は、紡績産業の新興へと受け継がれていく。明治政府は殖産興業を掲げ、各種産業の近代化を進める中で、増加する輸入綿糸を国内綿糸に転換するために民間紡績会社の育成を奨励した。この流れを受け、1888(明治21)年、土地の豪家であった大原孝四郎[おおはらこうしろう]を初代社長に創設されたのが倉敷紡績所(現クラボウ)であった。翌年、イギリス式の最新の機械と設備を導入して操業を開始した本社工場は、綿花と米の集散以外に産業を持たないまま明治を迎えた倉敷に近代産業の礎を築いた。

工場竣工当時は事務所として使われていた洋館。現在は、多目的・挙式スペース「メタセコイア」にリニューアルされている。

倉敷アイビースクエアの中庭広場。蔦と赤煉瓦に囲まれたホテルのほか、レストランやブライダルサロン、体験工房など、古いものと新しいもの、和と洋が調和する複合文化施設。イギリス積みの煉瓦もそのままに残る。


旧混打綿室を改装した現在の「アイビー学館」。英国式紡績工場を模した勾配のある天井、採光用の吹きガラスの窓などに往時の面影を宿す。
創業時の原綿倉庫を改修し、明治から現代に至る貴重な資料を展示した「倉紡記念館」。日本の紡績産業の通史を知ることができる。国登録有形文化財。


記念館の内部は、積み上げた原綿を結露から守った壁の桟や原綿の重さを支えるための分厚い床板など、倉庫として使われていた名残が散見される。
倉敷紡績所は多くの雇用を生み、電力会社や銀行、病院の設立など、町の発展を支えた。こうした事業を果敢に推進したのは、父の跡を継ぎ2代目社長に就任した大原孫三郎[まごさぶろう]であった。地方の一工場を全国でも有数の紡績会社へと導いた偉大な経営者は、奉仕の精神に根ざした様々な社会貢献活動でも知られている。
昭和の戦時下、工場は軍需品の生産を余儀なくされ、戦後は休止工場となった。その後、1969(昭和44)年に社内記念事業として、原綿倉庫を利用して創業以来の資料を展示した「倉紡記念館」が建設される。さらに、倉敷市伝統美観保存条例の施行を背景に、産業遺構の保存や観光施設への再生の機運が高まり、1974(昭和49)年4月、複合文化施設「倉敷アイビースクエア」が工場跡に建設された。
赤煉瓦の外壁は当時のままに、改装する建物も柱や梁などは可能な限り残し活用したという施設には、労働理想主義※1に基づく孫三郎の高い志が息づいている。名前の由来となった外壁をおおう蔦[つた](アイビー)は、夏に葉を繁らせ、冬は落葉して内部の温度を調節する工場空調の役割を果たした。また、衛生的で家庭的な雰囲気の分散寄宿舎の整備、職場環境を科学的に分析する倉敷労働科学研究所※2の設置など、画期的な試みの数々は「倉紡記念館」の貴重な展示に表れる。明治以来の綿産業の伝統は、世界に誇るジーンズ生産や帆布製品へと受け継がれ、新しい歴史を刻んでいる。
- ※1:孫三郎は「労働をより人間的に」を目標に掲げ、工場労働者の環境改善に取り組んだ。
- ※2:現 公益社団法人 大原記念労働科学研究所。