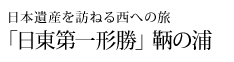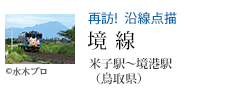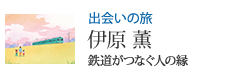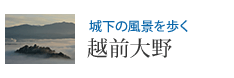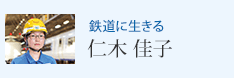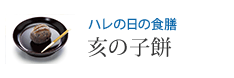225系車両の交番検査において、制御ユニットの点検ポイントを指導する仁木。技術とともに、車両の安全を守るという意識を育んでいく。
大阪府泉佐野市日根野にある車両基地。主に、きのくに線(紀勢本線)や関西空港線、阪和線などで運用される車両が配置され、一定期間走行した車両の検査やメンテナンスが行われる。列車の安全と快適を支える最前線には、培った車両検修の技術で若手社員の育成に励む仁木の姿がある。

顔の見えない電話応対。「明るく元気に」を心がけ、業務を円滑に進める。
学生時代、機械工学を専攻し、自動車を中心に船舶や航空機など、交通系の乗り物の理論と実践を学んだという仁木。その中で、通学でなじみのあった電車に興味を持ち、「鉄道車両を整備する」という仕事に憧れを抱いてJR西日本の「プロフェッショナル職採用(技術)」に応募した。2005(平成17)年4月、車両部門に入社を果たした仁木は、まず吹田工場技能訓練センター※1に配属される。何でも学び吸収したいと意気込んでいたが、「配属された20名中、女性は私1人。同期の男性とは違うカリキュラムで、見ていることも多かった」と当時を振り返る。実習作業では重量物が多く、はんだ付けの作業などは、労働基準法などの法律で全ての女性労働者の就業が禁止されていた。しかし、「与えられたことは前向きに取り組む」が信条の仁木は、制約の多い実習作業の中で、電車の床下に取り付ける10キロ近くある車両部品を持ち上げ、「これ持てます。やらせてください!」と自身を懸命にアピール。次第に同期と同じカリキュラムをこなすようになり、電車の仕組みや配線、配管、内装など車両検修の基礎を身に付けていった。
その後、日根野電車区※2で90日ごとに行う車両の走行装置やブレーキ装置などの検査、吹田工場電車センターでは電車の心臓部といわれる制御器の点検に携わったという仁木。「雷鳥」、「くろしお」、「きたぐに」などに搭載されている制御器内の接触器をコンマ数ミリで調整するという実習を通じて技術を磨き、車両部門における女性技術者の道を切り拓いていった。
※1. 2012(平成24)年6月、組織変更に伴い吹田総合車両所に改称。 ※2. 現在の吹田総合車両所日根野支所。

特急「はるか」の新型車両では、新搭載の機器についての検査項目を説明する。
2007(平成19)年10月に日根野電車区に本配属になった仁木は、この2年後から自身が習得した車両検修の技術を日根野電車区に所属する社員に教えるという業務にも携わった。「人に伝えることは難しく、最初は『こうです』と言い切ることも不安でした。新型車両にデジタル伝送の装置が搭載される時には、まずは自分がしっかり学び、理解してから伝えるように心がけました」と話す。その後、自身が最初に技術の基本を学んだ技能訓練センターに、今度は教える立場で勤務する。作業実習の指導にあたるほか、新入社員研修担当講師にも選ばれ、社会人としての心構えやマナー、時間厳守の姿勢を時に厳しく指導しながら、車両部門の新人の最初の一歩をサポートした。
大きな転機が訪れたのは2015(平成27)年6月。近畿統括本部人事課へ異動になり、新卒の学生をはじめとする採用担当に抜擢された。仁木は、これまでとは異なる仕事内容にとまどう反面、学生にとっても会社にとっても将来を左右する大切な業務という意識で、学生から届くエントリーシートに目を通していたという。会社説明会では、若い社員も同行させることで働くイメージを持ちやすくし、また、福知山線列車事故を惹き起こした会社としての安全対策を真摯に説明した。「採用業務を通して、私自身の会社への誇り、愛着もさらに大きくなりました」と語る。

定期的に行われるミーティングでは、所内の情報の共有化を図る。
今、係長として仁木は再び、自身の原点とも言える車両検修の現場に立ち、日根野支所における教育を担当している。交番検査班を中心とした安全のための活動「A.H.S.T.[アスト](安全な人職場に向けた取り組み)」の推進にもあたっている。係長をめざすきっかけになったのは、かつて日根野電車区で新たな車両情報システム(Ris-e)の導入に向けて地道な作業を続けていた頃の係長の存在だ。「責任は全部取るからやりたいことはやれ」と言ってくれた頼もしい姿が目標なのだという。「私も、若い人たちのやりがいや働きやすさをサポートしていきたい」と思いを語る。
入社当時と比べれば、女性が現場で働く環境は整い、今では仁木も検修当直として泊まり勤務をしている。「女性の先輩がいなかった部門。私が先頭を走ることで、ステップアップのイメージが描きやすくなればうれしい。私自身もさらに上をめざします」。仁木は後輩たちに、女性技術者の未来像を示している。