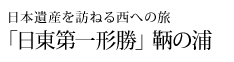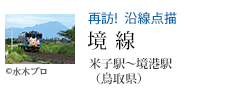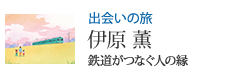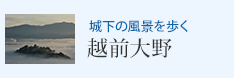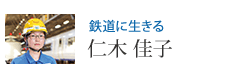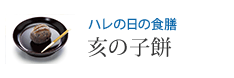日本百名山に名を連ねる「荒島岳[あらしまだけ]」をはじめ、雄大な山々が四方を取り囲む城下町 越前大野。
澄み切った湧き水が築城時のままの町並みを流れ、400年以上続く朝市が今も立つ。
碁盤目状に整備された城下から見上げれば小高い山の頂に町のシンボル 天守がそびえる。

越前大野駅から徒歩で登城口まで約30分。越前大野駅より約2分の京福バスで大野六間バス停下車、徒歩で登城口まで約8分。


大野盆地の中心、標高249mの亀山に築かれた平山城。城郭全体は梯郭[ていかく]式の縄張りで、山頂に本丸、東側の麓に二の丸、三の丸が造られた。現在の天守は、1968(昭和43)年に推定再建されたものだが、「武者登り」(写真下)など天正時代の野面積みの石垣が往時のままに残る。


城下町の東端に計画的に寺院を配置した寺町通り。城下を支配しやすいように、さまざまな宗派が集められた。
古くから、越前と美濃を結ぶ交通の要衝として栄えた大野。南北朝時代には斯波[しば]氏が戌山[いぬやま]城を築くなど、多くの山城が建てられたと伝えられる。越前大野城の歴史は、1575(天正3)年、大野郡の一向一揆を平定した金森長近[かなもりながちか]が、その恩賞に織田信長から領地を与えられたことに始まる。長近は、最初戌山城に入ったが、見通しの良い独立した丘陵の亀山を築城の地に選び、山頂に天守を建築。本丸・天守を守るため、東麓に二の丸、三の丸を配置するなど、4年の歳月をかけて城郭を築いた。同時に、東西6本、南北6本の通りによる短冊型の町割を整備するなど、城下町の基礎をつくりあげた。その後、1775(安永4)年に本丸などを焼失する大火に見舞われる。寛政年間に天守以外は再建されたが、明治維新後に破却された。
現在、亀山の頂には、1968(昭和43)年に元士族の寄付によって推定再建された2層4階の天守・小天守が建つ。再建にあたっては、1679(延宝7)年作成の蓬左[ほうさ]文庫蔵「大野城図」などの絵図や、連結式天守として有名な姫路城、同時代の浜松城や岡崎城を基にしたという。鉄筋コンクリート構造の内部は資料館として活用され、金森家をはじめ、1682(天和2)年から幕末までの約180年間城主を務めた土井家ゆかりの遺品などが展示されている。

城や武家屋敷の生活用水として使われていたことから、「殿様清水」とも呼ばれる「御清水(おしょうず)」。名水の町大野を代表する湧水地として、「名水百選」にも選ばれている。


特産の「上庄さといも」は、大野市上庄地区の豊穣で水はけの良い扇状地で育つ大野在来種。独特の粘りと歯ごたえがあり、煮崩れもしにくい。煮っころがしやのっぺい汁が家庭料理の定番という。
かつて、三の丸と城下を分けた外堀址が残る亀山の麓から山頂をめざす。登城口には、大野藩七代藩主土井利忠を祀る「柳廼社[やなぎのやしろ]」が鎮座する。藩の財政が厳しかった幕末、鉱山の開発や藩船大野丸の建造、藩直営店の大野屋を開くなど、進取の気風で財政改革を成し遂げた名君として慕われた。登り坂の途中には銅像が建つ。山頂では、野面[のづら]積みの石垣遺構が天守を守るようにして威風堂々と構えている。自然石をそのまま積み上げた天正時代の石垣は、水はけが良く風化が少ないそうだ。城主が通る「駕籠道[かごみち]」、侍が使った「武者登り」なども往時の姿を留める。遙かに荒島岳や経ヶ岳、白山を望み、市街地を一望できる城跡は、大野市民の憩いの場所にもなっている。
城の東側に広がる町並みを歩けば、至る所に湧水地があることに気づく。周囲の1,000m級の山々からの雪解け水が、水瓶のような地形の大野盆地に豊富な地下水をもたらすそうだ。城下は、豊かな湧き水を利用して南北の通りの中央に生活や防火のための用水路を設け、町家と町家の境には「背割り水路」と呼ばれる排水路を通した。往時の面影は、今も町割の中に色濃く残る。城に続く大手道として栄えた七間通りには、400年以上の歴史を誇る朝市の伝統が受け継がれている。
※七間朝市は春分の日から大晦日まで、朝7時〜11時頃に開かれている。