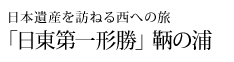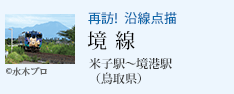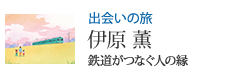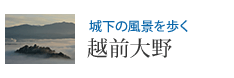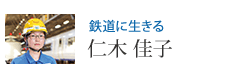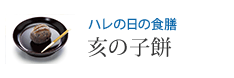境線は米子駅と境港駅を結ぶ全長17.9km。
1902(明治35)年に開通した山陰地方最初の路線で、
境(現:境港)駅〜米子駅〜御来屋[みくりや]駅間の一部にあたる。鳥取県米子駅から弓ヶ浜半島を縦断し、日本有数の漁港町、境港をめざした。

米子駅前の「山陰鉄道発祥の地」の碑とC57型蒸気機関車の動輪。
美保湾と中海に挟まれた弓ヶ浜半島。『出雲国風土記』の「国引き神話」によると、八束水臣津野命[やつかみずおみつぬのみこと]が国土を広げようと弓ヶ浜半島を綱に見立て、その綱で大山を杭に島根半島を引き寄せたという。その弓ヶ浜半島の付け根に位置する米子駅が、この旅の起点だ。
山陰の商都 米子には全国に誇る名湯 皆生[かいけ]温泉の温泉街が美保湾に沿って広がっている。漁師が海岸で源泉を発見したことに始まり、無色透明の湯は口にするとしょっぱい。海に湧く“塩の湯”が、皆生温泉の特徴だ。近年の皆生温泉は、「日本トライアスロン発祥の地」でも知られる。1981(昭和56)年に競技として初開催されてからは、毎年7月に全国から猛者が皆生海岸に集うという。参加者が選抜されるほどの人気だ。
温泉郷を後に、境線が発着する米子駅0番ホームに向かった。愛称名「ねずみ男駅」は怪しげで、ひょっこり他の妖怪も出てきそうだ。境線は境港出身の漫画家 水木しげるの代表作『ゲゲゲの鬼太郎』のキャラクターで町おこしを行っている。ホームには鬼太郎像や仲間たちのオブジェ、階段やベンチにまでキャラクターがペイントされ、派手なラッピング列車が“妖怪の国”へ誘うように停車している。

美保湾に面した皆生温泉。1900(明治33)年に発見された源泉は85度の高温で、神経痛やリウマチ、皮膚病などに効くという。

米子駅の愛称名は「ねずみ男駅」。0番ホームには、『ゲゲゲの鬼太郎』のキャラクターのオブジェやブロンズ像のほか、天井からは妖怪地図が下がる。


「鳥取県の弓浜絣後継者養成研修」をきっかけに、職人になった佛坂さん。畑で綿を作るところから始まり、手で糸を紡ぎ、染色以外の全ての作業を一人で行っている。「製作に時間がかかるので量産が難しい。でも、後世に伝えていきたいですね」。

米子市と境港市を結ぶ全長約17kmの弓ヶ浜海岸。防風林の松原が海岸沿いに広がる。正面に見えるのは霊峰 大山。弓ヶ浜海岸は、「日本の渚百選」や「日本の白砂青松100選」に選ばれている。
乗車した「こなきじじい列車」は駅を離れ、隣の博労町[ばくろうまち]駅、富士見町駅を通過する。次の後藤駅は米子の豪商 後藤快五郎が由来で、米子のまちづくりに尽力したことで知られる。莫大な私財を投じ、御来屋駅〜米子駅〜境駅(現:境港駅)間の線路敷設に貢献した功労者で、地域の感謝の思いからその名が駅名にあてられた。
住宅街を走る列車は河崎口駅を過ぎ、車窓が田畑風景に移ると後方に大山が見える。弓ヶ浜半島のほぼ中央部に位置する弓ケ浜駅は間もなくだ。弓ヶ浜半島には、弓浜絣[ゆみはまがすり]という伝統工芸が今に伝承されている。江戸時代には藩の財政を支えるまでに発展した産業で、原料となる伯州綿[はくしゅうめん]は現在も弓ヶ浜半島で栽培されている。「弓浜絣工房B」で活動する職人の佛坂[ぶつさか]香奈子さんは、「現在、弓浜絣職人は約20名。特徴は厚い生地ながら質感が柔らかいことです」と話す。製作には、約二カ月を要するという。
弓ケ浜駅からほどなく弓ヶ浜海岸に出ると、大山が姿を現している。まさに絵葉書のような風景が広がっていた。

境線を走る“鬼太郎列車”の仲間たち

写真左上:鬼太郎列車、中央上:こなきじじい列車、右上:ねこ娘列車、左下:ねずみ男列車、中央下:砂かけばばあ列車、右下:目玉おやじ列車。

車内の座席や天井にもキャラクターがあしらわれている。
境線には6種類のラッピング列車が走っている。境港出身の漫画家 水木しげるの代表作『ゲゲゲの鬼太郎』に登場するキャラクターがあしらわれた“鬼太郎列車”が、妖怪の愛称名のついた境線の各駅を巡る。車内アナウンスでは実際のアニメの声優が使われ、キャラクターたちが次の停車駅を知らせてくれる。
車両のキャラクターは「鬼太郎」「ねずみ男」「ねこ娘」「目玉おやじ」「砂かけばばあ」「こなきじじい」。どのイラストの列車がどの時間に走るのかは日によって異なる。

島根半島を背後に控える境港駅を出た“ねこ娘列車”。
弓ケ浜駅から再び乗車した列車は大篠津町[おおしのづちょう]駅を過ぎると、やがて大きな弧を描きながら走行する。車窓から飛行機の機体が見えると、間もなく米子空港駅だ。山陰の空の玄関口、米子空港(正式名:美保飛行場)の最寄り駅は、空港の滑走路延長に伴い2008(平成20)年に現在の駅名に改称された。ホームから空港が見えるほどすぐの距離だ。その駅から“鬼太郎列車”に乗り込んだ海外からの観光客が、物珍しそうに車内で記念撮影を楽しんでいる。
列車は高松町駅を過ぎ、余子[あまりこ]駅へ。「次は〜、上道[あがりみち]、上道です。愛称名は一反木綿です」。一反木綿は妖怪の中でも人気で、車内アナウンスが愛称の駅名まで知らせてくれる。隣の馬場崎町[ばばさきちょう]駅を過ぎ、やがて島根半島が迫ると終点の境港駅だ。愛称は「鬼太郎駅」。「ようこそ妖怪の国へ」と書かれた改札をくぐると、駅前の郵便ポストの上から鬼太郎が迎えてくれる。
駅前より東に続く「水木しげるロード」は2018(平成30)年にリニューアルし、再び脚光を浴びている。年間300万人が訪れる800mの通りには177体の妖怪ブロンズ像が並び、日没と同時に全ての像や街路樹がライトアップされる。ライトも色とりどりで、歩道には妖怪の影絵が次々と浮かぶ。それを見た子供たちが、声を上げてはしゃいでいる。通り沿いには、江戸時代創業の「千代むすび酒造」が境港で唯一の酒蔵として店を構えている。スタッフの角田尚智さんは、「2010(平成22)年の連続テレビ小説の反響で街の賑わいはピークに達し、ライトアップで再び増えました。特に、ここ数年は海外のお客様の姿を見ない日はないです」と話した。

近年の境港には大型クルーズ船や米子空港経由で、多くの外国人観光客が訪れている。境港のメインストリート「水木しげるロード」には、日常的に外国人観光客の姿が見られる。


リニューアルされた「水木しげるロード」。日没とともに50種類を超える妖怪が影絵となって路上に映し出される。夜間照明の演出は季節やイベントで内容が異なる。

1865(慶応元)年創業「千代むすび酒造」の角田さんは、「全国有数の境漁港で水揚げされる魚介を肴に、おいしいお酒をご賞味ください」と話す。

伯州綿の弓浜絣

伝統的な定番模様の鶴亀柄。

原料の伯州綿は弓ヶ浜地域で栽培され、「浜綿」とも呼ばれる。ざっくりとした風合いが弓浜絣の特徴。1975(昭和50)年に国の伝統的産業工芸品に指定された。
鳥取県西部弓ヶ浜地方に伝わる弓浜絣は、約250年前より続く伝統工芸だ。弓浜絣は弓ヶ浜地方で栽培される伯州綿を原料に、糸に紡ぎ、藍で染めた木綿の絣織物で、主に農家の女性たちが家族のために作っていた。
特徴は繊維が太く弾力性に優れ、保温性が高いことだ。柄は松竹梅や鶴亀、花鳥風月など伝統的な模様から幾何学、現代模様と豊富だ。約30の工程で最も気を配るのは、絣文様を表現するために染めない糸を一つひとつ括っていく「括り」という作業。現在では着物はもちろん、バッグやブックカバー、眼鏡ケースなどの小物も人気がある。

大漁旗を掲げた境漁港の漁船。境漁港では四季を通じて豊富な魚介類が水揚げされる。

日本有数の水揚げを誇る境漁港。これからの冬の季節は、ズワイガニ漁で賑わう。
というのも、近年の境港では世界の豪華クルーズ客船の誘致に力を注いでいる。漁港として全国有数の水揚げ量を誇る境港には、海に浮かぶ巨大ホテルを思わせる超大型豪華客船をはじめ大型クルーズ船がたびたび寄港している。その影響により、境港には世界から観光客が後を絶たない状況だ。
「国引き神話」の弓ヶ浜半島を“鬼太郎列車”で南北に走る約18kmの短い旅は、『ゲゲゲの鬼太郎』だけにとどまらず見所がたくさんある。温泉や海の幸などの自然の恵み、街のリニューアル、そして豪華客船など、話題の尽きない旅であった。

大型豪華クルーズ船の寄港地 境港

ビルのように巨大な大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」。(総トン数約11万t、全長290m)。

境港を出航した日本が誇る豪華クルーズ船「飛鳥II」。うっすらと大山が見える。
日本有数の漁港で知られる境港には近年、世界の豪華クルーズ船が年に60回ほど寄港している。世界で最も有名な豪華客船で知られる「クイーン・エリザベス」や「ダイヤモンド・プリンセス」、「マジェスティック・プリンセス」。そして、日本最大の豪華客船「飛鳥II」など、錚々たる大型豪華客船が寄港している。
境港は2013(平成25)年に「日本海側拠点港」に選定され、現在は新貨客線ターミナルの整備が進んでいる。2020(令和2)年に新ターミナルが完成予定で、年間100回のクルーズ客船の受け入れを見込んでいる。