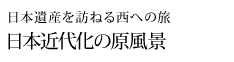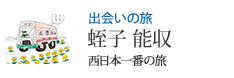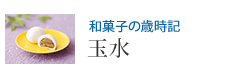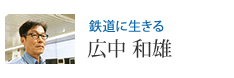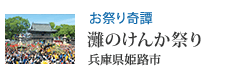山陰本線の園部駅から綾部駅まで42km。
さらに乗り継いで、綾部駅から東舞鶴駅までを結ぶ舞鶴線は26.4km。今回は園部駅から綾部駅を経て、東舞鶴駅までの68.4kmを走る。京都府のほぼ中央を南北に走り、舞鶴湾に臨む舞鶴を目指した。

田園風景の中を走る列車。(和知駅〜安栖里駅)

780(宝亀11)年に和気清麿により開創された京都帝釈天。京都仙洞御所や歴代園部藩主など、多くの人に「願いごとの叶う神」として崇められてきた。

京都府の中央部に位置する南丹[なんたん]市園部は、明治維新後に国内最後の城郭・園部城が築城された城下町だ。城跡の一部は今は高校となっている。江戸時代には京都から山陰に向かう交通の要衝として本陣や脇本陣、そして関所まで設けられた宿場町でもあった。
その市街地から東に離れた山の中腹に鎮座する京都帝釈天を訪ねた。創建は780(宝亀11)年、「庚申[こうしん]さん」で親しまれる古刹だ。近畿庚申信仰の拠点の一つで、700mの参道に108基の「願いの鐘」が数珠[じゅず]のように連なっている。一つひとつ鐘を打ちながら本殿に向かうと、願いが叶うという。
旅の起点は園部駅。3番線ホームを離れた列車はまもなく園部川を渡り、やがて桂川に架かるトラス橋梁を渡り日吉[ひよし]駅に到着した。駅からそう遠くない日吉ダムには、観光スポットとして人気の「スプリングスひよし」が隣接している。ダム建設に伴い、地域振興のために設けられた複合施設で温泉やキャンプなどが楽しめる。
列車はさらに北上し、胡麻[ごま]駅に到着。プラットホームから望める茅葺[かやぶき]屋根は「かやぶき音楽堂」。有名なピアニストのザイラー夫妻が福井県の古寺を移築した音楽ホールだ。国の登録有形文化財のホールでは毎年初夏と秋にコンサートが催され、世界から演奏を楽しみにファンが足を運ぶという。その日に限り、一部特急列車が臨時停車するほどの人気だ。
下山[しもやま]駅を過ぎた列車からの景色はすでに山気を帯び、蛇行する由良川を渡ると和知[わち]駅へ。和知のある京丹波町ではカヌー競技の普及を推進している。由良川の清流をコースにしたカヌー体験が行われるなど、家族連れで大賑わいだ。

かやぶき音楽堂は世界的にピアノデュオで有名なザイラー夫妻が建立。夫のザイラー氏は昨年逝去、和子夫人が継承している。秋のかやぶきコンサートは9月29日30日。10月27日28日は第11回国際デュオコンクールを開催。

由良川をコースにしたカヌー体験を実施している京丹波町。カヌー経験者がいない場合は、指導員がついてくれる。(要予約)

口径95cmの大型天体望遠鏡を所有する綾部市天文館パオ。施設では天文分野以外にもさまざまな体験教室やものづくり教室、イベントなども開催している。

隣の安栖里駅は「あせり」と読む。由良川により土砂が“せり”上がり、“あ”つまったことに因むそうだ。この辺りの風景は緑豊かで、瑞々[みずみず]しい田園風景が広がる。立木[たちき]駅、山家[やまが]駅を過ぎると舞鶴線が乗り入れる綾部駅だ。
大手繊維メーカー「グンゼ」の創業と共に発展した綾部。「蚕都」と呼ばれるほど古来から養蚕業が盛んだった。さらに「綾部市天文館パオ」に立ち寄った。市街地から距離が近く、身近な天文台として週末の観望会も評判だ。

ダムのある複合施設「スプリングスひよし」

日吉ダム直下にある「スプリングスひよし」。温泉や温水プール、体育館やレストラン、物産品販売所などが入る複合施設。

桂川上流域の洪水被害の防止、近畿圏の諸都市への水の供給を目的としている日吉ダム。
日吉ダムに隣接する道の駅「スプリングスひよし」は1998(平成10)年にオープンした複合施設。桂川を挟んだ「ウェルカムプラザ」と「リフレッシュプラザ」の両施設では天然温泉や屋内プール、体育館のほかレストランや地元の新鮮野菜の直売所、キャンプやバーベキューなども楽しめる。
泉質が自慢のひよし温泉は源泉100%の露天風呂。とくに「アロマロウリュウサウナ(熱気浴)」は人気で、抜群の癒し効果が評判だ。最近は南丹市の観光スポットの一つとして、連日観光客で賑わっている。

赤れんがパーク近くの北吸地区の湾には、海上自衛隊の艦艇が停泊する。

伝統的な手漉きの技法を守り続ける黒谷和紙。洋紙や機械漉きの影響から職人数は減少するが、紙漉き職人の吉野さんは「幸いにも、全国から意欲のある職人が集まりました。産業の活性化を図り、黒谷にもっと足を運んでもらえたらと思います」と話す。
舞鶴線に乗り換え、綾部駅を離れた列車は下由良川橋梁を渡って北に向かう。梅迫[うめざこ]駅を過ぎると山あいに入り、谷筋に列車の車窓から「黒谷の和紙」と書かれた看板が見える。
黒谷は800年の伝統を誇る「黒谷和紙」の産地で知られ、その紙漉き和紙の技が現在に受け継がれている。小さな集落を流れるのは黒谷川で、紙づくりに不可欠な清流だ。その畔[ほとり]には「黒谷和紙会館」や作業場があるので、立ち寄った。「黒谷和紙の特徴はなんといっても丈夫、破れません。素朴な質感が魅力です」と話すのは職人の吉野綾野さん。黒谷和紙は主に傘紙や障子紙、襖紙などを生産してきたが、今ではバッグや名刺入れなども手がけているという。

800年の伝統を紡ぐ黒谷和紙

黒谷の集落を流れる黒谷川。

黒谷和紙の拠点、黒谷和紙会館。会館内には資料展示や和紙工芸品の販売コーナーがある。
綾部市と舞鶴市の境に位置する黒谷地区は伝統工芸「黒谷和紙」で知られる集落で、その歴史は800年。平家の落ち武者が隠れ住み、生活の糧に始めたことに由来すると伝わる。
かつては村の住民のほとんどが紙に携わる「紙漉きの里」として栄え、明治期には黒谷村全76戸が紙に従事した記録も残っている。現在の紙漉き職人は9名だが、原料の楮(こうぞ)の処理から加工まで全て手作業で行っている。そうすることで、黒谷和紙の特徴である“強靭”さが生まれるという。黒谷和紙は1983(昭和58)年に京都府無形文化財に指定されている。
列車はトンネルをくぐり、真倉[まぐら]駅を過ぎて西舞鶴駅へ。日本海が深く入り込み、周囲を400m級の山々が囲んだ天然の良港、京都舞鶴西港は駅から約3kmほどだ。かつて舞鶴線の支線として旧舞鶴駅(現西舞鶴駅)から西港を結んだ貨物線が走り、地域の足としても活躍したという。西港の周辺には舞鶴湾の魚介を提供する道の駅「舞鶴港とれとれセンター」が観光客に人気で、寄り道するのもいい。
列車は進路を東に変えて伊佐津川を渡ると終着の東舞鶴駅だ。駅前の三条通りを行くと、東西に走る通りの名称が独特だ。「三笠」や「敷島」、「朝日」など日露戦争時の軍艦名を冠している。舞鶴の東地区は1901(明治34)年に旧海軍舞鶴鎮守府が開庁した軍港都市で、街には旧海軍が築いた赤れんがの建造物が点在している。舞鶴湾に面した「舞鶴赤れんがパーク」の赤れんが倉庫群もそれで、舞鶴線のトンネルや橋脚など、舞鶴には赤れんがの建造物が120以上もあるという。

舞鶴西港にはかつて舞鶴線の支線が走り、主に貨物線として活躍した。1985(昭和60)年に廃止。

舞鶴港で水揚げされた海の幸を直売する道の駅「舞鶴港とれとれセンター」。さまざまな海産物や海産物加工品が店先に並び、レストランも完備されている。
また、戦後の舞鶴港は「引揚港」としても知られ、旧満州や朝鮮半島、旧ソ連からの引揚者を受け入れた。その数は1945(昭和20)年から1958(昭和33)年までの13年間で66万人。引揚桟橋は復元され、『岸壁の母』の歌とともに現在に伝えられている。
京都府の中央部から日本海に抜ける旅は、伝統工芸や近代産業遺産を巡る旅であった。

「引き揚げのまち」として最後まで役割を果たした舞鶴。引揚者が帰国の第一歩を踏みしめた平引揚桟橋は1994(平成6)年に復元された。

東舞鶴を東西に走る通りは、「三笠通り」などかつての軍艦名を冠している。

赤れんがのまち・東舞鶴

赤れんが倉庫が集中して建てられた北吸地区。現在は「舞鶴赤れんがパーク」として人気の観光エリアとなっている。

1904(明治37)年に軍港引込線として設けられたれんが造りの北吸トンネル。海軍施設の物資運搬などに利用されていた。
舞鶴港のウォーターフロントに広がる「舞鶴赤れんがパーク」は、人気の観光スポット。明治期に旧海軍舞鶴鎮守府が開庁したのに伴い、赤れんが造りの海軍倉庫が数多く建てられた。格納庫として利用された赤れんが倉庫が北吸地区に12棟残り、現在は博物館や記念館など往時を伝える展示スペースとして活用されている。そのうち8棟が、国の重要文化財に指定されている。
舞鶴には倉庫以外にも赤れんが造りのトンネルや橋脚が現在に残されており、それらの瀟洒な「赤れんが」の風景はノスタルジーを誘う。