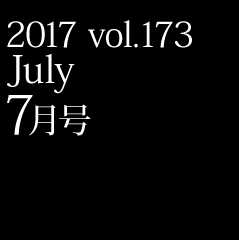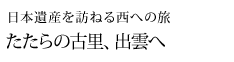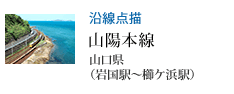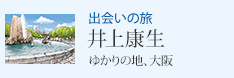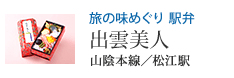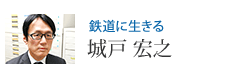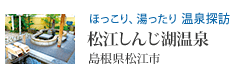- 柔道家。柔道全日本男子監督。東海大学体育学部武道学科准教授。1978年生まれ、宮崎県出身。5歳から柔道を始め、小中高時代全てで全国制覇。東海大学体育学部武道学科卒業。同大学院体育研究科修士課程修了。大内刈、大外刈、背負い投げを得意技とする攻めの柔道を武器に、2000年シドニー五輪男子柔道100キロ級での金メダルをはじめ、世界選手権3連覇、日本選手権3連覇などの偉業を達成。2008年5月に現役を引退し、2年間の英国留学を経て指導者の道へ。2012年のロンドン五輪後に新監督に就任し、2016年リオ五輪で52年ぶりの全階級メダル獲得に貢献した。妻はタレントの東原亜希さん。4児の父。
現役の頃から、よく大阪を訪れている。大阪には、友人や先輩、先生など、知り合いがたくさんいて、旧知の人たちと会って話をするひとときが、私にとってリラックスできる大切な時間になっている。大阪は食べ物がおいしい。大好きな肉はもちろん、ふぐも旨い。お好み焼き、焼きそば、たこ焼き、串カツなど、定番の大阪名物も、行けば必ずといっていいほど食べる。大阪は人との距離が驚くほど近い。見ず知らずの人が、親しげに肩をバシバシ叩いて「元気でやってるか?」と、声をかけてくれて、こちらまで明るく元気にしてくれるパワーがある。頻繁に通ううちに、いつしか大阪という街に特別な親しみを感じている。
けれども、学生時代や現役時代、合宿や大会のためだけに訪れていた頃の大阪は、「キツイ」「苦しい」場所だった。当時は、東海大学の先輩がたくさんいる大阪府警や、野村忠宏さん、篠原信一さんが拠点としていた奈良の天理大学に「単独合宿」というかたちでよく参加させてもらっていた。ホームグラウンドから一人遠く離れ、無意識の甘えや慣れが許されない環境に身を置くことで、自分を追い込み、律し、戒める。柔道は、畳の上に上がれば常に一対一の戦いだ。その覚悟を新たにするためでもあった。受け入れ側の先生や先輩方がつけてくださる稽古は真剣そのもので、当然、練習量は多く、内容も厳しいものになる。体力的な限界に加え、独りである不安との葛藤もあった。そんな単独合宿の経験から得たものは多く、指導者となった今、若手の指導の中に活きている。
京橋駅の近くのホテルに泊まっていた時には、練習の合間にトレーニングがてら、大阪城公園をよく走った。京橋界隈の雑踏から、大阪ビジネスパークの高層ビル群を抜けると、天守閣を取り巻くように広大な緑の公園が広がっている。4キロ余りある公園の外周は、恰好のジョギングコースになっていて、至るところから壮麗な天守閣を見ることができる。森ノ宮駅近くの噴水広場のあたりを走っていると、視界の中を大阪環状線のオレンジ色の車両が通過していくこともあった。コースの途中、外濠を渡って内濠沿いの道をとれば、走行距離をかなり短縮することもできる。日中の練習で疲れ果てている日など、ショートカットして近道を行きたい誘惑にかられることもあった。そんなときは、外濠のみごとな石垣を眺め、建設機材などなかった時代にこれをつくりあげた先人たちの底力に思いを馳せ、自分を奮い立たせた。歴史が好きで、戦国時代や幕末の戦法、歴史から学んだ教訓を、柔道にも取り入れてきた私にとって、織田〜豊臣〜徳川へとつながる大きな歴史の流れを感じられる大阪城は想像を掻き立て、モチベーションが上がる場所だ。ライトアップされた夜の天守閣も、いつ見てもなんとも言えず美しいと思った。
2003年、その大阪城のお膝元にある大阪城ホールで、世界柔道選手権大会が行われた。私にとっては、1999年のバーミンガム、2001年のミュンヘンに続く3連覇を賭けた戦いだった。その狭間の2000年にはシドニー五輪での優勝があり、大会当日が近づくにつれて言い知れない恐怖と重圧が膨れ上がっていった。そんな中で優勝を果たし、3連覇を達成できたことで、大阪という地はより深く私の心に刻まれることになった。現役時代の自分を一回りも二回りも成長させてくれた街。それが大阪なのだとあらためて思う。
2008年に現役を退き、家族ができてからは、プライベートで大阪を訪れる機会も増えた。初めて、試合や合宿のためではなく、ただ純粋に旅をすることの楽しみを知った。以来、親しい友人家族と一緒にUSJに遊びに行くなど、大阪で過ごす時間を心から楽しんでいる。旅の喜びを発見したことで、新たな関心も広がってきた。いつか子どもたちの手が離れたら、夫婦でゆっくりお隣の京都へも足を延ばし、日本文化の奥深さに触れる旅などもしてみたいと思っている。