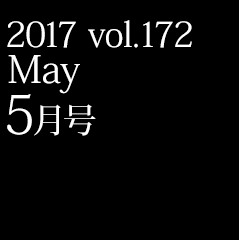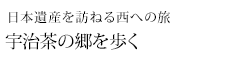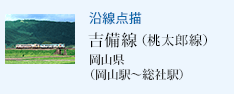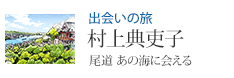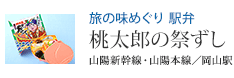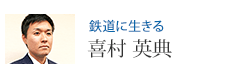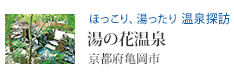岡山駅と総社駅を結ぶ吉備線の愛称は「桃太郎線」。
距離約20㎞、駅数10駅という短い路線だが、
沿線はそこかしこに日本の原風景が広がる。
「鬼退治」伝説が残る吉備路を訪ねた。

吉備線は岡山駅の10番線から出る。線路脇には起点を示す、「0キロポスト」がある。


大安寺駅を過ぎると笹ヶ瀬川を渡る。「桃から生まれた桃太郎」で知られる昔話『桃太郎』で、桃が流れてきた川とされる。
吉備線の駅名表示板のフレームは、「桃」を連想させるピンク色。

吉備線を走るラッピング列車。桃太郎やサル、イヌ、キジなどのキャラクターがあしらわれている。
岡山県のシンボルといえば、日本中の誰もが知っている昔話のヒーロー、桃太郎。桃から生まれた桃太郎はサル、イヌ、キジを従えて鬼退治に出陣。そんな勇ましい姿の銅像が岡山駅の東口に立っている。そして鬼退治一行が向かった先というのが吉備路。吉備線の沿線は桃太郎の原風景でもある。
吉備線は岡山駅の10番線から出る。ホームの列車には桃太郎のアニメキャラクターがラッピングされている。エンジンが始動し、岡山駅を離れると車内案内に「も〜もたろうさん、ももたろうさん…」のメロディーが流れ、すぐに備前三門[びぜんみかど]駅。ホームの駅名表示板の枠は桃に因んでピンク色だ。列車は住宅地を縫って西へ。大安寺[だいあんじ]駅を過ぎると肥沃な田園地帯が車窓いっぱいに広がった。
話は古代に遡[さかのぼ]る。古代の吉備国は大和政権と並ぶほどの大きな勢力を有する大国で、豊かな穀倉地帯と瀬戸内海の海産物、優れた製鉄技術を背景に大和を凌ぐほどに栄えた。奈良時代に備前、備中、備後、美作の4国に分割されるまでは実に広大な領土を持っていた。この吉備国の中心地だったのが現在の吉備線の沿線である。

大吉備津彦命が御祭神の吉備津神社。本殿・拝殿の比翼入母屋造の優美な建築様式は「吉備津造」とも言われ、国宝に指定されている。
吉備国に飛来し蛮行を重ねていた異国の王子「温羅[うら]」。大和朝廷は平定のために武勇に優れた皇子を派遣する。皇子とは大吉備津彦命で、家臣は楽々森彦命[ささもりひこのみこと]に犬飼建命[いぬかいたけるのみこと]、留玉臣命[とめたまおみのみこと]。朝廷に敵対する「温羅」は「鬼」として登場し、ついには討伐される。『吉備津宮縁起』に記された話をモデルに生まれたのが昔話の『桃太郎』だという。


備前の国の一宮として信仰を集める吉備津彦神社。御祭神の大吉備津彦命は、昔話『桃太郎伝説』の桃太郎のモデルとされている。
吉備津彦神社の境内には桃があしらわれた絵馬が掛かる。
備前一宮[びぜんいちのみや]駅すぐ近くの「吉備津彦神社」には、桃太郎のモデルの大吉備津彦命が祀られている。また隣駅の吉備津[きびつ]駅には「吉備津神社」があり、祭神はやはり大吉備津彦命。まぎらわしいが前者は備前国一宮で、後者は備中国一宮。特に吉備津神社の「吉備津造」の本殿・拝殿の建築様式は全国でも唯一。過去、火災で2度焼失したが、室町時代に足利義満が再建し、現在では国宝に指定されている。
吉備津神社には、大吉備津彦命によって討伐された鬼、温羅の首が竈[かまど]の下に埋められたと伝わる重要文化財の御竈殿がある。温羅の唸り声で吉凶を占う鳴釜神事[なるかましんじ]は古来より知られていて、現在も古式のままに執り行われている。

県の重要文化財に指定される吉備津神社の廻廊。1579(天正7)年に再建され、全長360mで、自然の地形のままに一直線に建てられている。

釜の鳴動で吉凶を占う「鳴釜神事」。国の重要文化財に指定される御竈殿の竈の下には、退治された鬼の温羅の首が埋められていると伝承されている。

吉備線から見える最上稲荷の大鳥居の高さは27.5mを誇る。最上稲荷は1250年前に報恩大師によって開かれたと伝わる。


足守は陣屋町として約250年にわたり繁栄し、街道沿いには商家が次々と築かれた。西洋医学を日本に伝える礎を築いた蘭学者、緒方洪庵の出生地でも知られる。
列車は吉備路をさらに西へと走る。田園風景の中に立つ巨大な鳥居は、岡山県下で最多の初詣客で賑わう最上[さいじょう]稲荷。最寄りの備中高松駅の旧名は「稲荷駅」といい、その昔、最上稲荷まで参詣のための稲荷山支線が走っていた。駅近くには、羽柴(豊臣)秀吉の「高松城水攻め」で有名な備中高松城跡がある。現在は歴史公園になっていて築堤跡の一部が残っている。
水攻めに利用した足守[あしもり]川の鉄橋を渡ると、足守駅。足守は北政所[きたのまんどころ](豊臣秀吉の正室・寧々)の実兄、木下家定が領有し、以後250年栄えた陣屋町。本瓦と格子の商家、白壁と長屋門の侍屋敷は保存状態も良く、当時の佇まいを残す。大坂の蘭学塾「適塾」を主宰した緒方洪庵[おがたこうあん]の生誕地でもあり、画聖の雪舟[せっしゅう]の生誕地も近くだ。
そして、鬼退治一行の楽々森彦命はこの足守の豪族だった。この付近は、桃太郎と鬼が激しい戦いを繰り広げた舞台となる。足守川の支流である血吸川[ちすいがわ]の由来は、大吉備津彦命が射た矢が温羅に刺さり、流れた血が川となったことに因む。双方が放った矢と石がぶつかって落ちた伝承の「矢喰宮[やぐいのみや]」もある。


吉備路には「桃太郎」ゆかりの地が点在する。写真左の矢喰宮は、大吉備津彦命が放った矢と温羅の投石がぶつかり合い、落下した地と伝承される。写真右は、矢の命中した温羅から流れる血が川となったと伝わる血吸川。
足守駅を過ぎ、服部駅に向かう。列車の右手に険しい鬼城山が車窓に映る。目を凝らすと山頂近くの斜面に石垣や砦のような建造物が見える。温羅の居城、鬼ノ城だ。昔話の桃太郎では鬼ヶ島とされたが、古代、周辺は「吉備の穴海」と呼ばれる内海で、鬼城山も島のようだったのだろう。学術的には古代朝鮮式山城で貴重な史跡である。

鬼城山の山頂に築かれた鬼ノ城。鬼の温羅がこもった城とされ、眼下に吉備平野が見渡せる。

備中国内324社の神々を合祀した備中国総社宮。
東総社[ひがしそうじゃ]駅を経て、終着の総社駅に着く。総社とは備中国324社の神々を合祀した「備中国総社宮」をいう。周辺には造山[つくりやま]古墳や作山[つくりやま]古墳をはじめ巨大な古墳や史跡が点在し、奈良時代に聖武天皇が発願し建立された備中国分寺の五重塔が佇む。どれもが吉備路の栄華を伝え、悠久の歴史を語りかけてくるようだ。昔話の桃太郎が日本の古代史と重なってくる吉備路の旅は古代ロマンに満ちている。

奈良時代、聖武天皇によって建立された備中国分寺。田園風景の中に聳える五重塔は吉備路を代表する風景。近くにはサイクリングロードが延びる。

吉備路には古墳や史跡が点在する。古代吉備国の王の墓とされる造山古墳は、県下最大で全国4番目の規模を持つ全長350mの前方後円墳。
岡山市から総社市まで約21kmのサイクリングコースが整備されていて、吉備路の自然を満喫しながら自転車で遺跡や史跡を巡るのもいい。目的に応じてコースを選べば旅はさらに楽しくなる。

備中国分尼寺跡は、奈良時代に聖武天皇の発願で建立。今では礎石や築地塀跡の一部が残るのみだが、広大な敷地は当時の栄華を物語る。
ここでは桃太郎のモデル、大吉備津彦命を祀る備前国一宮の吉備津彦神社からスタート。そこから備中国一宮の吉備津神社へ。こんもりとした形の秀麗な「吉備の中山」は『万葉集』にも詠まれている。大吉備津彦命が眠る山の麓を走る。山中を流れる細谷川が、備前と備中の国境になっている。標識に従い、西に向かうとゆるやかな地形の吉備平野を見晴らす。見渡す限り田園風景。なんとも、たおやかな風景だ。足守川沿いのサイクリングロードを進むと、吉備の王墓とされる造山古墳が姿を現す。周囲には中小規模の古墳が方々に点在していて、吉備国の往時の栄華を偲ぶことができる。



1905(明治38)年創業の三宅酒造5代目当主の小澤さん。「総社の蔵元は現在、2軒だけです。岡山は肥沃な米どころということもあり、かつては県に200軒以上も蔵元があったそうです」と話す。伝統の技法や酒造りの道具を展示する資料館もあり、代表銘柄の「粹府 媛」は、吉備の酒米を使用している。
ゆるやかな丘陵地に聳[そび]える備中国分寺の五重塔。「いいでしょこの風景。国分寺の風景はずっと変わりません。現在でも地中を掘れば遺跡や土器が出土します。そういう土地です」と話すのは、備中国分寺近くの酒蔵「三宅酒造」の5代目当主の小澤佑二さん。最近は海外の方が自転車でよく来るそうで、道案内もするという。ゆっくり巡って3時間。夕陽に染まる吉備路はまさに万葉の世界そのままだった。