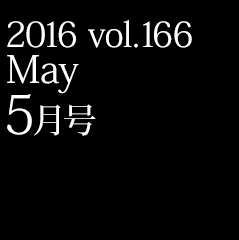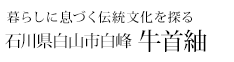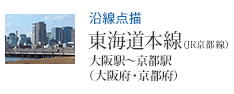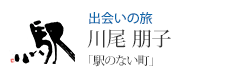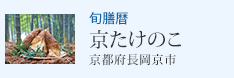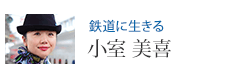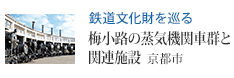![]()
京都盆地の西南端、西京区大原野から向日市、長岡京市、大山崎町へとつながる乙訓[おとくに]地域は、全国的に名高い「京たけのこ」の主産地である。
西山丘陵に広がる竹林で栽培されるたけのこは、色白で美しく、甘くやわらかな肉質を誇る。
3月下旬から5月にかけての最盛期、地域はまさに「竹の旬」に活気づいている。


掘り出したたけのこの水分が抜けきらないうちに、手早く調理するのがおいしい食べ方。定番の「若竹煮」の他、地元では刺し身や天ぷらで旬を味わう。
乙訓地域におけるたけのこ栽培の歴史は古く、本格的な栽培が始まったのは江戸中期といわれている。竹の品種は、中国から伝わった食用たけのこの代表モウソウチク(孟宗竹)。来歴については、宇治黄檗山萬福寺を開山した隠元禅師によってもたらされたとも、その4代目の管長が中国留学の際に株を持ち帰り、長岡京市にある寂照院境内に分植したとも伝えられる。
現在、西山一帯の785haの竹林のうち、およそ200haで京たけのこが栽培されている。生産量は全国の1割程度に過ぎないが、その品質は日本一といわれ、中でもえぐ味が少なく、まっ白でやわらかな肉質の「シロコ」は、最高級品として名高い。この地域のたけのこが良質な理由としては、まず土壌条件が挙げられる。京都盆地周辺の丘陵地は、大阪層群海成粘土という古来からの地層で形成されている。そのため、土壌は酸性の赤粘土で、土質はやわらかくて水はけが良く、竹の生育には最適という。もう一つは、この地域に受け継がれている「京都式軟化栽培法」と呼ばれる栽培方法にある。春の収穫と並行して新しくたけのこを生む親竹を選別し、その親竹が必要以上に伸びないように「しん止め」をすることや、秋から冬にかけては「敷きワラ」や「土入れ」を施すことなど、季節ごとに周到な管理が行われるのが特徴だ。肥料は、収穫後のお礼肥え、夏肥え、冬肥えの年3回。こうした「たけのこ畑」で育てられたものだけを、京たけのこと呼んでいる。

「京都式軟化栽培法」は、その収穫にも独自性が光る。たけのこは、穂先がわずかに地面に現れただけでも、太陽に当たって色が黒くなる。また、空気に触れることで硬くなり、味が落ちる。そのため、たけのこが地上に顔を出さないうちに掘り起こすのがこの地域の習わし。土中に隠れているものを収穫するからこそ、京たけのこの皮は白っぽく、中身はやわらかくみずみずしいのだという。姿が見えないたけのこを掘り出すのには、「ホリ」と呼ばれる金属部分が長い特殊な掘り鍬が使われる。その道具を自在に操り、傷一つ付けずに取り出すのはまさに名人芸。京たけのこの品質は、地元農家の熟練の技が支えている。
長岡京市で代々続くたけのこ農家を営む春田忠男さんも、そんなベテランの一人として伝統の栽培方法を守り続ける。緩やかな丘陵地に広がる竹林は、親竹が一定の間隔に間引かれて並び、美しく整備されている。毎年冬になると、稲ワラの上に赤土を重ねて敷きならすという自慢の「畑」は、歩くとじゅうたんのようにふかふかだ。この土入れによって、春たけのこが伸びてくると地表面にひび割れをつくり、居場所を知らせてくれるという。収穫の時期、春田さんは日の出とともにひび割れを探り、土中の形や大きさを推測しながら手際良くホリを扱う。「朝掘り」は、えぐ味もなく甘さも格別。京たけのこ本来の滋味に富んでいる。竹林に次の旬を担う若竹が育つ頃、季節は春から初夏へと歩みを進める。

稲ワラを敷き詰め、その上に土をかぶせる「土入れ」を毎年繰り返すことで、ふかふかの土壌になる。ワラは水分を蓄え、地温の低下を防ぐ役割も果たす。

ホリをたけのこの周囲に刺し込み、先端の刃先で竹の地下茎(根)から切り離す。穂先の動きで向きや大きさを推測し、皮を傷つけずに掘り出すのは名人の技。

えぐ味が少ない京たけのこは、アク抜きの糠[ぬか]を入れずに下茹でする。たけのこの食感と彩りを楽しむ「木の芽和え」は、春を感じる逸品。