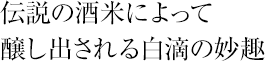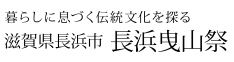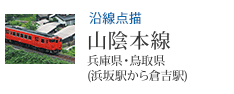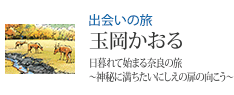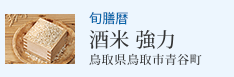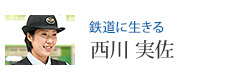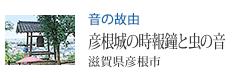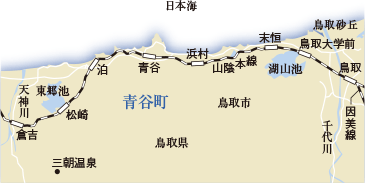
![]()
鳥取県を原産とする「酒米 強力」は、
現存する酒米の中で最も丈の長い品種とされる。
穂先までの長さは、人の背丈にも近い150cm。
その太くたくましい稲姿は、名前の由来ともいわれている。
秋に実った珠玉の粒は、雪深い風土に育まれ
豊穣のしずくへと姿を変える。
郷土の米と水が醸す、「地酒 強力」の旬を訪ねた。
強力は、明治時代の中頃、名峰大山の麓の村で生まれたと伝わる。1921(大正10)年には鳥取県の奨励品種に採用され、最盛期は県内の稲作面積の3分の1を占めるほど、米どころを代表する特産米であった。当時、強力には食用米と酒米の2種があり、特に酒米は酒造家垂涎[すいぜん]の的と評される品質を誇っていたそうだ。しかし、丈が長いため倒伏しやすく、病気になりやすいなど作付けが難しい。そのうえ収量も少ないため、生産効率が重視される時代の流れの中でしだいに栽培されなくなり、昭和20年代後半には姿を消してしまった。

交配していない源原種の強力は、他に類似しない独特の酸味やコクを持つ。燗にも向いており、酒肴には魚の煮付けなどが合うそうだ。
通常、米粒の周辺は脂肪分やたんぱく質が多く、中心になるほど純粋なでんぷん質になる。ご飯として食べる際には旨みとなる脂肪やたんぱく質も、酒造りには雑味となって現れる。晩稲[おくて]の大粒品種 強力は、たんぱく含有量が少なく割れにくい、まさに酒造りの優良種。また、中心部分は「線状心白」と呼ばれるでんぷん質形状で、高精米歩合(※1)に向くという。1979(昭和54)年、精米や醸造技術が飛躍的に進化した時代の酒造りを試したいという地元の蔵元の熱意によって、幻となっていた酒米復活の取り組みが始まる。幸運なことに、強力の種籾は、鳥取大学農学部に研究用として原種保存されていた。そのわずかな種籾をもとに、気概ある農家の協力を得ながら栽培に着手。強力は少しずつ稲穂を実らせ、1989(平成元)年秋、ようやく桶1本分を仕込める量が収穫できた。その後は、地域の農産文化としてデータが公開され、県内の農家で広く栽培されるようになった。

今、強力は、生まれ故郷の大山町をはじめ、八頭[やず]町、若桜[わかさ]町など県内の山間部を中心に栽培されている。化学肥料も農薬もなかった時代に生まれた稲は、近代農法に当てはめると、持ち味を発揮しないという。そのため、栽培の基本は、化学的なものは極限まで抑える、もしくは使用しない昔ながらの有機農法。また、土壌は河川の影響を受けることから、水量・水質ともに豊かな川のそばなどが栽培田に選ばれている。
昭和の終わり、幻の酒米復活に取り組んだのは、鳥取市内の蔵元2軒。その一つ、山根酒造場は「醸は農なり」の信条を掲げ、 高精白低温発酵(※2)による純米吟醸酒として甦った郷土の酒「強力」の伝承に努めている。酒造りを米作りの延長線上に位置付けるこの蔵元では、使用する酒米は全て完全契約栽培。強力にいたっては、蔵を守る杜氏自らも田んぼで育て、米作りの段階から特有の性質を見極めながら、酒造りに生かしているそうだ。
晩稲の強力は、10月に入る頃から収穫が始まる。刈り取られた稲は、水分量13〜14%以下に乾燥させ、11月の蔵入りを待つ。現在、強力を醸造する蔵元は県内で9軒。各蔵元が個性を競い合っている。同じ強力を使っても、醸造法や蔵人の手が変わることによって、醸された酒の味にはそれぞれの蔵の特徴が色濃く現れる。熟成期間を長く設けることで、旨み成分のバランスが整い“味が化ける”といわれる 酒米 強力。発酵の冬、熟成の夏を越え、再び巡る秋に味わいの旬を迎える。

他種と比べると丈が長く、太くたくましい強力の稲(写真左4本)。強力米生産農家は、難しい肥料設計のデータなどを蓄積し、技術の継承にも努めている。

酒の味を左右するともいわれる重要な蒸し米の工程。甑(こしき)と呼ばれる巨大な蒸し篭で、強力に合った最適な「蒸し」が行われる。