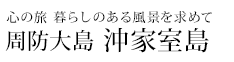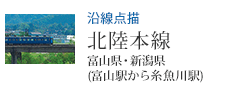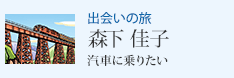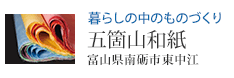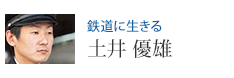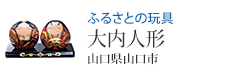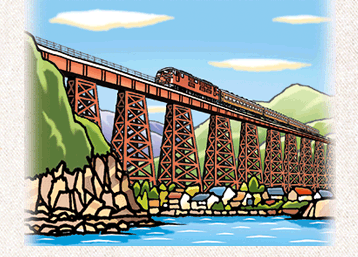

- 1971年1月24日生まれ。大阪府高槻市出身。脚本家。東京大学文学部宗教学科卒業。子どもミュージカル劇団に入り、バックダンサーとして舞台に立つ。学生時代は劇団「パンパラパラリーニ」をたちあげ演出・脚本を担当。
社会人になってシナリオセンターで学び、プロットライターとしてデビュー。プロットライター時代に『平成夫婦茶碗』(2000年、日本テレビ)で脚本家としてデビュー。TBSドラマ『世界の中心で、愛をさけぶ』で雑誌『ザテレビジョン』のドラマアカデミー賞(2004年夏クール)脚本賞を受賞。NHK朝の連続テレビ小説『ごちそうさん』で第32回向田邦子賞を受賞。
子供の頃、「汽車」に憧れていた。普段の生活の範囲内で電車を利用する事はあったのだけど、旅をするための電車――それは私の中で電車ではなく汽車と呼びたいようなもの――に乗った事がなかったからだ。
我が家の旅の足はもっぱら、オンボロの中古車だった。理由は簡単で、幼いうるさい子供を2人連れて移動するのには車の方が便利だし、切符代よりガソリン代の方が安くついたから。我が家はよく父の運転する車で小旅行に出かけた。こう書くと、何やら温かい思い出のようだが、その実態は、中々に壮絶な貧乏旅行だった。
どんな風に貧乏かというと、まず宿は取らない。雨露をしのぐのは父が会社で借りてきたテントだ。「アウトドア。いいじゃないですか」と思われるかもしれない。だが、父は「あんなん払わんでよろし」と、キャンプ場の場代を払おうとしなかった。ゆえに、まず、我が家はキャンプを張るところを探さねばならない。大切なのはあれこれうるさく言われないようなところ。そう、それはもう「キャンプ」というより「野宿」と言う方が正しい。
確か、福井の丹生海岸に行ったときのこと。まっとうなキャンプ場を横目で見る私たちに「ええとこあったで〜」と、父が見つけたのは断崖絶壁とまではいかないものの、切り立った岩場の合間に抱かれたような海岸だった。確かに見つかりはしないだろうが、そのかわり何もない。灯りもない、トイレもない、水道すらない。その水道すらないところでは海水で米を炊く。父が釣ってきた魚も潮で洗って焼き、食事をとる。「ここ、大波来たら一発やなぁ」としゃれにならない冗談に笑う。我が家の旅はいつもそんな感じだった。
それがゆえに一度だけのっぴきならない事態に陥ったことがある。淡路島にあじを釣りに行ったときのこと。父が車中に鍵をおいたまま、ドアを閉めてしまったのである。これはもうどうにもならないと、JAFを呼ぼうと言うことになった。
だが、相当に辺鄙な場所で、人家は見当たらず、ボーイスカウト用の小さな小屋がひとつあるのみ。そこに電話を借りに行ったのだが、なんと電話がない。ボーイスカウトの方たちも、一緒になって電話を探してくれたのだが、どうにもならなかった。疲れきった私は父を恨んだ。
「普通の旅館に泊まってたら、電話がないなんてことない。お父さんのせいや。お父さんがケチやからこんな事になるんや!」そう思ったとき、大きな石を持った父が戻って来て、やおら、その石をサイドガラスめがけて力一杯振り下ろした。
粉々になるサイドガラス。唖然とする私たちを前に、父は「ほな、帰るで」と、何事もなかったかのように車のドアを開けた。座席にビニールシートを敷き、びゅうびゅうと風が吹き込む車で大阪まで戻ったのだった。
こんなことがあったのだし、さすがにこりそうなものだが、能天気なのかケチなのかアホなのか、多分その全部であるがゆえ、車の旅はその後も続いた。だが、その中で私はちょっとしたご褒美をもらった。
ある年、舗装もされていない道を越えて、人気のない静かな浜にテントを張った。いつもと同じような旅行だったが、そこからは緑の山をつなぐ余部鉄橋とそこを走って行く「汽車」が見えた。私の目はその風景に目が吸い付けられた。緑に映えた鉄橋の赤はとてもきれいで、そこを走る「汽車」は格好よかった。乗れたわけではない。けれど、すごくすごくいいものを見たような気がした。
貧乏旅行の果てに出会った、私の思い出の風景である。