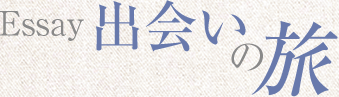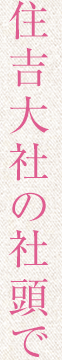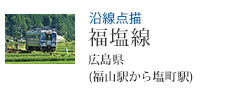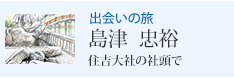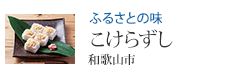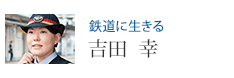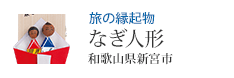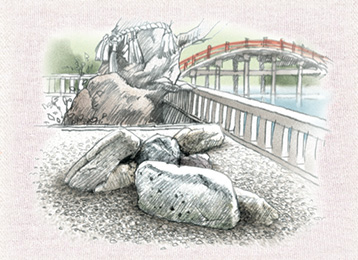
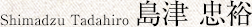
- 昭和47年鹿児島市生まれ。島津家第32代当主島津修久氏の嫡男。株式会社島津興業代表取締役副社長。平成8年株式会社日本興業銀行(旧みずほコーポレート銀行)入行。平成16年当社入社、平成21年から現職。平成23年照國神社および鶴嶺神社の権禰宜。
大阪は、島津家発祥の地である。意外と知られていない。島津家の公式記録によれば、家祖 忠久は源頼朝公の長庶子と記されている。忠久の母 丹後局は、頼朝公の側室として寵愛を受けていたが、忠久を身ごもるや、正室 北条政子の嫉妬を買うところとなり、鎌倉を追われた。わずかの供と上方に逃れる途中、局は摂津国で産気づき、住吉大社の境内で忠久を出産した。夜更けのお産を、末社の稲荷社(楠珺社)の神狐がご神燈を掲げて見守ったという言い伝えから、島津家では、代々、稲荷信仰が厚い。合戦や家運を賭けた重大事の前に、神狐が現れて嘉瑞を示した、という説話には事欠かない。鹿児島には「島津雨」という言葉がある。忠久が誕生した夜はひどい大雨だったという故事から、生まれた言葉である。そのため、鹿児島では雨は吉兆とされてきた。今でも、慶事の日に雨が降ると、お互い「今日は島津雨ですね」といった挨拶が交わされている。
住吉大社の反橋をわたった左手に、石玉垣に囲まれたひと抱えほどの大きさの霊石がある。この石にすがって、丹後局は無事に忠久を出産した。それ以来、「誕生石」と呼ばれ、安産祈願の信仰を集めるようになった。篤姫(天璋院)が将軍家に輿入れするために参府したときも、ここにお参りしたと記録されている。また、島津家の歴代藩主も参勤交代の途路に立ち寄り、狐灯の故事にならって、高張提灯を奉納したと伝えられている。
私が誕生石に初めてお参りしたのは、平成22年の春のことである。それまではご本殿への参拝ついでに、「島津家にまつわる石碑のひとつがあるらしい」程度の気持ちで立ち寄っただけだった。当時、妻との間には娘を二人もうけていた。次女が幼稚園に入園して、育児も少しく手が掛からなくなった。そんな頃合いを見はからって、そろそろ男児を授かりたいと思い、先祖の故事にならってお願い事をした。そして妻には内緒にしておいた。私は簡単に800年来の由緒と言うが、彼女にとっては800年分の重圧になる。言わず語らずのプレッシャーを感じているところを、さらに追い立ててしまうような気がした。ひとまず、住吉大社に参拝してきた、とだけ話しておいた。翌年の夏、第三子が生まれた。男児だった。嬉しさがこみ上げるのと同時に、住吉大社のご神威と誕生石の霊験が頭に浮かんだ。
名前を付けなければならない。島津家の通字は、長男は「忠○」、次男は「○久」という要領なので、ひと文字だけ考えれば良い。先祖と同じ名前は遠慮するので、選べる範囲は広くない。今にして思えば気の早い話だが、二十歳のときに、亡き祖父と考え合わせていたので、命名に時間はかからなかった。
そのような一連の段取りを片付けたところで、住吉大社に御礼参詣に伺った。高井権宮司(現宮司)と神武権宮司には、殊のほか、喜んで頂いた。あわせて、これを結縁に誕生石を斎場にして初代忠久の誕生記念祭を執り行いましょう、とのご提案を頂いた。光栄なお話である。九州新幹線が全線開業して、関西と鹿児島が一層近くなった頃合いでもある。相互の交流拡大につながる象徴なりきっかけなりにしたいとの思いもあって、謹んでお受けすることにした。住吉大社はかつて官幣大社に列せられたお宮である。祭典の格調・品格に相応した奉納品を用意しなければならない。島津家に「島津忠久誕生図」がある。元々は住吉大社のご宝物だったが、江戸後期に薩摩藩大阪屋敷の藩役人が借受けて模写した画だ。
その後、原画は難に遭い、所在不明のままになっている。そこでこの絵図を再復写してお納めすることにした。また、先祖のならいに従って、丸十紋の高張提灯もあつらえた。
平成25年4月、住吉大社の神職・巫女の方々の助勤を仰いで、父 修久(照國神社宮司)が斎主となって祭典を執り行うことができた。在阪の鹿児島県関係者をはじめとして120名ほどの方々にご参集頂いた。また、忠久誕生の折に産湯と湯薬をすすめてくれた社家の末裔の方や、住吉大社御用達で「さつま焼」を看板商品にもつ菓子商のご当主など、ゆかりの方々にもご参列頂いた。神事の最中に軽雨が走り過ぎた。感慨一入である。直会でも、もっぱら島津雨の再来が話題になった。
大切なものは、往々にして目には見えない。目に見えないからこそ、大切にするし、信じて守り続けなければならないものがある。ひとの心、思いやり、優しさ、絆・・・思いのほか、多い。いつの日か、島津家発祥の地である住吉大社の社頭で、このことを長男に語り継ぎたいと思っている。