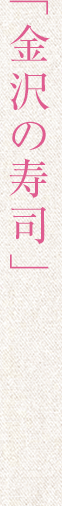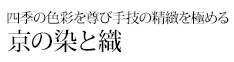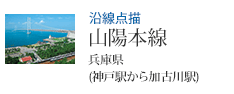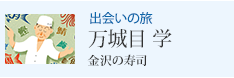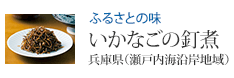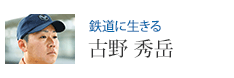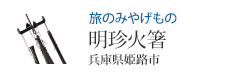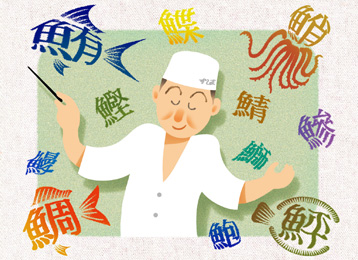
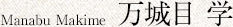
- 小説家。1976年生まれ、大阪府出身。京都大学法学部卒業。2006年、第4回ボイルドエッグズ新人賞を受賞した『鴨川ホルモー』でデビュー。『鹿男あをによし』『プリンセス・トヨトミ』『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』で直木賞候補に。他の小説作品に『ホルモー六景』『偉大なる、しゅららぼん』、エッセイ集に『ザ・万歩計』『ザ・万遊記』がある。現在、「週刊文春」にて伊賀の忍びを主人公にした『とっぴんぱらりの風太郎』を連載中。
去年、私は金沢で寿司を食べた。
むろん若輩者であるし、それほど寿司を食べた経験があるわけでもない。だが、そのとき食べた寿司の味が今も忘れられない。間違いなく、私がこれまで経験した寿司のなかでいちばんおいしかった。
まず、店の雰囲気がよかった。
昼間に行ったからだろうが、客が誰もいなかった。白木のまばゆいカウンターに座り、多少は緊張を感じながら、主人の薦めるままに、先に刺身を少しいただき、あとで握ってもらった。大きな木のまな板に魚の切り身が置かれ、そこに細長い包丁が添えられる眺めが、とにかくうつくしかった。
私は大阪で生まれ育った。
食に関しては日本で最高の環境にあるという、街全体の強い思いこみと同化しながらすくすくと育った。
しかし、大学を卒業し、はじめて関西を離れ静岡の化学繊維工場に就職したとき、私は「おや?」と思った。魚が明らかにおいしい。独身寮の食堂で出てくる、何も凝った手を加えていない素朴な魚料理が明らかに大阪で食べてきたものよりおいしい。伊豆に近いその勤務先にて、私は決して海鮮物に関しては、大阪が一等ではないことを思い知ったのである。
静岡の次に私は東京に引っ越し、三年の無職の期間を挟んで作家になった。すると、半年に一度くらい、寿司をご馳走してもらう機会に恵まれるようになった。そこで私はまたしても知ってしまった。週末のたびに独身寮から車で三十分ほどの漁港の店に赴き、おいしいおいしいと食べていた、あの静岡の寿司が決して一等ではなかったことを。
大阪に住んでいた頃は、東京の食べ物はマズいものばかりだと聞いていたが、いざ住んでみると、マズいもの自体が東京にはほとんどなかった。なかでも寿司のおいしさは、たまにしか食べられないということもあろうが、相当に大したものだった。
そんな私が金沢を訪れた。
戦国末期の忍者を主人公にした小説を連載するための準備として、忍者寺という異名をとる妙立寺の見学がその主たる目的だった。続々と訪れる観光客が時間ごとに正確に区切られ、忍者屋敷のように奇矯な防御の仕掛けが施された本堂を、寺の案内の女性に率いられぐるりと一周した。そののちに、私は一軒の寿司屋ののれんを潜ったわけである。
金沢駅から少し離れたその寿司屋で小一時間を過ごし、私は金沢城の観光に向かった。二の丸を突っきり、大学生の頃に訪れたときにはなかった櫓に登り、鬱蒼と緑が生い茂る植物園のような本丸を巡る間、私はほとんど先ほど食した寿司のことばかり考えていた。
つくづくすばらしかったという賛辞の言葉ばかりがとめどなく湧き出るわけだが、では何がすばらしかったのか、と一歩進んで考えたとき、「寿司にストーリーがあったから」という理由が真っ先に思い浮かんだ。
そう、寿司に物語があったのだ。
「いやいや、最近めっきり僕、スランプでねえ、ネタが見つからんのですわ。なんぞ君、どっかにええネタ転がってへんかな?」
「何言うてんや君、ネタなら君の頭の上にのっとるがな」
「あ、そやった。僕、寿司やったわ」
という類の物語ではない。
ひとつひとつ出される寿司に、何であろう、意味があったのである。このひとつはまだ静けさを保ち、このひとつで一気に盛り上がって、このひとつでクライマックスを迎える、そしてこのひとつで穏やかな結末へと向かうわけです――。そんな具合に寿司がときに控えめに、ときに雄弁に語っていたように感じられたのである。
寡黙な主人がそっと出す寿司が奏でる物語に、客は静かに耳を澄ます。
また同じ店を訪れたとき、果たして私は同じ感興を得ることができるのだろうか。ふたたび金沢の地を踏む日が、楽しみであり、同時に少しこわくもある。