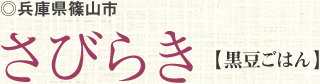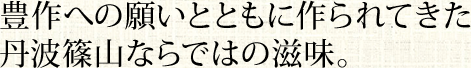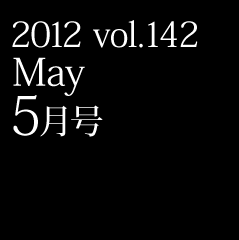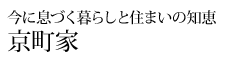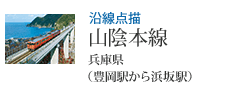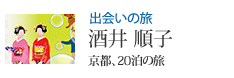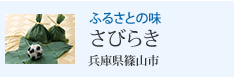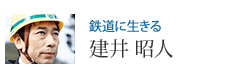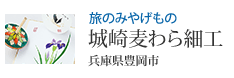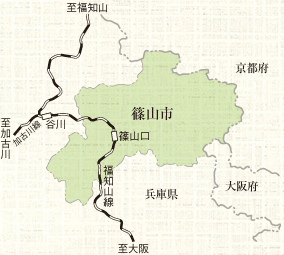
古くから、日本では春になると山から神が下りて田を守ると信じられてきた。そして、稲作作業の中でも田植えは特別なものとされ、田の神を迎えるさまざまな行事が行われてきた。盆地特有の自然環境によって、豊かな農産物を育んできた丹波篠山地方。この地に伝わる田植え初めの風習には、土地の恵みを活かした郷土の食文化が息づいている。

兵庫県東部に位置する篠山市は、四方を山々に囲まれるように、標高200メートルから300メートルの篠山盆地に開けている。市の中心部は城下町の風情ある町並みを残し、周辺部には山並みを背景にしたのどかな田園風景が広がる。盆地という地形の特性から昼夜の寒暖差が大きく、また夏は蒸し暑く冬は底冷えが厳しいという変化に富んだ気候は、丹波篠山ならではの多くの自然の恵みをもたらしてきた。
中でも、「丹波黒[たんばぐろ]」と呼ばれる品種の丹波篠山黒豆は、この地方の粘土質で肥沃な土壌や昼夜の激しい気温差が好条件となり、粒の大きさ、漆黒の艶、糖度の高さなど、最上級の品質を誇っている。栽培の歴史は古く、江戸時代には当時の藩主青山忠講[ただつぐ]が将軍徳川吉宗に献上して喜ばれ、栽培が奨励されたことなどから、篠山の黒豆は日本中に広く知られるようになった。
近年は、お正月の縁起物である煮豆のほか、青々とふくらんだ若サヤの状態で収穫した丹波篠山黒枝豆の人気も高い。地域を代表する特産品として、手間暇を惜しまずに栽培される一方で、昔から農家では田んぼの畦[あぜ]道を利用して自家用の黒豆を作っていたという。こうした畦豆や出荷されない豆などを使った料理は、地元の味として家庭の食卓に上ってきた。田植えどきのごちそうや子どものおやつでもあったという。篠山市地域活性化センター「黒豆の館」ではこうした地元食材を使った料理を食べることができる。

10月から11月頃の冷え込んだ朝、篠山盆地一帯は 深い霧の中に沈む。丹波霧とも呼ばれる朝霧の発生によって糖度を増し、良質の黒豆へと成熟する。

黒豆畑ののどかな田園風景が続く。
丹波篠山の味覚、黒豆を使った料理の一つに「黒豆ごはん」がある。一晩水に浸けておいた黒豆を、つけ汁といっしょに炊き込んだ素朴な味わい。黒豆の色素が溶け出しているため、ほんのりと紫がかった色合いも美しい。また、黒豆ごはんはもち米で炊いたようにもっちりとした食感に炊きあがる。
この黒豆ごはんを供した行事に「さびらき」がある。「さびらき」とは「早苗開き」または「早開き」と書き、田の神に苗の成長を祈願する行事である。田んぼや自宅で木の葉を敷いて供え物をする風習が全国各地に残る。篠山の農家ではこの行事名が、いつの頃からか供える黒豆ごはんそのものの名前ともなった。

炊きあがった黒豆ごはんを丸いおにぎりに。

十文字においた2枚の朴の葉の中心に黒豆ごはんをのせ、両方の葉で巾着のように包み、稲わらで結ぶ。
篠山市の食文化センター指導員の森下さんによると、さびらきの日には黒豆ごはんをおにぎりにし、温かいうちに朴の木の葉で包んだものを作っていたそうだ。それを家の神棚に供えるほか、田んぼの四隅や水の落とし口に栗の木の枝を立て、稲わらで吊るしてお供え物とした。田植えどきの朴の葉は大きく、緑が鮮やかで、香りも強くなる。朴の葉や栗の木が使われたのは、どちらもその芳香を虫が嫌うとされ、「虫が付かずに稲が成長する」という意味があるのだという。
昔ながらの風習は失われつつあるが、地元の小学校では食育の一環として郷土料理の学習が行われ、「さびらき」作りが取り上げられたこともあり、その名残は郷土色豊かな味わいとして今に伝わっている。