 |
 |
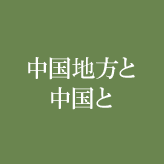 |
 |
岡山から山口までの範囲を、中国地方とよぶ。中国が近畿より西側の本州をさす地域名となっている。

とりわけ、広島ではこの名をよく耳にする。たとえば、新聞社であり放送局である。広島では、中国新聞がいちばんよく読まれる。テレビでも、地元のひとびとは、RCC中国放送をよく見ている。そういえば、中国銀行という名の銀行もあった。

これが、中国人には、なかなかわかりにくいことであるらしい。どうして、広島では中国新聞が読まれ、中国放送が見られるのか。なぜ、岡山から山口までのあいだが、中国地方とよばれるのか。それがいぶかしいという中国人留学生に、会ったこともある。

その留学生は、最初、広島あたりに中国人がおおぜいすんでいるせいだと、思ったらしい。それで、広島とその周辺は中国地方になったのだと、彼なりに考えたのである。

なかには、鳥取や島根が中国大陸にちかいせいだと見当をつけたむきも、あろうか。しかし、そうした思いつきは、みなまちがっている。くだんの留学生も、自分の考えがあやまっていたことにはすぐ気がついたと、言っていた。 |
|
 |
 |
だけど、なぜ岡山/山口が中国になるのかは、いまだにわからない。おしえてくれませんかと、その留学生からはたずねかけられたものである。

なるほど、たしかに中国人は、これを不可解に思うだろう。

じっさい、広島の中国新聞は、銀座五丁目に東京支社をおいている。そして、すぐちかくの銀座八丁目には、中国通信社の日本支社もある。現代中国の通信社と、中国を名乗る広島の新聞社が、同じ銀座にオフィスをおいている。中国人で、こういうことに、頭がこんがらがらされた者は、すくなくないだろう。

歴史好きには、しかし、あらためて説明するまでもあるまい。中国という名は、奈良時代につけられた。八世紀の奈良朝がもうけた行政区分に由来する。

大和の王朝人たちは、自分たちのいる場所を、畿内と称していた。畿という文字は都[みやこ]を意味している。畿内は、だから現代語になおすと、首都圏というほどの意味になる。そして、山背、摂津、河内、和泉、大和の五国を、彼らは五畿とよんでいた。

ほかの地域は、五畿=畿内との距離で、三つにわけられた。すなわち、近国[きんごく]、中国、遠国[おんごく]の三つである。今の中国地方という名称は、奈良朝がもうけたこの区分にまで、さかのぼれる。 |
|
 |
 |
といっても、奈良時代の中国と今の中国地方には、かなりのずれがある。

奈良時代には、石見、安芸、伊予、土佐以西が遠国とされた。近国は、因幡、美作、備前、淡路までである。とうぜん、中国はそのあいだにはさまれた諸国となる。すなわち、出雲、伯耆、備後、備中、讃岐、阿波である。

そう、かつての中国には四国の東半分もふくまれていた。鳥取、岡山の東側。そして島根、広島の西側は、そこからはぶかれていたのである。

いや、それだけではない。奈良時代の中国は、日本列島の東側にもあった。越前、越中、能登、飛騨、信濃、諏訪、甲斐、駿河、遠江、伊豆。以上十国も、かつては中国へくみこまれていた。それら十国が、東側の近国と遠国にはさまれた中国だと、そうみなされたからである。

王朝を中心にして同心円をいくつかえがき、日本の諸国を分類する。中国の地名は、そんな古い地理意識のたまものであった。そして、これを広島とその周辺だけが、今にいたるまでたもちつづけてきたのである。

旅行者、とくに中国人読者のみなさん、おわかりでしょうか。もう、広島で中国新聞や中国放送を見かけても、おどろかないで下さいね。 |
 |
 |
|
|
 |