 |
 |
京都府の南部、茶どころ宇治に
初夏の訪れを告げる八十八夜の茶摘歌。
黄檗山萬福寺[おうばくさんまんぷくじ]の
三門前にはその情景を
詠んだ田上菊舎[たがみきくしゃ]の
句碑が立つ。
一面に広がる茶畑で、
新芽を摘みとるのどかな光景。
菊舎の心をとらえた季節の風物詩を、
宇治茶の歴史とともにたどってみた。 |
 |
 |
菊舎は、加賀の千代女と並び称される江戸時代の女流俳人である。1753(宝暦3)年、長府藩士田上由永[よしなが]の長女として生まれ、16歳の時に嫁ぐものの24歳の若さで夫と死別。残る半生を俳諧の道に精進するため、28歳にして出家し、尼僧となって俳諧修行の旅に出たといわれている。松尾芭蕉の「奥の細道」を逆回りに巡るなど、当時では珍しい女性ひとりでの行脚を続ける中で、『手折菊[たおりぎく]』『首途[かどで]』など多くの作品を残している。

萬福寺の石碑に刻まれた句は、1790(寛政2)年3月から5月にいたる、吉野山探勝を中心とした宇治、大和紀行の俳諧記録『吉野行餞吟[よしのいきせんぎん]』に収められている。京を出て宇治へと足をのばした菊舎は、中国の高僧、隠元禅師によって開創された日本三禅宗の一つ、黄檗宗[おうばくしゅう]の大本山・萬福寺に立ち寄る。明朝様式を取り入れた伽藍配置や法具、読経など、すべてが異国情緒に包まれた山内と三門を挟んで広がる日本の茶畑の風景。その対比を鮮やかに詠いあげたこの句は、菊舎の代表作とされる。 |
 |
 |
| 「横まくり」と呼ばれる宇治流手もみ製法の工程。葉を手で転がしながら乾燥させていく。 |
 |
 |
| 萬福寺の三間三戸、重層の楼門造の三門。建立は1678(延宝6)年で、大雄宝殿や天王殿など他の伽藍とともに国の重要文化財に指定されている。 |
|
|
|
 |
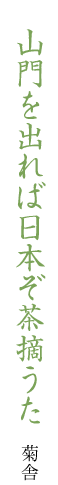 |
 |
 |
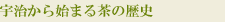 |
日本茶発祥の地ともいわれる宇治で、茶の栽培が始まったのは鎌倉時代。この地に茶の種をもたらしたのは、京都栂尾高山[とがのおこうざん]寺の明恵上人[みょうえしょうにん]と伝えられる。明恵上人は、師匠である栄西禅師が中国から持ち帰った種子を栂尾・深瀬にまくとともに、さらなる普及のために宇治の地を選び、その栽培方法を伝授した。馬に乗ったまま畑に入り、いく筋もの馬の蹄の跡をつけ、その足跡に種をまくように教えたという逸話も残る。明恵上人が乗り入れた茶畑は「駒蹄影園[こまのあしかげえん]」と呼ばれ、その跡地とされる萬福寺総門前に立つ記念碑が、宇治茶の起源を物語っている。

このように歴史的な生産地である宇治は、高級茶の産地としても名高く、緑茶の中でも最上級の碾茶[てんちゃ](抹茶)や玉露などがつくられている。栽培方法にも特徴があり、日光を受けて自然に栽培される「露天園[ろてんえん]」とは異なり、葉を摘む20日ほど前からよしずとわらなどで茶畑を覆い、日光にあてない方法がとられている。「覆下園[おおいしたえん]」と呼ばれるこの方法によって、旨味成分であるテアニンから苦味、渋味成分であるカテキンへの変化を抑え、まろやかなお茶となる。「新茶」とは、その年に萌え出た新芽からつくられるお茶のことで、一番茶ともいう。碾茶、玉露の高級茶には、この一番茶のみが使われる。茶づくり350年の歴史を誇る宇治・木幡の松北園では、萌芽から50日目となる5月初めから6月にかけてが茶摘みの期間。ハサミや機械による葉の摘み方が主流となった今も、昔ながらの手摘みで香味に富んだ宇治茶を生んでいる。 |
 |
 |
 |
 |
| 茶づくりは茶摘みに始まり、いくつかの工程を経て製品となる。宇治の茶摘歌はその工程ごとに歌われた自然発生的な作業歌で、大きくは「茶摘歌」「焙炉師節[ほいろしぶし]」「茶撰歌[ちゃよりうた]」の3種類に分かれる。地域や歌う人によって節は異なるが、“宇治はよいとこ 北西晴れて 東山風そよそよと”という歌詞はどの歌にも登場する。宇治市歴史資料館の坂本博司さんによると、葉を摘みとる時の茶摘歌は、実際にはその最中は作業に追われるため、昼ご飯の前や一日の終わりなど、作業の節目に歌われていたという。誰かが音頭をとって一斉に歌うものではなく、どこからともなく声が聞こえ、茶園全体に歌声が広がっていく。そんなのびやかな歌われ方であったとされる。明治の終わり頃までは歌い継がれていたが、機械化が進み、歌い手の歌う場面がなくなり、茶づくりの現場から歌声が消えて久しい。菊舎が訪れたのは、茶摘みの最盛期には早いものの、農家が準備で少し慌ただしくなった頃ではないかと考えられている。耳にした歌がどのようなものであったか定かではないが、見渡す限りの茶畑から感じる茶摘みの臨場感を、銘茶の産地にふさわしい秀句として残したのである。 |
 |
 |
|
|
 |