|
北前船の大海商といえば、加賀百万石の財政を支えた豪商・銭屋五兵衛[ぜにやごへい]を忘れるわけにはいかない。通称、銭五。銭屋は生家の屋号で、加賀藩の御用を務める材木商であった。39歳の時に、銭五は質流れの百石ほどの古い船を修理し海運業を始め、類い稀なる才覚と算用を発揮した。

銭五の本拠地は金沢市の北にある犀川河口の宮腰で、現在の金石[かないわ]。北前船の母港・宮腰には何軒もの廻船問屋があったが、銭五は抜きん出た存在だった。20年で全国に30数カ所の支店を持ち、大小200艘もの大船団を擁し、鎖国令下にも関わらず南太平洋の島々やアメリカ大陸にまで渡って交易したといわれる。海運業のほかに、材木、生糸、海産物、米問屋などを手がけ、加賀藩の金融経済を預かり、自らの財力で御用金を賄ったという。しかし、強大な財力を持つに至って、加賀藩の政争に巻き込まれ、最後には獄死する。「藩の権力と癒着した政商」という批判的な見解もあるが、海外交易の先駆者だと讚える評価もある。金石の屋敷跡には、北前船史上最大の豪商、銭五の波乱に満ちた生涯を伝える資料を展示した記念館があり、4分の1の縮尺の巨大な北前船の模型が目を引く。

日本海に面したこの金石一帯は古くは大野郷と呼ばれ、日本の五大醤油生産地の一つでもある。この大野の醤油も北前船に積み込まれた。最盛期には60軒の醤油醸造元があったが、現在でも28軒の醸造元が400年近い郷土の味を継承している。先祖は北前船の船主、あるいは海運業だったという醸造元も少なくない。大野醤油の特徴は、昆布出汁に合う少し甘くて上品な味で、食材の持ち味や色彩を身上とする加賀料理の風味を引き立てる要となる。金沢の人は大野醤油でないと口に合わないとまでいう。

金沢の冬の味覚といえば「かぶら寿し」。かぶらの間に鰤[ぶり]の切り身を挟んで麹粕でつけ込んだなれ寿しだが、高級な鰤を使うかぶら寿司は、そもそも藩政時代に金沢の魚屋が上顧客に贈答用としてつくったものだ。少し値段がはるのは今も同じで、家庭の食卓でどの家でも親しまれているのは「大根寿し」である。鰤の代わりに鰊[にしん]を使う。つくり方はかぶら寿しと同じように、塩漬けした一口大の大根に麹をまぶし、乾燥した身欠き鰊を敷きつめて10日間ほど熟成させる。すると鰊の旨味が大根に程良く馴染む。パリパリと食感がよく、さっぱりした味だ。晩秋から冬にかけて、金沢の家庭では大根寿しを漬けるのが習わしで、市場にはずらりと鰊が並ぶ。大根寿しは、金沢のおふくろの味なのだ。

糠で塩漬けした「こんかいわし」や河豚[ふぐ]や河豚の卵巣、鯖[さば]などを糠で漬け込んだものも名産だが、もともとはこれらも北前船によって運ばれた鰊を糠につけて保存食にしたのがはじまりという。蝦夷でとれた食材が北前船によって持ち込まれ、今ではすっかり郷土の味となり、昆布も鰊も北陸地方の食文化を語る上で欠くことのできない食材となっている。

金沢から日本海沿いに南に下ると、ここにも北前船の里がある。現在は加賀市だが江戸時代の頃は大聖寺[だいしょうじ]藩に属した瀬越[せごえ]と橋立[はしだて]である。大正時代の雑誌に「日本一の富豪村」と紹介されたこともあり、沖合には隆盛を象徴するように何艘も北前船が錨を下ろし、荷積みや荷下ろしで活気にみなぎっていた。山中温泉にこんな唄が残っている。「山が赤うなる木の葉が落ちる。やがて船頭衆がござるやら…」。航海を終えた橋立の船乗りは大金を懐に山中の湯に浸かり、「板子一枚下は地獄」の緊張を解きほぐし、しばしの休息を贅沢三昧に過ごしたのだろう。

北前船の繁栄と活気も、明治末には交通手段の近代化とともに急速に衰退していった。今はひっそりと佇む豪商の屋敷に栄華を偲ぶばかりだが、北前船が運んだ食文化は脈々と今に引き継がれ、しっかりと根づいている。 |
|
 |
|

金沢の家庭の味は「大根寿し」。地元で採れる大根と北海道の身欠き鰊を麹で馴染ませた大根寿しは、冬場になると金沢のどこの家庭でもつくられ“おふくろの味”。これがないと正月はこないといわれる。
〈撮影協力/かぶら寿し本舗かばた(金沢市)〉 |
|

北前船の里資料館(加賀市)。北前船の大船主だった酒谷[さかや]家の屋敷。外観も内部も建てられた明治初期のままで、橋立の北前船の歴史や船乗りたちが使用した道具などを展示する。 |
|

資料館には、船主や船乗り、家族が航海の無事と安全を祈願して神社に奉納した船絵馬が数多く残っている。写真は資料館近くにある出水神社に奉納された船絵馬。 |
|
|
|
|
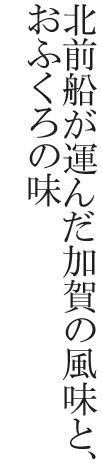 |
|
 |
|

北前船史上最大の海商といわれた銭屋五兵衛は、海運業のほかにも多彩な事業を行い巨万の財力を天下に誇った。加賀藩の金融経済の要職を務め、加賀百万石の財政を建て直した。が、その最期は冤罪に問われ80歳で獄死する。写真下は銭五の屋敷のあった金石にある「石川県銭屋五兵衛記念館」に置かれた4分1サイズの常豊丸の模型。 |
|

大野川に面したヤマト醤油味噌の工場。この辺りは加賀藩主が船遊びをした場所でもあり、市街地の近くにも関わらず町並みは藩政時代の風情が今も漂っている。 |
|

大野町のヤマト醤油味噌が醸造する「北前船」。北前船時代の伝統製法でつくられた昆布出汁によく合う醤油で、色は薄く、味は少し甘め。繊細で上品な風味だ。素材の味を際立たせる加賀料理に欠かせない。 |
|
|