|
白帆に風をはらんで穏やかな海を航海する船団、暴風と荒波に翻弄される帆船 … 鮮やかな彩色で描かれた絵馬の数々が北陸地方の日本海沿いの神社に残っている。北前船の航海の安全と無事を祈願して奉納された船絵馬だ。

北前船は江戸中期から明治30年代まで、蝦夷(北海道)と大坂の間を、日本海沿岸の諸港に寄港しながら、下関、瀬戸内海を通って往来した廻船である。上方や瀬戸内では「北前」とは「日本海側」を意味し、北の日本海から来る船を「北前の船」と呼んだことに由来する。日本海沿岸では北前船とは呼ばず「千石船」「弁才船[べざい]」、また越中地方では一度の航海で倍の儲けを得られることから「バイ船」と呼んだ。船の大きさは通常500石から1,500石で、なかには2,000石近い大型船を持ち大小200艘もの船団を擁する大船主もいた(千石船は積載量150t)。

北前航路、西廻り航路といわれる日本海ルートを最初に試した人物は加賀藩三代藩主、前田利常。経済の中心、大消費地でもあった大坂には各藩の蔵屋敷があった。加賀藩は蔵米を大坂に運ぶために、それまでは敦賀で船荷を陸揚げし、陸路と琵琶湖の水運を経て大津、京都、大坂へと運んでいた。これが日本海側からの物資輸送の通常ルートだったが、荷の積み降ろしや陸路を搬送するのは手間がかかり効率も悪い。そこで利常は、米100石を下関、瀬戸内海を経由して大坂に廻送し、このルートの有利さを証明した。その後、1672(寛文12)年に幕府の命を受けた河村瑞賢[ずいけん]によって蝦夷と大坂を結ぶ西廻りの北前航路が拓かれたと歴史書には記されている。

だが、それよりも以前、近世初頭に蝦夷地と内地との交易を行っていた人々がいる。近江商人だ。全国各地に進出していた近江商人は、蝦夷で仕入れた金や皮革、海産物などを内地へ廻送し多くの利益を得ていたが、この時、彼らに雇われて船を操っていたのが越前や加賀、能登、越中の船乗りだった。この船乗りたちで力をつけた者がやがて自前の船を持ち、自力で蝦夷との交易を行い、大船主に成長していった。船主たちが巨万の富と財を築くのは、北前航路が本格化する江戸時代中期になってからである。

北前航路が確立されてからの船の寄港地は、日本海沿岸だけで大小100港以上もあったが、その母港の多くは北陸地方の諸港だ。なかには、加賀の橋立の船主のように、船を繋留する母港を大坂の港としていたところもある。船乗りたちは、春の彼岸頃に橋立を発ち、大坂へ陸路で赴く。大坂から蝦夷へと出航し、秋の彼岸頃に大坂へ帰港、再び徒歩で橋立へと戻るのだ。

一般的には船主が住む港が母港であり、そこから大坂へと出帆する。大坂で生活・日用雑貨品を積み込み、蝦夷へ向かう途中の瀬戸内や日本海沿岸の寄港地でさまざまな物資を売買しながら航行する。これを「買積[かいづ]み制」といい、北前船は、船主が荷主でもあり各港で商売をしながら運送する。航海は通常、大坂と蝦夷とを春から秋にかけて一年に一往復していた。

海の大動脈として物流を支えた北前航路。北前船はいわば“海を往く総合商社”であった。本州からは、米や塩、砂糖、酒、酢、鉄、綿、薬、反物や衣類などあらゆる生活物資を積み込み、売買しながら日本海を蝦夷地に向けて北上した。これを「下り荷」という。逆に、蝦夷地から上方へと向かう荷を「上り荷」といい、主に昆布や鰊、鰊粕[にしんかす]、干鰯[ほしか]、鮭、鱈などの海産物を運んだ。一回の航海の利益は現在の額で約1億円にもなった。しかし、北前船は船主に巨富をもたらしただけではない。鰊粕や干鰯などの魚肥は、上方の綿花栽培を支え、麻に替えて肌触りのよい木綿の衣類を普及させたほか、各地の生活文化にさまざまなな影響を及ぼした。

そして、北前船が蝦夷から運んだ「昆布」は日本の食文化を一変させた。とりわけ北前船の故郷、北陸地方では昆布は郷土の食文化と深く関わっている。 |
|
 |
|
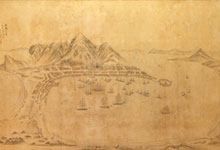 |
|
幕末もしくは明治初頭の頃の函館湾の様子を描いたものと思われる。
数多くの北前船に交じり、アメリカ、フランス、イングランドなどの国旗を掲げた西洋の大型帆船の姿が描かれている。
(北前船の里資料館) |
|
 |
|
オランダから輸入したものを真似て作った遠眼鏡(とおめがね)。漆塗りの上に金文様を描くなど、美麗な仕上がりとなっている。船頭や問屋の主人が使用した。
(北前船の里資料館) |
|
 |
|
| ■北前船の航路と主要な寄港地 |
|
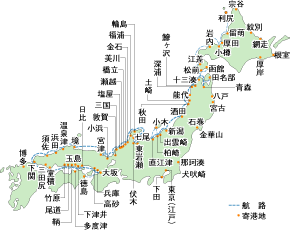 |
|
|
|
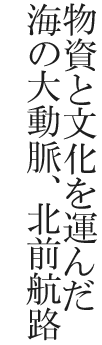 |
|
 |
|

加賀・橋立の船主・酒谷長平の持ち船『幸貴丸』。およそ1,300石積の大きさで、船上には船頭以下16名の乗員の姿が見える。明治期撮影。
(北前船の里資料館蔵) |
|

最後の北前船といわれる「神通丸」の模型。富山市東岩瀬の元船主・米田氏が、船頭らの記憶に基づいて船大工らに造らせたもの。
(米田寿吉氏寄贈/富山県蔵) |
|

船の航行用に十二支の方位をつけた和磁石。北前船は必ず2つ以上の磁石を持ち込んで航海した。
(北前船の里資料館) |
|