|
天王寺駅から15分足らずで、四天王寺の南大門にたどり着く。そこへ至る参道には、線香屋に仏壇店、経木店、四天王寺名物・釣鐘まんじゅうの看板もある。ここには「四天王寺さん」の雰囲気が滲み通ったような風景が展開する。

中門をくぐると五重塔、そして金堂、講堂が一直線で並んでいる。1945(昭和20)年3月の大阪大空襲で伽藍は焼失し、1963(昭和38)年に再興された。伽藍のひとつ、五重塔に上ってみた。高さ39.2m。ビルの7〜8階分ほどの高さがあるうえ、階段が狭くて急勾配なので、すぐに息が切れた。

毎月21日の「お大師さん」では、ことのほか賑わう亀井堂の経木流し。石造りの亀を型どった水盤があり、亀の口から流れ出る清水で経木を洗ってもらう。水盤に長い手杓をいれ、器用に経木を選り分けている。伽藍の北にある六時堂前の亀の池では、亀の甲羅干しに付き合ってひと息いれる。

四天王寺の名称のもとになった四天王は、東方の持国天、南の増長天、西の広目天、北の多門天を指す。蘇我馬子と物部守屋が争った際、聖徳太子が四天王の像を彫ったところ戦いに勝利し、このお礼に太子が四天王寺を建立したと伝えられる。天王寺の地名もこの四天王寺に由来する。

「海の向こうには極楽浄土がある」。西門石鳥居越しに沈む夕陽は、古来、四天王寺信仰のシンボルとしてあがめられてきた。平安期に金堂で発見された「四天王寺縁起」には「五重塔と金堂は極楽の東門に当たる」とあり、西門から極楽浄土へ渡れるという大衆の信仰が、四天王寺詣につながっていった。

四天王寺を中核に見立てると、北へ向かって生國魂神社、高津宮、難波宮、大阪城がひとつの線上に並ぶ。南は茶臼山、帝塚山の古墳群から住吉大社、仁徳陵につながる約12kmの南北ラインは、上町台地を貫いている。この台地一帯は5000年前、大阪湾に突き出す半島状の地形だった。いまは、四天王寺西側の谷町筋から松屋町筋にかけての傾斜地が、「天王寺七坂」とよばれる坂の街に姿を変えている。

一番南端の坂である逢坂(国道25号)から北へ四つ目の愛染坂に向かう。593(推古天皇1)年、四天王寺建立のおり、聖徳太子は四箇院[しかんいん](敬田院、悲田院、施薬院、療病院)の社会教育・福祉事業の思想を広め、薬草を植え、病気に備える施薬院を現在の愛染堂がある場所に建立したと伝わる。坂の途中にある勝鬘院[しょうまんいん]の愛染堂は、若い女性に人気である。6月30日から7月2日の愛染まつりには、大阪の娘さんがその年になって初めて浴衣を着て、愛染様にお披露目に行く日だという習わしが、愛染の語感もあって女性の心をくすぐるのだろう。大阪市内で最古の建造物「多宝塔」よりは、縁結びの霊木「愛染かつらの木」に足が向くのは自然かもしれない。

愛染堂の北側に鎌倉時代の歌人藤原家隆(1158〜1237年)の塚がある。役人を辞めた家隆は晩年この地に住んだ。「夕陽庵」と名づけて、西の海に沈む夕陽に感動し、唄を詠んだ。これが夕陽丘という地名の由来ともなった。
|
|
| 「契りあれば なにわの里に宿り来て |
| 波の入日を 拝みつるかな」 |
|
 |
|
 |
|
|
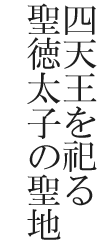 |
|

四天王寺・亀井堂の経木流し。石造りの亀の口から流れる清水は、金堂の地底にある青龍池から湧きでていると言い伝えられる。青龍池は極楽に通じているとされ、経木を流すことで先祖や故人の極楽往生を願う。 |
|

勝鬘院の多宝塔。1594(文禄3)年に豊臣秀吉が建立したと伝えられる。国の重要文化財。 |
|
 |
|

勝鬘院[しょうまんいん]愛染堂の本尊、愛染明王。怒りに満ちた怖い形相だが、その心は慈悲と敬愛に満ち、愛欲という煩悩を菩提(悟り・成就)に変える力を持つ。 |
|

愛染坂。下り口に勝鬘院、通称「愛染さん」があるところからこの名が付けられた。 |
|

上町台地の高台にある「家隆塚[かりゅうづか]」。藤原家隆がここに庵を結び暮らしたころは、海岸線がすぐ下まで迫り西海に沈む夕日を間近に見たことだろう。 |
|