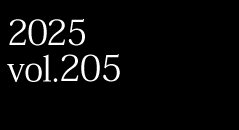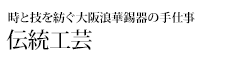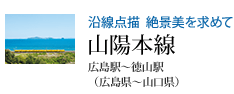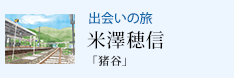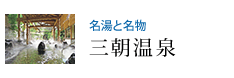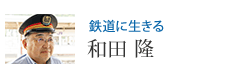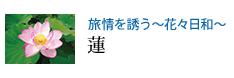作家。1978年岐阜県生まれ。2011年『折れた竜骨』で第64回日本推理作家協会賞、2014年『満願』で第27回山本周五郎賞、2021年『黒牢城』で第12回山田風太郎賞、翌2022年同作で第166回直木三十五賞を受賞。
猪谷という駅がある。
深い谷に臨む、小さな集落の端に置かれた駅だ。駅舎の近くには関所の跡地があり、ここが昔から境界の地であったことを物語る。猪谷は飛越、すなわち飛騨国と越中国の境に当たっている。
そして猪谷は、現代においても境界である。一本の線路の、この駅より北はJR西日本の、南はJR東海の営業エリアだ。加えて、以前この駅には、鉱山街から延びる神岡鉄道も乗り入れていた。いまや降りる者の姿も稀な無人駅だが、幾本もの鉄路をまたぐ構内踏切や、かつては多くの物資を集積していたのだろう空閑地などに、ここが輸送と交通の要衝であった往時がしのばれる。
宮脇俊三氏はかつて、国鉄完乗の旅の中で訪れた猪谷駅で、神岡へ折り返す列車と富山へ向かう列車を誤って駅のホームに取り残された(『時刻表2万キロ』)。鉄道旅行の名人たる氏が乗り誤ったのは意外だが、境界という猪谷駅の性格に照らせば、そういうこともあろうかと思われなくもない。
境界は一般に不安定であり、とかく誤りが生じやすい。「いま」が「さっき」の続きではない時には、よからぬことが忍び寄ってくるものだ。形而下的に書くなら、境界は人目につきにくいため管理が行き届きにくく、利害が錯綜するためルールを一般化しにくく、管轄がはっきりしないため責任の所在が曖昧になる。旅人を惑わしたのも、境界ゆえの複雑な車両運用だった。
この不安定さゆえ、境界には古来から魔除けが置かれてきた。関東から中部には道祖神が多く祀られ、近畿では山の神、九州では猿田彦大神の祠がよく見られるという。これらの魔除けは境界に安定をもたらすものというより、不安定さが境界を超えて内側に押し寄せないよう阻害するという意味合いが大きかった。
しかし今日、人の流動性はかつてと比較しようもない。数多の人間が境界を超えて内側に入り込み、外側に出ていく。いま私は、出ていくことについて考える。
境界を踏み越えて内から外に出れば、あらゆるものが変わる。ゴミ出しのルールが変わる、学区も選挙区も変わる、スーパーの品ぞろえが変わる、言葉も少しずつ変わっていく。助けてくれる隣人も親族も、はるかに遠くなる。境界を超えた者は、決して全てではないにせよ、多くのことを一から始めなくてはならない。境界を超えて外に行くということは、昨日までの自分が積み上げてきたいのちを、生を少し捨てることだ。修辞的に言えば、それは小さく死ぬことでもある。
用あって飛騨に戻る時、私は以前羽田空港から富山空港へ飛び、そこから車を使っていたが、北陸新幹線が富山まで通じてからはそちらを使っている。北陸新幹線とはまことに、一つの奇蹟だ。東京駅で「かがやき」に乗り込めば、弁当を使ううちに関東平野の北端に達し、ふとまどろむ間に日本海が見えてくる。
富山から非電化区間の気動車に乗り込めば、すべての列車は猪谷に停車し、ここでJR西日本とJR東海の乗務員が交代する。境界の不安定さが万が一にも入り込まぬよう、交代に際してどれほど慎重を期すか察するに余りある。猪谷に停車する車内で、私はまた、ふと考える。境界を超えて出ることが少し死ぬことであるとするなら、ふたたび境界を超えて戻ることは何を意味するか。
列車が動き出し、山深くへと入り込む。猪谷から先は見知った土地だ。葉の青さ、陽の近さ、険山激水みな見覚えがある。
境界の先から戻る者は、少し生き返る。
参考文献 八木康幸『村境の象徴論的意味』