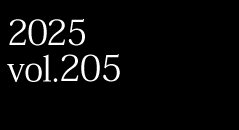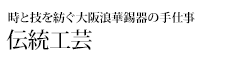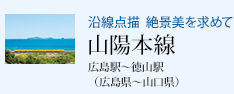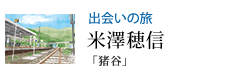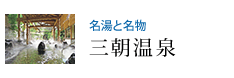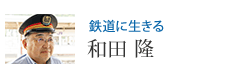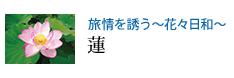![]()
多島美の瀬戸内海を背景に走る山陽本線の列車。(由宇駅〜神代〈こうじろ〉駅)
山陽本線は神戸駅から北九州市の門司駅を結ぶ長大路線。沿線には、瀬戸内海の名所や旧跡、絶景美が点在する。今回の旅は、広島駅から徳山駅までの88.5km。列車は瀬戸内の多島美を車窓に、周防灘沿いの町をめざした。


![]()
2025年3月にグランドオープンした広島駅南口の新駅ビル「ミナモア」。2階の中央アトリウム空間には、路面電車が乗り入れる予定だ。
今回の旅の起点は広島駅。芸備[げいび]線や呉線、可部[かべ]線、そして新幹線が乗り入れる一大ターミナルだ。そんな広島駅に今年3月、新しい駅ビルが開業した。駅南口の高さ約100m、地上20階建ての大型ショッピングセンター「ミナモア」だ。映画館やホテルなども併設し、駅ビルの2階には路面電車の停留所が設置され、新たな賑わいの場として話題を集めている。
瀬戸内最大の玄関口の駅を離れた列車は進路を西に京橋川を渡り、やがて廿日市[はつかいち]駅を過ぎると進路を南に変え、広島湾に沿って走る。
広島駅から約30分で宮島口駅に到着。宮島口旅客ターミナルからフェリーに乗り換え“神が宿る島”といわれる宮島を参拝した。船上からは養殖の盛んな広島の牡蠣筏[かきいかだ]を望み、航路の先には海上に立つ巨大な鳥居が徐々に近づいてくる。神が鎮座する嚴島[いつくしま]神社だ。回廊型の社殿は荘厳で、皇室の安泰や国家鎮護、海上の守護神として古くから崇信された。後白河法皇や高倉上皇など、多くの皇族や貴族が参詣したことから都の文化が宮島にもたらされたという。
宮島をあとに、宮島口駅から再び乗車する。列車はさらに南に向かい、玖波[くば]駅に到着。駅前からバスで南側に下れば、安芸灘の大野瀬戸[おおのせと]に臨む風光明媚な場所に2023年に開館した下瀬[しもせ]美術館が立つ。宮島と瀬戸内の多島美を背景に、水盤にたたずむカラフルな可動展示室は世界でも類をみない建築で、2024年には「世界で最も美しい美術館」として評価された。収蔵作品は、マティスやシャガールなどの絵画のほか、アール・ヌーヴォーのガラス工芸など多岐にわたり、県の新たな美術鑑賞の名所となっている。
列車は和木駅から山口県に入り、間もなく岩国駅に到着する。

広島駅新駅ビル直上に誕生した「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」は、瀬戸内の観光地をつなぐ新たな旅の拠点となっている。

![]()
宮島フェリーから望む大野瀬戸に浮かぶ牡蠣筏。広島県は牡蠣の養殖が盛んで、生産量は全国1位を誇る。

「アートの中でアートを観る。」がコンセプトの下瀬美術館。エントランス棟の外観は周囲の景色を映し出す。エントランス内は、柱と梁が一体となった構造が屋根を支える。



海に立つ嚴島神社と江戸情緒漂う表参道商店街を歩く

![]()
創建は593(推古天皇元)年と伝わる嚴島神社。島全体が神として崇められていたことから、陸地では畏れ多いという理由で、潮の満ち引きするところに社が建てられたという。
広島湾に浮かぶ宮島に鎮座する嚴島神社は、信仰篤い平清盛によって1168(仁安3)年に現在の規模に造営された。日本三景の一つに数えられる「安芸の宮島」には、江戸時代の宿場の佇まいが今も残り、伝統的な町家以外にもモダンなカフェや雑貨店などが立ち並ぶ。「清盛通り」とも呼ばれる表参道商店街には宮島名物の杓子[しゃくし]専門店をはじめ、70店舗以上の商店が軒を連ねている。



表参道商店街で宮島しゃもじ専門店を営む「杓子の家」。店主の宮郷厚樹さんは、「宮島では“しゃもじ”を“しゃくし”と呼びますが、実は正式名称です。“しゃもじ”は宮中に仕える女官が使った言葉です。一般的にはそちらの方が残りました」と話す。


![]()
大野瀬戸を挟んで宮島を望む下瀬美術館。水盤の上に並ぶ8つのカラフルな可動展示室は造船技術を活用し、水の浮力で動かせる仕組みになっている。


岩国のシンボル 錦帯橋と郷土料理 岩国寿司

![]()
ライトアップされた錦帯橋。木造五連のアーチ橋は期間限定でライトアップされ、季節や曜日によって色とりどりの色彩に変わる。


平清の7代目店主の神尾紀一郎さんは岩国寿司について、「具材は特に決まりがなく、瀬戸内の魚や岩国れんこんなど地元のもので、身近な食材であればいい」そうだ。
錦帯橋は岩国市のシンボルだ。“暴れ川”で知られる錦川の氾濫で何度も流失したが、木造にこだわり何度も再建された。2001年〜2004年には「平成の架替事業」が実施され、その佇まいは、現在も多くの人々を魅了している。
そんな錦帯橋のたもとで郷土料理を提供するのは、創業1858(安政5)年の平清[ひらせい]だ。「岩国寿司」をはじめ、岩国の特産物を用いた料理を中心に提供している。岩国寿司とは岩国領主に献上し、喜ばれたという伝承から「殿様寿司」とも呼ばれる押し寿司。今は冠婚葬祭などで提供されているそうだ。


![]()
周防大島の飯の山展望台から望む柳井市側の眺望。日本三大潮流の大畠瀬戸や大島大橋が一望できる。
山口県東端部に位置する岩国市は、岩国の歴代領主吉川家によって築かれた城下町だ。居城を構えた標高約200mの城山山頂からは錦川を天然の外堀に、岩国の町並みが眼下に広がる。錦川の両岸は、かつての重臣たちが生活した地区と家臣や町人の居住区に住み分けられた。その二つの地区をつなぐのが、錦帯橋[きんたいきょう]だ。現在も多くの人々に利用される木造のアーチ橋の曲線は美しく、その佇まいはまさに絶景美だ。橋の下からのぞく橋梁の木組みは緻密で、匠の技術が入念に施されている。
岩国駅を離れた列車はいくつかの川を渡り、さらに南下する。藤生[ふじゅう]駅を過ぎると、徐々に瀬戸内の海が列車の車窓を彩り始める。由宇[ゆう]駅からは海の風景が連続し、陽光が射し込んだ海面はキラキラと輝いている。横たわる周防大島[すおうおおしま]を背景に、客船や貨物船が引き波を立てながら行き交い、その航跡も瀬戸内海の風景として溶け込んでいる。大島大橋が迫ると大畠[おおばたけ]駅で、この周辺は特に潮の流れの激しい難所で知られる。『万葉集』に詠まれた「大畠瀬戸[おおばたけせと]の渦潮」は、日本三大潮流の一つに数えられている。列車は進路を西に変え、柳井港[やないみなと]駅を過ぎて少し内陸に入ると間もなく柳井駅だ。
柳井は古くは舟運を利用した海上交通の要衝で、江戸時代には「岩国のお納戸」と呼ばれた。駅から北にほどなく行くと、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定される一角がある。商業都市として賑わった、かつての佇まいを今に残した「古市[ふるいち]・金屋[かなや]地区」だ。本町通りには本瓦葺[ほんがわらふき]、格子窓の白壁町家が整然と並び、時代劇のセットのような町並みが続いている。軒先を飾るのは「柳井金魚ちょうちん」で、ゆらゆらと風に揺れる様子は涼やかだ。柳井を代表するこの民芸品は夏の風物詩で、夜になると通りは一面の柳井金魚ちょうちんの明かりで彩られる。

![]()
白砂青松の海岸が約2.4kmにわたって続く虹ケ浜海岸。西日本屈指の海水浴場で、「日本の渚百選」や「快水浴場百選」に選ばれている。


中世の町割が残る白壁の町並み「古市・金屋地区」

![]()
古市・金屋地区の白壁の町並み
山口県南東部に位置する柳井市は、かつて柳井津として瀬戸内海の舟運を利用した市場町だった。中世の町割がそのまま残る「古市・金屋地区」には、白壁の美しい江戸時代の商家が約200mの通りに面して立つ。
柳井の郷土民芸品「柳井金魚ちょうちん」は、青森県弘前のねぷたを参考に、柳井の伝統的綿織物「柳井縞[やないじま]」の染料や竹ひご、和紙などを応用して考案された。夏場になると軒先の柳井金魚ちょうちんに明かりが灯り、毎年8月13日には町を挙げて「柳井金魚ちょうちん祭り」が盛大に催される。

お盆の行事「柳井金魚ちょうちん祭り」。会場では約2,500個に明かりが灯る。

江戸時代から伝わる「柳井金魚ちょうちん」。割り竹で組んだ骨組みに和紙を貼り、赤と黒の染料で色付けして製作されている。

1830(天保元)年から同じ製法で作られる柳井の甘露醤油。一度でき上がった醤油に、再び麹を加え、再仕込みする独特な製法で作られる。仕込みから完成まで2〜3年かかる。

列車は進路を西に、白砂青松で知られる虹ケ浜海岸最寄りの光[ひかり]駅から、櫛ケ浜[くしがはま]駅を過ぎて、煙突群が見えると目的の徳山駅だ。瀬戸内海沿いに林立する周南[しゅうなん]コンビナートのプラント群の風景は日中でも壮観だが、夜景の“多灯美”は圧巻だ。幻想的な景観は観賞ツアーが組まれるほど人気で、多数のビュースポットが点在する。
見どころ豊かな山陽本線は、瀬戸内海の絶景美や史跡を満喫する旅であった。

![]()
徳山駅周辺の周南コンビナートの夜景。周南市内には撮影スポットが点在し、工場群の多灯美の夜景を満喫できる。