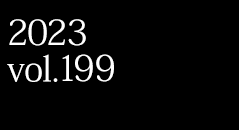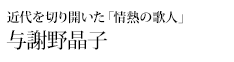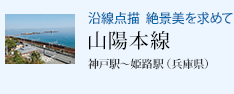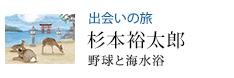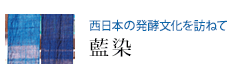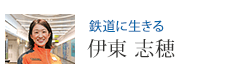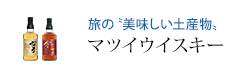![]()
須磨浦の海岸沿いを走る列車。(須磨駅〜塩屋駅)
山陽本線は、兵庫県の神戸駅から福岡県北九州市の門司駅を結ぶ534.4kmの大動脈だ。この旅では、都市の賑わいや瀬戸内ならではの穏やかさなど、表情豊かなベイサイドを臨みながら、神戸駅から姫路駅へと向かう。


1874(明治7)年の大阪〜神戸駅間の鉄道開業より、歴史が始まる神戸駅。現在も、1930(昭和5)年建造の端正な駅舎が残る。「0キロポスト」は、駅構内5番線の線路側の壁にある。
兵庫県の神戸駅から北九州市の門司駅を結ぶ山陽本線。神戸駅は東海道本線の終点と山陽本線の起点となる境界駅で、構内には『東京起点589K340M、神戸起点0K0M』と表記された「0キロポスト」と呼ばれる距離標がある。大阪駅から姫路駅までの区間は「JR神戸線」の愛称で親しまれている。
神戸駅の東側は、アミューズメント施設が充実し、港町神戸らしく洗練された風景の中に、異国情緒漂う街が共存するベイエリアだ。神戸ハーバーランドumieや、明治時代の倉庫を再利用した商業施設の神戸煉瓦倉庫に代表される観光スポットが点在する。
列車は「第1回近畿の駅百選」に選ばれた新長田駅へ。駅南側の公園には、神戸出身の漫画家、横山光輝氏の人気作品『鉄人28号』の巨大モニュメントが設置されている。高さ約15mの鉄人28号は圧巻。震災復興と地域活性化のシンボルとして、地元の商店街が中心となって製作を実現させた。このモニュメントは列車の中からもチラリと見ることができる。
列車は徐々に海に近づいて走る。須磨海浜公園駅から須磨駅あたりまでは、「日本の渚百選」に選ばれた須磨海岸が続く。キラキラと陽光に輝く大阪湾の穏やかな水面が車窓を満たしていく。JR神戸線ならではの絶景区間だ。
さらに海と山がひときわ近い塩屋駅界隈は、明治期に始まった洋風な街の雰囲気も相まって、近年では若者にも注目されている。背後に見えるジェームス山は、この地に外国人向け住宅地を開発したイギリス人、アーネスト・W・ジェームスに由来する。ジェームスは、緑を残し、ありのままの地形を活かすイギリス式の区画整備を基本に1930年代に開発した。海に向かってなだらかに続く丘陵地には、1908(明治41)年に建てられたコロニアル・スタイルの洋館、旧グッゲンハイム邸も佇んでいる。

![]()
新長田駅近くの公園にある鉄人28号モニュメント。鉄骨構造で、設計に1年、製作に1年を有し2009年に完成した。

![]()
須磨浦公園から登る標高252mの旗振山(はたふりやま)からは、明石海峡大橋と淡路島が一望できる。

旧グッゲンハイム邸。近年の調査で、実際に暮らしたのはこの北隣と判明したが、長く親しまれている名称が引き続き使用されている。


幻想的な光の世界に酔いしれる、神戸ハーバーランドの夜

![]()
昼とは異なる表情をみせる、神戸ハーバーランドの夜。街全体に輝くイルミネーションが神戸湾に反射する絶景スポット。

神戸ハーバーランドから港湾緑地、メリケンパークを遠望。神戸ポートタワーは、2024年春再開に向けリニューアル工事中。

明治時代の赤煉瓦倉庫に、レストランや家具店などが軒を連ねる神戸煉瓦倉庫。
神戸ハーバーランドは、ショッピングやグルメ、映画館など大型複合施設が充実した神戸有数のショッピング&観光エリア。潮風を感じる遊歩道には、散歩やジョギングを楽しむ人もいて、地元にも親しまれているスポット。夕刻からオレンジ色に染まり、夜になるとイルミネーションで輝き、ビュースポットとしても人気だ。ライトアップされた街並みはクルーズ船が停泊する神戸港の水面に反射し、どこを歩いても幻想的。


明石海峡大橋を間近に見ながら舞子駅に向かう列車。(垂水駅〜舞子駅)
撮影協力:シーサイドホテル舞子ビラ神戸
列車が舞子駅に近づくと、両手を堂々と広げたような大きな吊り橋が眼前に迫ってくる。本州と淡路島をつなぐ吊り橋、明石海峡大橋だ。橋の袂に広がる舞子公園一体は、古くは白砂青松の舞子浜として親しまれ、安藤広重は『播磨舞子の濱』の美しい海岸風景を描き、志賀直哉も著書『暗夜行路』に「塩屋、舞子の海岸は美しかった」と残している。
吊り橋を支えるアンカレッジと呼ばれる巨大なコンクリートの塊の中にあるのは「舞子海上プロムナード」だ。明石海峡へ突出した海面からの高さ約47mの回遊式遊歩道があり、周りは大きな橋桁に囲まれ、一部がガラス張りの足元からは、明石海峡の潮の流れが渦巻く。そのスケールの大きさに目がくらみそうだ。


舞子公園から、明石海峡と大橋を臨む

![]()
美しい佇まいから「パールブリッジ」の別名を持つ明石海峡大橋は、夕刻からひときわ幻想的な表情に。夜間のライトアップも時期によってパターンが変わる。

明石海峡大橋の回遊式遊歩道「舞子海上プロムナード」。

ガラス張りの床面になった丸太橋がスリル満点。
橋長3,911mを有する明石海峡大橋。この下は1日1,400隻以上の船舶が行き交う海上交通の大動脈。古くから好漁場でもある明石海峡の環境をなるべく損なわないように、厳しい条件の中で建設された。海峡を借景とする舞子公園は、県立都市公園として1900(明治33)年に開園。松林と芝生の中に神戸の中国人実業家の別荘だった「移情閣」などの歴史的な建物が現存。夕暮れ時にここから見る、オレンジ色の海峡とシルエットになった橋のコントラストは絶景。

松林と芝生が広がる舞子公園。


![]()
三方を岩盤に囲まれた「浮石」を御神体とする石の宝殿、生石神社。かのシーボルトも江戸へ上る道中、高砂に訪れ、石の宝殿の詳細なスケッチを残している。

1700年間、採石が続く竜山石は、日本で有数の歴史を持つ。「地元の人にこそ、その誇りを伝えたい」と松下さんは語る。


![]()
姫路駅から見る姫路城。平成の大修理では、築城時の美しい姿を引き継ぐために伝統工法が用いられた。日本初の世界文化遺産登録から2023(令和5)年12月で30年を迎える。


![]()
書寫山圓教寺の境内で、岩山の中腹にある舞台造の「摩尼殿」。蓮の花をかたどった御朱印など、御朱印の種類が豊富。
列車は明石駅、山陽新幹線の接続駅でもある西明石駅を経て、一級河川の加古川を渡れば、宝殿[ほうでん]駅だ。この駅名は、「石の宝殿」といわれる生石[おうしこ]神社に由来する。御神体の巨大な石造物は、水面に浮かんでいるように見えることから「浮石[うきいし]」と呼ばれ、パワースポットとして有名だ。この辺りで採石される竜山石[たつやまいし]は、古くは百舌鳥[もず]・古市古墳群に埋葬された石棺や、近代の名建築といわれるさまざまな洋風建築にも採用されていた。採石場の一つ「松下石材店」の松下尚平[なおひら]さんは、竜山石採石を誇りある産業として伝えるべく、地元の子どもたちにその魅力を教える活動を行っている。
工場地帯が広がる高砂市を抜ければ今回の最終地、姫路駅に到着。北出口から続く大通りの先に見えるのは世界文化遺産、国宝姫路城。大天守と3つの小天守からなる連立式天守で知られ、大天守は1609(慶長14)年に建築されたものが今に残る。
駅からバスで北上すると、「西の比叡山[ひえいざん]」と呼ばれる書寫山圓教寺[しょしゃざんえんぎょうじ]がある。ロープウェイに乗り継いで、息を切らして坂を登れば、標高371mの山上には伽藍が広がる。摩尼殿[まにでん]を中心に大講堂や常行堂などの重要文化財が点在し、写経や坐禅が体験できる。
旅の終わりは、姫路のご当地グルメ、生姜醤油でいただく「姫路おでん」に舌鼓。疲れた体に旨さが染み渡る。港町神戸から、古刹が残る姫路まで。時代が変わっても多くの人を魅了する、名所や文化に触れる旅であった。


播磨地域の特産を、生姜醤油[しょうがじょうゆ]で食す「姫路おでん」


創業25年を数える、姫路おでんの専門店「能古(のこ)」。出汁はかつおと昆布のみ。生姜はその都度すりおろし、出し汁で割った濃口醤油と合わせる。春菊、近江八幡の赤こんにゃくなど具材も鮮やか。
姫路を中心に限られた地域で生姜醤油をかけて食べる「姫路おでん」。その始まりは諸説あるが、醤油の産地、たつの市が姫路の西隣にあり、生姜も姫路地域で生産されていることもあり、昭和の初期頃にはこの食べ方がされていたという。
明石ダコや岩津ネギ、筍(たけのこ)など播磨の特産品も、旬に合わせておでんとして登場する。別添えの小皿で供される生姜醤油につけると、あっさりとして旨味が引き立ち、いくらでも食べられてしまう。


「姫路おでんは一年中食べても美味しい。季節に応じて地元の旬のものも添えています」と、店主の大橋ひとみさん。