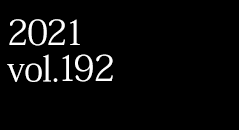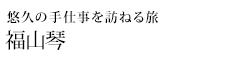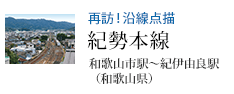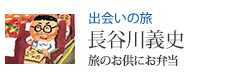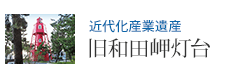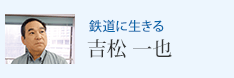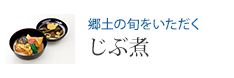新幹線の運行を司る東京新幹線総合指令所。「迷わず列車を止める意識の浸透」を取り組みの最重要事項の一つに掲げる。今回の主人公は同所で総括指令長を担う吉松 一也。

運用指令員と一緒に資料の確認をする。
1981年に当時の国鉄に入社し、大分駅、新大阪駅で駅係員として勤務した後、1990年に京都車掌区の車掌となった。ある日新幹線指令員の公募を目にし、自ら手を挙げ、1998年に東京新幹線総合指令所に着任、新幹線指令員としての歩みをスタートした。初めての新幹線の世界。在来線とは運転する仕組みも車両も異なり、全てが一からの勉強だった。
指令員は、現場からの情報をもとに列車の運行に関する判断を行わなければならない。だからこそ“言葉”を特に大切にしてきた。
そんな中で、反省を強く心に刻んだ事象がある。2017年12月の新幹線重大インシデントだ。安全に関して強固なハード対策が施されている新幹線でも、言葉が重要な意味を持つことをあらためて痛感した。「言葉は相手に正しく伝わらなければ意味がありません。“言ったつもり”“そんなつもりで言ったのではない”は通用しません。また聞く側も“聞いたつもり”“わかったつもり”ではいけません。確認会話が非常に重要です。」

列車指令員と臨時列車の設定に関する打ち合わせを行う。
現在、吉松は当日の運行管理責任者である総括指令長を担っている。総括指令長は、当日の指令業務の最高責任者として、大規模災害が見込まれる場合や輸送障害発生時の対策策定、会社を跨ぐ事象が発生した場合の他社との調整を行うとともに、指令員のマネジメントなどを担う。
また、運転再開の最終判断も重要な役割の一つだ。“「危ないと感じたとき」と「安全が確認できないとき」は「迷わず列車を止める」”ことが重要であり、指令員自身が「不安だ」と判断したら迷わず列車を止めるよう常日頃から伝えています。結果として止める必要がなかったとしても、安全サイドへの判断のため褒められるべき考動であると考えています。これに対して、運転再開は判断を誤れば危険に直結するため、不安の残る状態で判断を行ってはならず、安全な状態であることを確認できたとき初めて判断ができます。この判断は現場からの情報をもとに行います。現場で対応している社員は、一早く状況を解決したいという思いを持ちながらも、なすべきことが多々あり大変忙しい状況にあります。そんな人たちを急かすようなことをしては、確実に判断するための情報を得ることができません。指令員に対しては、現場で対応してくれている仲間を信頼して焦らずに待つこと、待っている間に自分たちができることを着実に行うことが大切と伝えています。」

関係箇所と丁寧に確認会話を行う。
技術革新により鉄道や職場を取り巻く環境は大きく進化している。新幹線重大インシデント以降、言語技術教育の取り組みが始まるなど、ハード面だけでなくソフト面においても多くの仕組み、ルール、マニュアルが整備されてきた。「人財育成のあり方は、時代や環境によって変わるものです。これからの時代、生き字引だけに頼らないシステム化した育成方法に転換していかなければならないと思います。一方で引き続き人が伝えていくべきこともあります。それは“ハート”です。鉄道員魂、指令員魂は、マニュアルでは伝えることはできず、私たちが後輩に伝えることで着実に引き継いでいかなければならないと考えています。」
最後にコロナ禍にある今、今後の展望を聞いた。「人々の生活スタイル、価値観は大きく変わりつつあります。収束後も元通りとはならないでしょう。しかし、安全が私たちにとって最も大切であることに変わりはありません。先人たちの経験と知恵とを引継いだ私が、さまざまな重大事象や技術革新などを踏まえて講じられてきた安全対策をさらにアップデートさせて後輩に引き継ぐことに力を尽くしたいと考えています。また、変革の時代を迎えた今、速やかな問題解決には多様な考え方が必要です。指令員一人ひとりが“感じたこと”や“思ったこと”を素直に発言できる職場づくりに貢献していきたいと思います。」変わりゆく時代を前向きに受け入れ、安全を追求し続ける吉松の背中は頼もしかった。