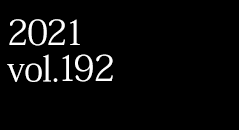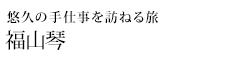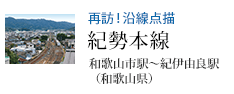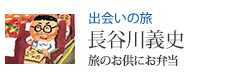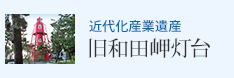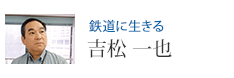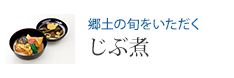海岸に沿って、美しい砂浜と松林が広がる須磨海浜公園。その西端に、現存する鉄造灯台としては
日本最古といわれる旧和田岬灯台の姿がある。
今では、兵庫開港の歴史を物語るモニュメントとして地域の人々に親しまれている「須磨の赤灯台」。国際都市神戸の発展を支えた航路標識の足跡をたどる。

移設から半世紀以上、今では地域のランドマークとして親しまれる。廃灯に伴い、灯台としての機能は和田岬から約2km離れた遠矢浜に新設された灯台に引き継がれた。1998(平成10)年、国の登録有形文化財となり、2008(平成20)年には横須賀市の観音埼灯台などとともに、日本の灯台建設の歩みを物語る近代化産業遺産群として認定されている。

旧和田岬灯台へは、山陽本線「須磨海浜公園」駅から南西方面へ徒歩約8分。

木造、白色塗装の初代和田岬灯台。
(公益社団法人 燈光会所蔵)
航海の安全を守る灯台は、海と陸地との境目に塔状の目印として立つ。最上部には光を放つ光源が設置され、航路標識の代表といわれる。その始まりには諸説あるが、日本では復路離散した遣唐使船の目印に、九州地方の岬や島で篝火[かがりび]を焚いたことが起源と考えられている。江戸時代に入り海運が盛んになると、岬の先端や港に近い神社の境内には「灯明台[とうみょうだい]」や「常夜灯」などが置かれたという。
光力の弱い灯明台に代わり、光達距離に優れた灯台の建設が始まったのは、幕末期の開国がきっかけとされる。1866(慶応2)年、江戸幕府は諸外国との間に改税約書(江戸協約)を取り交わし、樫野埼、観音埼、潮岬、神子元島[みこもとしま]など計8灯台の建設を約束する。また、1867(慶応3)年には、兵庫開港に備えて外国船の夜間航行の安全を確保するため、イギリスとの間で大坂約定[おおさかやくじょう]を締結。関門海峡から大阪湾内に5カ所の灯台(部埼[へさき]・六連島[むつれじま]・和田岬・友ヶ島・江埼)を設置することを決定した。明治維新後、これらの灯台建設は新政府に引き継がれ、1871(明治4)年4月、兵庫港の南西に初代和田岬灯台が竣工した。設計・監督は、イギリス人技師リチャード・ヘンリー・ブラントン。技術指導に留まらず、灯台守の養成や保守システムづくりにも貢献したブラントンは、「日本の灯台の父」と呼ばれている。

最上部から東の方角を望む。移設の際は一度解体され、約6km東の和田岬から海上を通ってこの地に運ばれてきたという。

螺旋階段。1層目から2層目に向けて螺旋状に伸びる重厚な鉄製階段。六角形鉄骨造に改築された当時の姿のままに残されている。
1層目内部。1辺約3.9mの室内を壁で仕切り、倉庫と作業所に使用。無駄がなく、最小限の部材で建てられているのが特徴という。


青空に映える赤い塔の頂では、灯台として機能していた頃の名残のように、当時の風向計が悠々と風を受けている。
フレネル式レンズと台座。フランスの物理学者フレネルによって発明されたレンズは、のこぎり型の断面形で光源からの光を水平方向に遠くまで届けた。台座部分に残る刻印から、1870(明治3)年製造の初期灯台のものとわかる。

当初の和田岬灯台は、木製八角形の3層構造で、外面は白色に塗装されていた。木造灯台は耐久性に乏しく、火災の危険もあるため、主に急設を要する4等※1以下の灯台に適用されたという。鉄骨造に改築されたのは1884(明治17)年。鉄製六角形の3層構造で、灯光も石油灯からガス灯に変更された。やがて、和田岬は造船など重工業の拠点となり、工場が建設されていく。その建物と区別するため、1914(大正3)年には現在の赤い外壁に塗装されたと記録に残る。その後、周辺は埋め立てが進み、1963(昭和38)年に廃灯。新設の灯台に役目を譲り、現在地の須磨海浜公園に移設・保存された。
現在、旧和田岬灯台は松の木立の中で佇む。入口の記念額「明治五年一月二十九日初点燈於舊臺[きゅうだい](旧灯台)※2一七年三月一日再点燈於新臺(新灯台)」の文字が、改築の経緯を示す。中に入ると、1層目は燃料などが備蓄された倉庫と灯台守の作業所に区切られ、中央部分から螺旋階段が2層目へと伸びる。狭く急なこの階段を、灯台守は日に何度となく往復したそうだ。3層目の灯籠内には、明治初期のフレネル式不動レンズが破損しながらも残り、暗い海に光を届けた往時が偲ばれる。灯台の近代化を物語る貴重な史跡は、今も海を望む場所で存在感を示している。
- ※1:レンズには、いちばん大きい1等から順に6等までと6等より小さい等外という等級があり、レンズの焦点距離で決まる。
- ※2:現在の公式記録では、初点灯は記念額とは異なり、1872(明治5)年8月29日となっている。