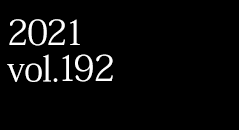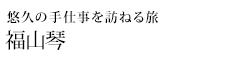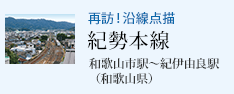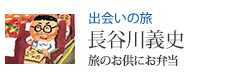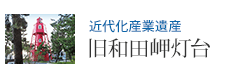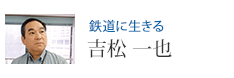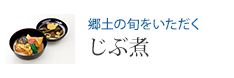紀勢本線は和歌山市駅から三重県の亀山駅まで全長384.2kmの長大路線。今回は、和歌山市駅から紀伊由良駅までの49.7kmを旅した。たわわに実ったみかん畑を車窓に、万葉人が愛でた風景を眺めつつ南へと走る。

和歌山城天守閣からの眺望。天候がよければ、淡路島や四国まで望める。

紀州55万5千石の和歌山城。現在の天守閣は、1958(昭和33)年に再建された。
虎伏山[とらふすやま]に立つ和歌山城は、徳川御三家の一つ紀州藩55万5千石の居城だ。名君の誉れ高く、徳川8代将軍にもなった徳川吉宗が治めたことでも知られる。白亜三層の天守に登ると、好天であれば、はるか淡路島まで望める。
城の南側に広がる寺町のお寺に足を運ぶと、巨大なお顔だけの大仏に遭遇した。首大仏が境内に鎮座する無量光寺だ。高さ約3mの巨大なお顔は迫力いっぱいで、お顔を拝むことでまざまなご利益があるといわれ、受験シーズンには学生たちがこぞって訪れる。
旅の起点は和歌山市駅。ホームを離れた列車は紀和駅を過ぎ、阪和線や和歌山線が乗り入れる交通の要衝、和歌山駅へ。ここからホームが替わり、車両を乗り換える。宮前駅を過ぎ、和田川を渡ると紀三井寺駅に到着だ。

1684(貞享元)年に和歌山城下吹上邸で生まれたとされる徳川吉宗。紀州藩5代藩主となり、1716(享保元)年には徳川8代将軍を襲職。「徳川中興の英主」といわれる。

紀州藩10代藩主の徳川治宝が建立した浄土宗の無量光寺。高さ3mの首大仏は元々、末寺の仏像だったが1835(天保6)年に焼失。溶け出した銅だけで再び鋳造され、その後、無量光寺に移された。


創建770(宝亀元)年の紀三井寺。寺の名前は、境内の三つの井戸に由来する。西国三十三所第2番の札所。

室町時代から紀州漆器の産地として栄えた黒江。のこぎり歯状の町家には、かつて職人が生活していた。
駅から東にほどなく歩けば、紀州藩歴代藩主が繁栄を祈願したとされる紀三井寺がある。見上げるように続く231段の石段は民話『結縁坂[けちえんざか]』で有名な縁結びで知られる坂だ。そんな階段を上り切れば、陽光でキラキラと輝く和歌浦の風光が一望できる。
対岸の和歌浦には和歌の神様、衣通姫尊[そとおりひめのみこと]を祭祀した玉津島神社が鎮[しず]まる。和歌浦は万葉人が憧れた景勝地で、神社の背後に控える奠供山[てんぐやま]からの景色は、玉津島に行幸された聖武天皇が絶賛したとされる。山頂からはアーチ型の不老橋を眼下に広大な干潟の風景が広がる。その景勝は山部赤人や柿本人麻呂などの万葉歌人によって詠われ、多くの歌が万葉集に収められている。
紀三井寺駅から隣の黒江駅まで約4分。駅から少し離れた南側には「黒江地区」がある。この地もまた古く万葉集に詠まれた景勝地で、かつては入江だった。やがて漆器の産地として知られるようになり、江戸時代には隆盛を極めた職人の町となった。延長約230m、幅約12mの川端通り周辺には、格子の町家が“のこぎり歯”のように斜めに立ち並んだ一角がある。諸説あるそうだが、建物が敷地から少し斜めに建ち並んでいるのは、荷車などを頻繁に停める際に必要なスペースを設けるための知恵だとされている。

万葉人も憧憬した名勝 和歌浦

聖武天皇が愛でたと伝わる奠供山からの眺望。1910(明治43)年に、当時「東洋一」と称された高さ30mの昇降機が和歌浦眺望のために設置されたという。夏目漱石の小説『行人』に登場している。

和歌の神、衣通姫尊が祀られ、多くの和歌が奉納された玉津島神社。
和歌山市の南西部に位置する和歌浦は、和歌川の河口部に広がる景勝地だ。聖武天皇の行幸の際に万葉歌人 山部赤人が詠んだ「若の浦に 潮満ち来れば 潟を無み 葦辺をさして 鶴鳴き渡る」の歌で知られるように、海のない都人の憧れの地であった。
和歌浦には玉津島神社をはじめ妹背山に架かる三断橋、片男波[かたおなみ]の砂洲や湾に浮かぶ島嶼[とうしょ]…、他にも紀州藩初代藩主頼宣が、父である家康を祀った紀州東照宮や和歌浦天満宮など歴史的な文化財が多数存在する。和歌浦は「絶景の宝庫 和歌の浦」として、2017(平成29)年に「日本遺産」に認定された。

列車は有田みかんの段々畑を車窓に走る。(紀伊宮原駅〜藤並駅)
列車は黒江駅から海南駅を過ぎ、進路を西に難読駅の冷水浦駅を過ぎる。「しみずうら」と読む。箕島[みのしま]駅を過ぎると、車窓には緑の中に黄金色が点々と続く風景が現れる。特産物の有田みかん畑だ。山々の斜面に実ったみかんの段々畑の風景に見入るうちに列車は有田川を渡る。藤並駅を通過すると、“醤油醸造のまち”の玄関口、湯浅駅だ。
新設された湯浅駅から南北に走る熊野古道を辿り、西に入ると白壁土蔵や格子戸の商家が軒を連ねた古い町並みがある。東西約400m、南北約280mの一帯は国の「重要伝統的建造物群保存地区」で、古くから受け継がれる手づくり醤油醸造の歴史をその佇まいとともに現在に伝えている。
湯浅は熊野三山へ続く熊野古道の宿場町だった。そして、何より湯浅の名を知らしめたのが醤油。鎌倉時代に宋より伝わった金山寺味噌の副産物として誕生した醤油は、湯浅がその発祥の地だ。江戸時代の最盛期には92軒もの醤油蔵があったという。かつては藩に保護された手づくり醤油蔵だが、量産品が流通する時代の流れでその数は激減した。創業180年の「角長[かどちょう]」6代目の加納誠さんは、「現在では湯浅に醤油蔵は4軒。角長が今日まで続けてこられたのは、昔ながらの手づくり醤油一筋に徹したから。角長の醤油でないと、と言ってくださるお客様は多いです」と胸を張る。

醤油づくりに不可欠な酵母の棲みつく角長の醤油蔵。現在も昔ながらの手作業で品質管理をしている。


湯浅湾に注ぐ山田川河口に設けられた内港の大仙堀。「しょうゆ堀」とも呼ばれ、醤油や原料の積み下ろしで賑わった。
1841(天保12)年創業の手づくり醤油蔵「角長」。6代目の加納さんは、「醤油蔵は年々、減っているのが現状です。厳しい時代ですが、それでも昔ながらの手づくり醤油にこだわり続けます」と話す。屋号は「角屋長兵衛」に由来する。

和歌山県内でしらすの水揚げ量が最も多い湯浅。「しらす丼」は湯浅の新名物として町内には提供するお店が10軒を超える。

湯浅の特産品である醤油や金山寺味噌などお土産が充実する「湯浅美味いもん蔵」。2階では、湯浅特産のしらすを使った料理が楽しめる。

醤油発祥の地 湯浅の重要伝統的建造物群保存地区。北町通りには、伝統の湯浅醤油や金山寺味噌などを扱う商家の瓦屋根や格子が続く。

湯浅町の新拠点「湯浅えき蔵」

「湯浅えき蔵」2階の図書館。高さのある本棚の裏側には、おしゃれなカフェが併設されている。

湯浅の新たな拠点となった湯浅駅と「湯浅えき蔵」。
2020(令和2)年3月に湯浅駅と一体化してつくられた複合施設「湯浅えき蔵」が全面オープンした。駅舎は“醤油醸造のまち”にちなみ、醤油蔵がモチーフになっている。3階建ての建物は1階に観光案内所や観光交流センター、2階にはおしゃれなカフェや図書館が設置されている。3階にはコンサートなどを催せる地域交流センターが設けられ、地域交流の拠点としての役割を担っている。3階と屋上は南海トラフ巨大地震による津波を想定した設計により、約800人の避難が可能だ。
湯浅から広川を挟んだ隣町の広川町は「ヤマサ醤油」7代目、濱口梧陵[はまぐちごりょう]の生誕地だ。地域の人々からは尊敬の意を込めて「ごりょうさん」と親しまれている。旧広村は1854(安政元)年の安政地震の際に、大津波に襲われ甚大な被害を被った。しかし、梧陵が事前に稲むらに火をつけ、それを目印に村人を誘導し、いち早く高台の廣八幡宮[ひろはちまんぐう]に避難させ、多くの命が救われた。この『稲むらの火』の教訓は現代にも通じている。2017(平成29)年の第70回国連総会本会議では、津波のあった11月5日を「世界津波の日」として制定された。

旧広村出身の濱口梧陵が村人を避難させた廣八幡宮。小高い丘陵地に鎮座し、山頂は海抜約40m。地域の氏神でもある。
広川ビーチ駅を過ぎるとまもなく旅の終点、紀伊由良駅だ。西方に行けば、万葉ゆかりの白崎海岸が広がっている。
紀伊半島の西を辿る今回の紀勢本線の旅は万葉の風景に触れ、日本の味のルーツを訪ねる旅であった。

濱口梧陵を顕彰[けんしょう]する「稲むらの火の館」

「稲むらの火の館」の中にある「津波防災教育センター」には、『稲むらの火』の物語や津波防災の歩みなどが展示されている。

館長の 山光一さん。
山光一さん。

梧陵の功績や教訓、津波の恐ろしさを現在に伝えている「稲むらの火の館」。
広村堤防からほど近い「稲むらの火の館」は、町が誇る濱口梧陵を顕彰する施設として2007(平成19)年に開設された。
旧広村で生まれた濱口梧陵は、安政地震による津波で家や仕事を失った村人たちを救うために私財を投じ、村の再建に尽力。そのシンボルが広村堤防だ。館長の 山光一さんは、「安政の地震はマグニチュード8.4。大津波が旧広村をのみ込みました。梧陵さんの避難誘導がなければ、壊滅的だったと聞いています」と話す。この後、梧陵は100年後の津波に備えるため広村堤防を村人の協力で完成させた。昭和南海地震ではその役割を果たし、現在も広川町を護り続けている。
山光一さんは、「安政の地震はマグニチュード8.4。大津波が旧広村をのみ込みました。梧陵さんの避難誘導がなければ、壊滅的だったと聞いています」と話す。この後、梧陵は100年後の津波に備えるため広村堤防を村人の協力で完成させた。昭和南海地震ではその役割を果たし、現在も広川町を護り続けている。