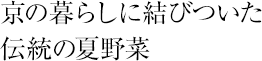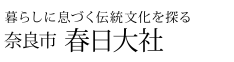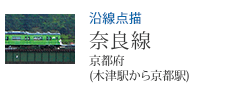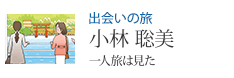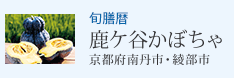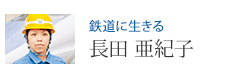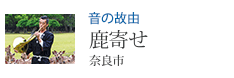![]()
京野菜と呼ばれるものには、古くからの主産地の名を冠するものが多い。
胴にくびれを持つ、大ぶりの鹿ケ谷かぼちゃもその一つ。
京都盆地の東部、五山の送り火で知られる大文字山(如意ケ嶽[にょいがたけ])の麓の鹿ケ谷で生まれ、200年にわたる栽培の歴史を持つ。
京都が誇る伝統野菜、鹿ケ谷かぼちゃの旬に触れた。
京都の食文化を語るうえで欠かせないのが、特産品として名高い京野菜である。京都は地理的に海から遠いため、新しい魚介類が手に入りにくかったこと、また茶道の懐石料理や寺院の精進料理が発達したことなどを背景に、古くから良質で多品種の野菜が求められてきた。さらに、盆地特有の寒暑の差の激しい内陸性気候や豊富な水、腐植質を含んだ肥沃な土といった自然条件も加わり、土地に根ざした野菜が数多く生み出された。

だしをきかせた料理との相性が良い鹿ケ谷かぼちゃ。
淡泊な味わいに肉の旨みを添えた「鶏そぼろあんかけ」は、おすすめの食べ方の一つ。
ひょうたん型の外観が特徴の鹿ケ谷かぼちゃも、京の風土が育んだ代表的な品種。鹿ケ谷は地名で、専修念仏で知られる法然が草庵を結んだ地でもある。『京都府園芸要鑑』(1909年刊行)によると、起源は文化年間(1804〜1818年)。洛東・粟田村の農夫が、奥州津軽から持ち帰ったかぼちゃの種を隣村の鹿ケ谷の農家に分け与え、栽培されたのが始まりという。初めは普通の菊座形のものができたが、数年作っているうちに胴がくびれた独特の形になった。以来、生誕地の鹿ケ谷を中心に、近郊各地でも作られるようになり、昭和初期に新しい品種が出回るまでは、京都でかぼちゃといえば鹿ケ谷かぼちゃを指すほど普及していった。

南丹市園部の産地
今では、かつてのように家庭の食卓に上ることは少なくなったが、京料理には欠かせない素材で、形のおもしろさから茶席の飾りや花材など観賞用の利用も多い。また、明治以前から京都府内で栽培されていたことなどが基準となる「京の伝統野菜」にも指定され、昔ながらの味を今日に伝えている。
鹿ケ谷かぼちゃは名前の由来となった土地を離れ、現在は京都府南丹市や綾部市へと生産の場を移している。野菜の生産地は、戦前までは京都市街地の外、「洛外」であった。しかし、都市化が進み、洛外は家々が建ち並ぶ市街地へと変貌した。こうして生産の場や食の嗜好の変化で、市場ではほとんど姿を見ることのない品種も少なくない。鹿ケ谷かぼちゃもまた、品種の保存に努める数軒の農家によって、その伝統が守られている。
栽培は3月の播種から始まり、収穫時期は7月上旬〜8月中旬。暑さの盛りに旬を迎える夏野菜だ。大きいものでは高さ20cm以上、重さは2〜3kgほどになり、深緑色の果実の表面には幾条もの筋とコブがある。保存性にも優れ、夏に収穫しても年内までは日持ちがするそうだ。ごつごつとした外見に比べて、食味はあっさりと淡泊。果肉のきめは細かく粘質で、だしをよく吸い煮崩れしないのが特徴という。この淡白な風味に鶏肉の旨みを沁み込ませた「鶏そぼろあんかけ」は、鹿ケ谷かぼちゃならではの持ち味が生かされた一品だ。
毎年7月25日、鹿ケ谷にある住蓮山安楽寺では、甘辛く炊いたかぼちゃを参拝客に振る舞う「かぼちゃ供養」が行われる。「夏の土用の頃に当地のかぼちゃを振る舞えば病気にならない」というお告げを受けて始まったこの行事では、特別に農家に委託して栽培された鹿ケ谷かぼちゃが煮炊きされる。旬の味覚が、歳時記の中に実っている。

晩生種のため栽培期間が長く、地面に接して日が当たらない部分が黄色くならないように、果実を転がす「玉回し」という作業をしながら成長を見守る。

種は下部の大きい方にだけあり、この部分の味が良いそうだ。写真は、形のおもしろさを利用し、種を取った部分に色鮮やかなすり身を詰めた「海老鋳込みあんかけ」。
かぼちゃは一度蒸してから、だし汁で煮込む。