 |
 |
 |
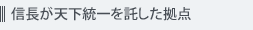 |
安土の町の名は日本の歴史上に確固と記されている。安土・桃山時代(1568〜1600年)の安土とは、織田信長が天下布武の夢を託して琵琶湖を見晴らす安土の山上(199m)に城を築き、ここを天下統一への足がかりにしたことに由来している。

駅を出てすぐ目にするのは太刀を片手に、扇をかざして遠くを見つめる信長の立像だ。近くには幻の安土城を20分の1スケールで復元した精巧な模型を展示している城郭資料館もある。町内にはほかに、安土城天主(天守)の最上部を原寸で復元した「信長の館」、「相撲やぐら」やキリシタン神学校の「セミナリヨ跡」など信長ゆかりの史跡があって、のどかな田園風景の中を一つ一つ訪ねるのが町歩きのコースになっている。

例年6月に催される「あづち信長まつり」は町をあげての祭りで、戦国武者に扮した行列がお目見えするが、信長をもっと身近に偲ぶにはやはり安土城跡に佇んでみることだ。天主閣へと続く長い石段の一段一段に、天下取りを目前にした信長、そして秀吉や家康の気配や息遣いまでも感じ取れそうだ。 |
 |
 |
 |
 |
| 整備された大手通りの長い石段。下から仰ぐと圧倒的なスケール感があり、攻めてくる敵陣もこの石段を見たら戦意を喪失するのではないかと思われるほど。石段に沿って、雛壇上に秀吉や家康の屋敷があったとされている。 |
 |
 |
| 信長の時代、安土城下には楽市楽座が設けられて賑わった。随所に堀が巡らされた水郷の町としても知られる。 |
 |
 |
|
 |
 |
駅を出てすぐ出迎えてくれるのは信長の立像。信長は現在も安土町のシンボルである。 |
 |
 |
安土町内には信長や安土城の資料が展示された施設が点在している。中でも「信長の館」に実物大で再現された安土城天主閣は圧巻。 |
 |
 |
安土駅の南広場にある相撲櫓。信長が催した相撲興行は近代相撲の発祥といわれる。 |
 |
 |
セミナリヨはイタリア人宣教師オルガンチノによって創立されたキリシタン神学校。現在は公園として整備されている。 |
 |