 |
 |
水の中をゆらゆらと漂う金魚。
ガラス越しに眺める小さなその姿は、
涼感を誘う夏の風物詩である。
日本人は、金魚を観賞の対象とし、
夏祭りや縁日の余興にも取り入れてきた。
明治・大正・昭和と活躍した
青木月斗の句とともに
金魚と暮らしとの関わりの歴史をたどってみた。 |
 |
![平明で、至味[しみ]ある作句を唱える](image/poet_caption01.gif) |
| 青木月斗は、1879(明治12)年大阪で薬種商を営む青木家の長男として生まれた。本名は新護[しんご]といい、文学的素養は、和歌や発句を嗜んだ母親ゆずりといわれる。病弱のため、1年遅れで尋常小学校に入学した月斗は、のちの山中北渚[ほくしょ]、松村鬼史[きし]と出会う。彼らは生涯、俳句交遊を重ねる仲間となる。1894(明治27)年、大阪薬学校(現大阪薬科大学)に入るが、まもなく中退し、家業を継承。薬房経営に励むかたわら、北渚や鬼史らと句作に精を出した。この頃は月兎(28歳の頃月斗に改号)と名乗り、新聞『日本』の子規選に投句を続け、やがて正岡子規の認めるところとなる。1899(明治32)年には、関西における子規門の最初の俳誌『車百合』を創刊。わずか3年ほどで廃刊したものの、創作意欲は衰えず、各地の俳誌の選者を務めるなど、関西俳壇の中で名声を高めていった。その後、『カラタチ』に続き終生の主宰誌『同人』(1920(大正9)年)を創刊する。冒頭の句は、月斗が選者となった『同人俳句集』(1931(昭和6)年刊)に収められている。「句は味であり、調べである」を信条に、明朗で簡明直栽な句作りを提唱した月斗らしく、素直な情景描写で詠われている。 |
 |
 |
| 豪放磊落な人柄が多くの人を集めたといわれる月斗。句作第一主義を提唱しながら門下を指導し、多くの俳人たちを世に送り出した。(松本島春氏蔵) |
 |
 |
| 明治風俗画で多くの佳作を残した橋本周延[ちかのぶ]代表作、36枚揃えの美人画のうち、10番目の作品には金魚を持った少女が描かれている。(『真美人 金魚』/箱本館「紺屋」蔵) |
 |
 |
| 体のつくりをはじめ餌や水換えなど、金魚を飼うための情報が網羅された、日本で最初に出版された金魚飼育書『金魚養玩草』。(郡山金魚資料館蔵) |
|
|
|
 |
![金魚玉に聚[あつ]まる山の翠微[すいび]かな 月斗](image/poet_text.gif) |
 |
 |
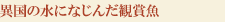 |
縁日の金魚すくいに代表されるように、日本の夏を象徴する金魚だが、実は中国伝来の魚である。渡来の時期については諸説あるが、1748(寛延元)年に刊行された安達喜之[よしゆき]著の『金魚養玩草[きんぎょそだてぐさ]』の中に、室町時代の1502(文亀2)年に泉州左海の津(大阪府堺市)に渡来したことが記されており、これが定説となっている。最初にやってきた金魚は、ヒブナが変異した現在ワキンと呼ばれる品種で、人々は「コガネウオ」と呼んでいたという。長崎や堺などの港町に入ってきた美しい舶来の小魚は、豪商や大名の手に渡り、上方を中心に金魚観賞の文化は広がっていった。

当初は、富豪や武家階級など、限られた人たちの間のぜいたくな愛玩物であったが、江戸時代の中頃から幕末にかけて、庶民にも広く普及し始める。金魚の入った桶を天秤棒でかついで歩く行商人が現れ、「金魚え〜、金魚」の呼び声が町中に響くようになったのもこの頃である。幕末にはビイドロと称してガラスが普及。球体の薄いガラスの器は金魚玉[きんぎょだま]と呼ばれ、手軽な運搬具として人気を博し、金魚売りには欠かせない小物となっていた。人々は、この金魚玉に金魚を入れて持ち帰り、そのまま家の軒先に吊るすなどして水の中の姿を観賞し、夏の暮らしに涼を呼んでいたのであろう。 |
 |
 |
 |
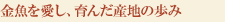 |
奈良県北部に位置し、その昔15万石の城下町として栄えた大和郡山。日本有数の金魚の産地として知られ、のどかな田園風景が広がる一帯には金魚田が点在する。郡山の金魚は、1724(享保9)年、甲斐の柳沢吉里[よしさと]が郡山に国替えされた時に持ってきたと伝えられる。金魚好きの殿様は、家臣にも飼育を奨励したことから、金魚養殖は下級武士の内職にもなっていたという。さらに、最後の郡山藩主柳沢保申[やすのぶ]は、1887(明治20)年「柳沢養魚研究所」を設立。廃藩置県によって失職した士族救済の事業として援助を惜しまず、後継者の保恵[やすとし]もまた、1900(明治33)年「柳沢養魚場」を開設して品種の改良や販路拡大に尽力。周辺農家も巻き込み、地場産業としての礎を築いていった。

奈良県郡山金魚漁業協同組合長の西川吉郎氏によると、こうした歴史的背景に加え、養殖に適した地理的環境に恵まれたことも発展の要因という。「佐保川と富雄川に挟まれた水が潤沢な地域。農耕用の溜め池では、エサとなるアカコが簡単に手に入りました」。郡山の金魚養殖は、米作りと並行して行う水田養魚が中心。池堀よりも広い面積での飼育は、大量生産を可能とした。現在も約80戸の生産農家が金魚すくい用のワキンをはじめ、ランチュウなど高級魚の養殖に励んでいる。毎週水曜日の競りの後、郡山の金魚は日本の夏に彩りを添えるため、全国各地へと旅立っていく。 |
 |
 |
| 金魚はフナの野生種から突然変異と交雑を繰り返し、観賞の対象として品種を固定化して生産飼育されてきた。体形は大きく「ワキン型」(上)「リュウキン型」(中)「ランチュウ型」(下)の3種に分類される。(やまと錦魚園・郡山金魚資料館) |
 |
 |
| 出荷を控えた金魚は、養魚池から透明な水に移して体を慣らした後、各地に送られる。 |
 |
|
 |
 |
|
|
 |