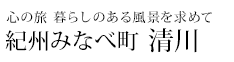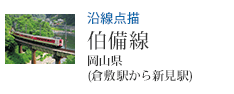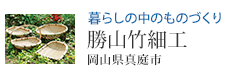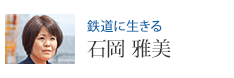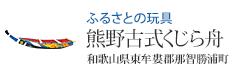- 初の劇場映画「萌の朱雀」(1997年)でカンヌ国際映画祭カメラドール (新人監督賞)を史上最年少受賞し、鮮烈なデビューを果たす。「殯の森」(2007年)で同映画祭グランプリを受賞。「玄牝-げんぴん-」などドキュメンタリー作品も多数。昨年にはカンヌ国際映画祭で、日本人監督として初めて審査員を務めた。今年、祖母の故郷である鹿児島県奄美大島を舞台にした最新作『2つ目の窓』が大ヒット上映中、秋には世界公開を控える。今年9月12−15日開催の「なら国際映画祭」ではエグゼクティブディレクターとして奔走中。
-
- 公式サイト www.kawasenaomi.com
- 公式ツイッターアカウント @KawaseNAOMI
幼少の頃、冬休みには城崎温泉に行くのが我が家の習慣だった。幼い頃に両親が離婚をして、小学校時代に祖父母世代の子供がいない老夫婦のもとに養女にもらわれた。この養父が車の運転が好きで、週末はいつも郊外のデパートに買い物に出かけた。彼の田舎は岐阜だったので、夏休みには岐阜へのお墓参りをかねて長良川の鵜飼を見た。そんな思い出たちがわたしの中にある。なかでも、城崎温泉にはいつも泊まる宿があって、行くと馴染みの感じで仲居さんが出迎えてくれるので嬉しかった。「ゆとうや」というその旅館は温泉街の中程にあったように思う。創業が1688年というから江戸時代にさかのぼる。やけに大きな門構えを記憶している。そして古い木造建築の独特の佇まいと匂いも。いつかの冬。いつものように「ゆとうや」を訪れ、蟹鍋の夕食をいただき、温泉に浸かった。小学校に入ったばかりの頃で自分で何かができることが嬉しくて、その広い旅館のどこに自分たちの部屋があるのかをしっかり記憶し、ひとりでお風呂から部屋に戻れることが嬉しかったのだろう。養父母を驚かすために、ひとりで部屋に戻ろうとした。が、なぜだかそこに寝間着や浴衣がなかったので、誰とも遭わないことを願ってわたしは素っ裸のままで廊下へ飛び出した。そして長い廊下を走って部屋に戻る途中、やはりそんな時に限って仲居さんと遭遇してしまった。顔から火が出るほど恥ずかしかったが、そのまま苦笑いでその場を走って通り過ぎた。今から思えば誰かと遭わないことなんてないということがわかるけれど、そのときは冒険をしているような気になっていたのかもしれない。老舗旅館なのに子供が素っ裸で走っている光景をお客様に見られていたかもしれないなんて、申し訳ないことをしたと思う。しかしわたしには今でもそのような無謀なことをする時があって、後から考えてなぜあんなことをしたんだろうと思うのだが、不思議とそうしたことの記憶は鮮明だ。生まれついての独創的な性格なのかもしれない。ルールや常識ということからいつも少し離れた考えが脳裏をかすめる。映画を創るようになってから、むしろそういう感覚を映画にしてゆくことで自分の居場所を見つけたのかもしれない。
城崎は映画学校で講師をしていた頃に慰安旅行で訪れたこともある。幼少の頃以来だったのでとても懐かしく湯に浸かった。途中出石のそばを食べ、お土産には甘エビを持ち帰った。大人になると食べることへの楽しみが増えるようだ。その土地の名物料理とお酒に舌鼓を打つ。そこに土地の人との対話が加われば尚よい。さて、そんな城崎への想いから高校時代の友人たちと久しぶりに集まって温泉でも行こうということになり、そのときは電車で訪れた。自分で働いたお金で女の友人と旅をすることで自分がもう学生ではないのだという少し寂しいような気分にもなった。専業主婦になっている友人とはあんなに仲がよかったのに今の自分の立場からは全く別の世界で生きているような感覚のことを聞かされたりして、驚くことがしばしばだ。水道やガス代を節約するための術やリサイクルで得をする方法などを聞くにつれ、立派だなと思うのだが自分には全くその余裕がないことに後ろめたさも感じる。この時一緒に行った一番仲のよかった友人がいる。小学校時代から知っていて中学も同じ塾も同じ高校も同じで毎日バスで一緒に通っていた。30歳を過ぎた頃同窓会の会場でトイレに行った時、彼女が「わたし癌やねん」と言った。耳を疑ったが「もう手術したから大丈夫」と聞かされ安心した。2年後再発、還らぬ人となった。まだ小学校にあがる前の幼い子供のいる身だった。彼女との最後の旅となった城崎温泉。城崎の駅のホームで電車を待っていた時に吹き抜けた風の匂い。そんなことと一緒に時折彼女の屈託のない笑顔を想い出す。城崎はもういない人の面影とともに久しぶりに訪れてみたくなる場所である。