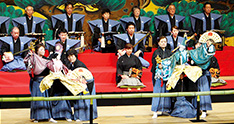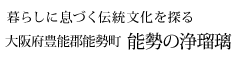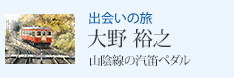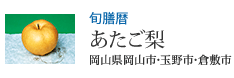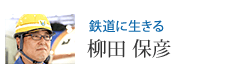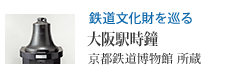- 1974年大阪府出身。京都大学大学院卒。脚本家・プロデューサー、日本チャップリン協会会長、劇団とっても便利代表。チャップリン研究の第一人者として国際的に活動。映画研究に対して、イタリアのポルデノーネ無声映画祭特別メダル。脚本・プロデューサーを務めた映画『太秦ライムライト』で、カナダのファンタジア国際映画祭最優秀作品賞他多数受賞。『チャップリンとヒトラー メディアとイメージの世界大戦』(岩波書店)で、第37回サントリー学芸賞受賞。京都市文化芸術表彰受賞者。
原稿を前に何を書けばいいのか戸惑っている。
それは、僕がJRを偏愛する鉄道マニアであるからで、はたして本稿では、実家からほど近かった山崎駅の大カーブでの撮影の思い出か、北陸本線の敦賀・新疋田間のループの撮影ポイントを探して一日中歩いたことか、今はなき大阪駅11番線に滑り込んできたピカピカに磨かれたお召し列車塗装のEF58の美しさか、そのどれを書けばいいのか戸惑っているわけだ。
子供の頃、全国一本につながった国鉄2万キロの路線図を、乗った順に地図で塗り潰していくのが楽しみだった。早朝でも深夜でも、行き先々で黙々と業務に従事する鉄道マンたちに出会った。本来は無機的であるはずの、鈍く冷たい鉄路が、かくも人間的な温かみと哀愁を持って光るのは、鉄道マンたちの誇りがそこに捧げられているからだろう。
僕の小学生最後の日に、国鉄は115年の歴史を終えた(最終日は全線乗り放題の「謝恩フリーきっぷ」で乗りまくった)けど、JR西日本はその歴史の正当な末裔だと思っている。500系新幹線のような先鋭的な列車を創る技術と発想を持ち、他方梅小路では我が国の発展を支えた蒸気機関車を整備・修復できる伝統を今に伝える(もちろん、大阪のサッパボイラ社の存在は大きい)、その両方を兼ね備えているからだ。
JR西日本のなかでは、山陰・中国地方の路線が好きだ。中国地方には、特別に高い山もなければ巨大な湖もない、しかしそのなんの変哲もない山河こそ、日本の原風景だと看破したのは宮脇俊三だったか。僕にとって旅とは、木次線の三段スイッチバックで休み休み山を登るキハ52系の力強いエンジン音とふと訪れる山間の静寂に、曰く言いがたい悲しみを感じることだ。
鉄道マンの思い出も中国地方が多いような気がする。季節外れの大雪のときに、「寒いでしょ」と部屋に入れてくれた芸備線の駅長。切符をなくしたのをごまかした時、「正直に言えば許してあげるよ。人間は感情の動物やから」と諭してくれた伯備線の駅員。「山陰本線全線走破記念と切符に書いてください」とお願いしたら、「そこで待っとき」と車掌室に座らせてくれて、僕が間違えて汽笛のペダルを踏んでしまったのを「こら!」と笑いながら怒った車掌さん。
大学に入って、演劇活動が忙しくなったこともあり、以前ほどローカル線の旅はしなくなった。その間、列車は速くなり、車両の快適さは増し、ダイヤは便利になった。いいことばかりだ。気がつけば、国鉄色の485系の雷鳥も地方にいけば必ず乗れたキハ58系気動車も消えた。けど、そんな寂しさは、どうでもいいことだ。便利になることで助かる人のほうがずっと多いからだ。そもそも車掌室に子供を入れる車掌など、今なら大問題だ。
それでも、交通科学博物館の閉館時は、すっかりさぼっている鉄道ファンながらお別れに行った。義経号をはじめお馴染みの車両の展示を楽しんだ時は、そこまでの感慨はなかった。だが、名物のジオラマの部屋で、80分の1の模型列車に夢中になっている子供たちを見て、かつての自分に再会したようで、こみあげるものがあった。近年の自動制御のものではなく、ポイント切り替えなどすべて手動の旧式のジオラマ。見ると、隅っこの制御盤の前で若い職員が手際よく切り替えている。子供たちが喝采する運転はすべて、彼にかかっているから責任重大だ。背筋を伸ばして、指差し確認をしているその姿―国鉄がなくなった時には生まれてもいなかった若い職員の気高さに、100年余りの歴史を支えてきた鉄道マンの誇りを見て目頭が熱くなった。そして、彼が手動で照明を変えた時、その古風な作り物の夕景はまさに余部鉄橋から見下ろした夕日となり、少年の頃、車掌室で間違ってペダルを踏んで山陰線のトンネル内に鳴った汽笛が再び僕の中に響いた―満場の子供たちが歓声をあげるなか、僕は一人あふれる涙をとどめることができずにいた。
最近、京都鉄道博物館を訪れた。数々の名車両から鉄道公安の制服のようなマニアックなものまで、もちろん本物のSLに乗れる梅小路ならではの「スチーム号」も含めて、すべて堪能した。そして、新しくなったジオラマは、列車の解説を女性職員が丁寧に読み上げていて、その誠実な語り口に新しい時代の鉄道マンの姿を見て、嬉しくなった。時代も施設も変わっても、変わらず子供たちは歓声をあげていた。僕もまた新しい旅に出ることにしよう。