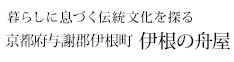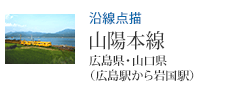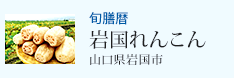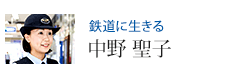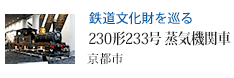![]()
山口県の東端、古くは岩国藩の城下町として栄えた岩国市。 中心部を県内最大河川の錦川が流れ、その河口付近には清流を利用した「岩国れんこん」の主産地が広がる。
夏、一面純白の花で彩られたハス田は、秋の気配が漂い始める頃から、実りの季節を迎える。
色白で、腰のある粘り、歯ごたえが特徴の伝統の味。岩国が誇るれんこんの旬に触れた。


酢飯にれんこん、しいたけ、錦糸卵などを散らし、ハスの葉で仕切って何層にも重ねる「岩国寿司」。江戸時代、藩主吉川公に献上され、「殿様寿司」とも呼ばれた。
れんこん(蓮根)は、多年性水生植物のハスの地下茎が肥大化した部分を指し、実際は「根」ではなく、地中に潜る「茎」を食用とする。日本には、奈良時代に花ハスが伝わり、当初は観賞用として栽培されていたという。ハスは、泥の中に根を張り、美しい花を咲かせた後、実の入った花托[かたく]が肥大する。この表面が蜂の巣に似ていることから、古くは「ハチス」と呼ばれ、それがいつしか「ハス」になったのが名前の由来とされている。食用としての栽培は、江戸時代後半。輪切りにすると多数の穴(通気孔)が開いたれんこんは、「先が見える」「見通しがきく」ことに通じる縁起の良い食べ物とされ、おせち料理や慶事に欠かせない食材として定着した。
岩国での栽培の始まりは、今から約200年前の1796(寛政8)年。藩主吉川経忠[きっかわつねただ]の命を受けた篤農家村本三五郎[さんごろう]が、干拓した農地の塩害に苦しんでいた農民を救うため、現在の岡山から備中種の種バス(種となるれんこん)を持ち帰り、錦川下流の門前地区に植えたのが起源とされる。その後、代々の藩主が埋め立てた干拓地に栽培を普及させ、また、日照時間が長い瀬戸内の温暖な気候、豊富な水量を誇る錦川の水に恵まれたことから、尾津・門前地区を中心とした一大産地が形成されていった。現在の主な栽培種は、明治時代に中国から導入された晩生の白花種。白くやわらかな肉質、粘りとシャキシャキした歯触りを併せ持ち、岩国れんこんを特徴づけている。因みに一般的なれんこんの穴の数は8つだが、岩国れんこんはほとんどが9つだそうだ。

産地では、4月頃、基肥を施し水を張ったハス田に、一定の間隔で種れんこんを植え付ける作業がスタートする。岩国れんこんの生育には、15度以上の適温が長く続くことが条件とされ、初夏の陽気とともに萌芽が始まり、田の水面には浮葉[うきは]が現れ出す。白花種は、ハスの中で最も葉が大きく、葉の直径は1m以上、茎は3mの高さにもなる。水面が見えなくなるほど青々と繁った立葉[たちは]は、夏の間たっぷりと太陽を浴び、その栄養分を地下茎に送る役割を持つ。そのため、夏場は十分な日照があることや、葉が台風の影響を受けないことなどが作柄を決めるという。
地中で肥え太った新れんこんが出回るのは、9月半ば。収穫の頃には水は抜かれているが、足が泥に埋まるような、ぬかるんだ圃場[ほじょう]での作業はかなりの重労働だ。掘り出す作業も、最初に掘り取り機を使って表面の土を除いた後は、鍬の一種である「ばんくう」や「かいかき」といった特殊な道具を使った手作業になる。傷がつかないよう丁寧に収穫されたれんこんは、本来の風味と新鮮さを保つため、泥付きのままで箱詰めされる。出荷の最盛期は、贈答やおせち料理の需要が高まる12月。収穫は冬を越え、春先まで続けられる。
地元では、祭りなどの行事でふるまう「岩国寿司」の具材に、昔も今もれんこんは欠かせない。さらに、岩国れんこん振興協議会が主体となって、新しいレシピの開発や普及にも力を入れる。地域の食卓に、特産品の伝統が息づいている。

主産地の尾津地区では、錦川の清流が各圃場に必要に応じて供給されるよう、パイプラインが整備され、徹底した水質管理が行われている。岩国れんこんは白花種で、赤い花のハスは観賞用とされる。

れんこんの芽が見えるまで機械で泥を取り除き、全体の姿を想像しながら専用の道具を使って丁寧に掘り出す。


郷土料理の一つ「大平(おおひら)」は、れんこん、里芋、山菜、鶏肉などを煮込んだ汁物。岩国寿司とともに祝いごとには欠かせない郷土の味だ。