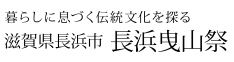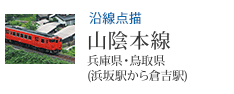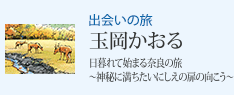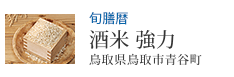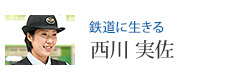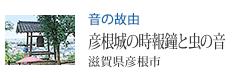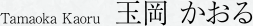
- 1956年、兵庫県三木市生まれ。作家。神戸女学院大学卒業。1987年神戸文学賞受賞作の『夢食い魚のブルー・グッドバイ』(新潮社)で文壇デビュー。代表作は、山本周五郎賞候補作となった『をんな紋』3部作(角川書店)、『天涯の船』(新潮社)、『銀のみち一条』(新潮社)、『負けんとき ヴォーリズ満喜子の種まく日々』ほか多数。執筆のかたわら、テレビやラジオにもコメンテーター、パーソナリティーとして出演中。近著は 『天平の女帝 孝謙称徳』(新潮社)を11月に出版予定。
夕日が傾き、柿の木に残った朱い実が一つ。烏がどこかで、早くおうちに帰ろ帰ろ、と鳴いている……。
子供の頃から何度も訪ねた奈良といえば、そんな夕暮れの印象ばかりだ。帰らなくてはいけないから気が急くし、帰りたくないからよけいに空は早く暗く沈んで、心細さをかきたてる。つまり、関西在住の私にとっては、奈良といえばいつも日帰りで行く旅だからそうなってしまうのだ。
ところが、三年ばかり前から、奈良に足繁く通う必要ができた。この11月に上梓する書き下ろし小説の取材で、初めて天平時代を書くことにしたからだ。
取材というのは案外予定が立たないもので、いっそ時間に制限がないように、奈良に泊まることを始めてみた。
帰らなくていいとなると、夕焼けを見送り、月が昇って振り返れば、ライトアップされた東大寺の鴟尾の壮大さに息を飲んだり。タイムスケジュールがすっかり異なり、目に入るものも大きく変わった。
この上おきまりの宿があれば、もっと奈良は居心地よくなる。そこを拠点に時間をフル利用、身軽に動いて、機動力が増すからだ。
ちなみに、私の定宿は登大路にあるホテル。
駅から来て最初に鹿と出会う公園のエリア、奈良県庁や興福寺のあるあたりにあって、部屋の窓からは興福寺の北円堂が真向かい、というロケーション。鹿たちがほろほろ歩いて来るのも視野の内だ。こぢんまりとしたホテルゆえ、いつも閑静で、スタッフの気配りがゆきとどいている。根が移り気な私は、定宿なんて腰を据えたのはここが初めてだが、心許せる快適さは他のどことも代えられなくなっている。
さて、ここに居場所ができると、今まで素通りだったり、なかなか行けずにいた場所がぐっと身近になってきた。
最大の出会いは、春日大社で行われる「おん祭」。千年以上も前から続く神事で、若宮から神様におでましいただき、お旅所の行宮までお遷ししあらゆる芸能で楽しませるというもの。なにしろ開始は星も凍りつくような真冬の夜中。日帰りでは絶対に参列できない。
「寒いですよー。カイロはお持ちですか?」
ホテルのスタッフにさんざん脅され、完全装備の防寒を整える。部屋を出たのは夜の十一時。一の鳥居からは街灯もなく、星明かりしか、導いてくれるものはない。いつもは漫然と歩いているだけというのに、春日の森の広大な闇は、自分の中にむくむくと、空気や風に鋭く感応できる原始の力を呼び覚ます。
本殿前まで歩いて二十分。懐中電灯も写真のフラッシュも許されず、携帯電話はもとより口をきいてもいけない。漆黒の暗闇と静寂こそが、神様の通る世界なのだ。
やがて、白装束の神官の方々が口々に「ヲー、ヲー」という警蹕[みさき]の声を発しながら、古式どおり、榊の枝で十重二十重に囲んだ神様をお連れする。
暗くて何も見えない、聞こえない。なのに、そばを通った瞬間、何やらひやり、圧倒されるような浄いものの存在を感じたふしぎ。
科学が地上のあらゆる現象を解明し尽くしたというのに、まだこんな神秘的なものが日本にはあるのだ。千三百年を越す時間の中で、先人たちがさまざまに知恵をめぐらせ、創り出した大いなる文化。継承されてきたのは、おそらく聖地の力だろう。
神事がすんでホテルにもどれば、笑顔と温かいほうじ茶で迎えられ、身も心も温まる。
奈良への旅は、長い歴史をさかのぼる旅。なのに文明に満ちたホテルの部屋で緊張を解くと、自分がどこか更新されて、前進の旅であったと実感できる。おかげで原稿用紙九百枚におよぶ大作を完成させることもできた。
だからそのつど心を磨いて、また出かけることになるだろう。愛すべき定宿から。