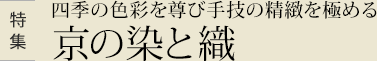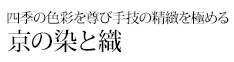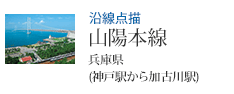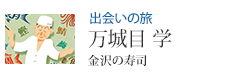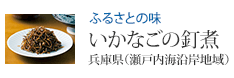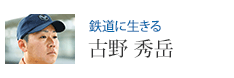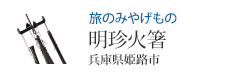![]()
「太秦」という難読の地名が京都市の西、洛西にある。「うずまさ」と読むこの場所には5世紀頃に、帰化した渡来人の技術集団が暮らしていた。農耕や土木技術に優れた彼らがもたらしたものの一つが養蚕、染、織絹の技術である。
815(弘仁6)年に編纂された『新撰姓氏録[しんせんしょうじろく]』にこんな記述がある。要約すると「仁徳天皇の時代に、秦氏なる渡来人が日本の各地に養蚕・織絹の技術を伝え、できあがった糸・綿・絹・帛[はく]を天皇に献納すると、天皇はその肌触りの柔らかさ、温かさに喜んだ。それで波多記公[はたのきみ]という姓を授けた」というのである。
さらに雄略天皇の時代に、天皇は禹都万佐[うずまさ]という号と山城国、現在の京都の西方の土地を与えた。それが今日の「太秦」である。秦氏は豊かな財力で聖徳太子を支え、平安京遷都にも大きな働きをする。

西陣織「渡文」で復元された能装束『黄地枝垂桜に胡蝶と源氏香図文様唐織』。地は黄一色で金箔糸で源氏香の図が地文様風に表わされている。上文様は枝垂桜と胡蝶。

「日本の文化の根源は、季節の移ろいをどう表現するかにある」と吉岡さんは話す。宇治川の畔にある工房「染司よしおか」は江戸時代からつづく。
京の染と織は秦氏を始祖として今日に伝わっている。しかし、『染と織の歴史手帳』など多くの著書を持つ「染司よしおか」の当主、染織研究家でもある吉岡幸雄さんはこう指摘する。「京が唐の長安に倣ったように染織も中国の強い影響下にあった。それから解き放たれ、日本の風土に合った“和”の文化を構築するのは、遣唐使が廃止され、平安時代も約百年を経たころからです」。
かな文字が生まれ、和歌が詠まれはじめたのと同じころに、王朝貴族が着衣した十二単に見られる「襲[かさ]ねの色目[いろめ]」という繊細な色の重ね合わせが登場する。これが中国の文化を離れた独自の和の文化で、細やかに移ろう日本の四季の趣きを色彩と配色で表現する「襲ねの色目」には、草木花にちなんだ美しい呼び名がつけられた。秋であれば「紅葉[もみじ]の襲ね」、「撫子[なでしこ]の襲ね」、「桔梗[ききょう]の襲ね」など。
それぞれは色彩と濃淡の変化で、花、葉、枝が表現される。色の違いは微妙で、日本茜[あかね]や紫根[しこん]、紅花[べにばな]、蓼藍[たであい]などの植物の色素で染め分け、それを重ね合わせて着た。こうして季節を表現し装束を身につけ楽しむことが貴族の教養であり、「源氏物語もそういう風潮の中から誕生した」と吉岡さんは言う。
「襲ねの色目」はやがて武家の世とともに廃れるが、季節の自然を日々の暮らしに取り入れ、色彩の変化を尊ぶ感性は、日本伝統の美意識として西陣織や京友禅に受け継がれてゆく。平安京の織部司の技を継ぐ精緻を極めた西陣織、繊細で優雅な京友禅。どちらも京都の風土が育てた他にない手技と趣きである。
日本ほど四季の移ろいが見事なところはないといわれる。しかも王朝文化に彩られた京都では、感性はより優雅に、より洗練されて、匠は技を競い合う。そして時代時代の厳しい顧客の目に鍛えられ、磨かれてきたのが京の染と織である。

「染司よしおか」で染められた「襲ねの色目」。
平安時代の女房装束の正装は十二単といわれるが、普段は5枚重ねたものが基本となる。貴族の女性たちにとって、美しく着飾ることは、たしなみであり教養でもあった。
上の写真は秋の「襲ねの色目」の代表で「撫子(なでしこ)の襲ね」。右から花の色3色、葉の色2色を染め分けた5色が基本。衣装の襟元と裾に見える、わずかにずらした5枚の微妙な色調を楽しんだ。