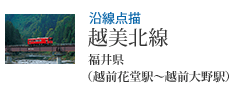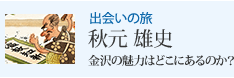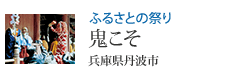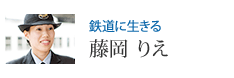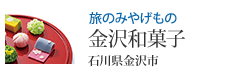-
金沢21世紀美術館館長。1955年東京都生まれ。
東京芸術大学美術学部卒業。1991年から2004年まで、(株)ベネッセコーポレーションに勤務。美術館の運営責任者として企画、運営に携わる。ベネッセアートサイト直島では、直島・家プロジェクト(第一期)を担当。2007年4月より金沢21世紀美術館館長。「金沢アートプラットホーム2008」で金沢の街を舞台にプロジェクト型展覧会の開催。2010年に「第1回金沢・世界工芸トリエンナーレ」ディレクターとして、新しい時代の工芸を世界に向けて発信。
金沢は、“古都”、“小京都”と形容されることがある。言葉の定義からいっても、歴史からいっても、そして金沢人の心情からいっても、これは正しくない。加賀前田藩は外様の大名であり、そこで花開いた文化は武家文化である。
冒頭からやかましいことを言うようだが、こういったスタンスからご理解いただけると思うが、金沢人は金沢のことを、金沢であって、それ以外ではない、と考えている。胸を張って「エヘン!」とそういうことは言わないが、低姿勢でありつつ、そう思っている。
さて、その金沢はいかなる場所であるのか?
金沢の歴史は、まあまあ、古い。1583年の前田利家公の入城の時からだから、400年ほどである。伝統もその時間の中で培われた。歴史、あるいは伝統というものの解釈によるのだが、長さを問題にすれば、今言った程度である。大方の地方の主要都市がそうであるように金沢も江戸時代の歴史、文化を背景に発展した。では、金沢らしさはどこにあるのかというと、発展段階で近世的な文化をよく引き継いできたところである。「なんだ」と言うなかれ。つまり保存と継承のされ方が際立っていて、他のところではなくなってしまったものが、高いレベルで現存しているのだ。
加賀藩は、ご存じの通り外様大名で100万石という大藩であった。圧倒的な大きさである。それもあって徳川幕府との微妙な政治関係から、文化、学問に力を入れ平和政策をとった。それをさらに進めたのが五代綱紀公で、学問、工芸、芸能を幅広い視野から振興した。学問、文化を大切にする気風はやがて町衆の中にまで浸透し、今に継承されている。街並、物品がよく残ったという意味で戦災に遭わなかったことも幸いした。
金沢の伝統文化、芸能が一地方都市にあって根強く継承されてきたのは、このような事情による。と、こう語ると、数百年前の文化政策がいまだに生きているというのはどうも俄かに信じがたいと思うだろう。しかし、少なくとも金沢人は、こういう物語をいまも語り続けている。
明治の開国、そして戦後の動乱期に日本はその都度、欧米に追いつけとばかり、古いものを棄て、新しいものに飛びついた。金沢だって、そういう気分が覆っていただろう。しかし、結果として残すことを選んだ。
この「ものが残っている」という状態は重要なことだ。我々は、実物を手掛かりに歴史を学んでいく。歴史は本や博物館を通じて頭の中で学ぶものになってしまったが、本来は生活空間の中にあり、それを通じて経験し、実感するものである。そうでなければ、単なる絵空事。眼の前の歴史、文化に自分との連続性を感じない。
さて、ここ20年程の金沢が何をしてきたかというと近世的なまちの再生に力を入れてきた。都市の外観を整備し、伝統的街並の保存を行ってきた。と同時に、建物の高さ制限や看板サインの規制、電柱の地中化、街路樹の整備など全体のバランスにも配慮した。それに工芸や芸能の奨励を徹底的に行ってきた。
街並や古物をよく残し、それを顕在化して、都市を歴史的な場にするということをここまでする都市もめずらしい。そしてこれらの中には、常に近世的な文化水準を手本とする金沢的美意識が存在している。
この美の追求の姿勢は、過去のものだけに向けられてきたわけではない。過去に対して向けた美意識はそのまま現代文化に対しても向けられた。過去の物の保存活動は市民間での金沢的美意識の共有化のプロセスでもあったろう。
駅前のもてなしドーム、市民芸術村、卯辰山工芸工房、金沢美術工芸大学など、今日的金沢の美意識を象徴し、現在の金沢の文化を発信する場所がいくつもある。そして最後に金沢21世紀美術館が加わった。金沢21世紀美術館は、今生まれつつある現代美術を扱う美術館であり、その射程距離は世界である。今の金沢の目標は、文化都市・金沢を世界に発信することだ。そのために2009年にユネスコの「創造都市ネットワーク」に登録した。
金沢のまちは過去とつながるだけではない。現代というものを足場にしながら未来へ、世界へと可能性を開いている。歴史とは、過去を考察することであると同時に未来を創造する手掛かりでもある。金沢というまちは、過去、現在、未来を共存させ、世界とつながろうとしている。
過去は過去のためにあるのではない。未来に向かう重要な手掛かりである。それが伝統というものの正体であろう。