 |
 |
野原一面に広がる菜の花のじゅうたん。
陽光に輝くその姿は、
のどかな春の原風景といえる。
可憐な花を愛でるだけでなく、
その蕾は早春の味覚として、
また、種子は菜種油に加工されるなど
古くから日本の暮らしに結びついてきた。
江戸中期の俳人、
池西言水[ごんすい]の心をとらえた
咲き誇る菜の花に思いを馳せ、
人と花との関わりの歴史をたどってみた。 |
 |
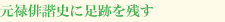 |
池西言水は、1650(慶安3)年奈良に生まれ、本名は則好[のりよし]、通称を八郎兵衛といい、洛下堂[らっかどう]などの号を持つ。祖父は和歌に通じ、実父も俳諧を嗜むという恵まれた環境で育ち、絵画や茶道、書画骨董の目利きとしても優れていたという。12歳の頃より句に親しみ、16歳で法体してからは俳諧に専念したと伝えられる。1676(延宝4)年、言水27歳の頃江戸へと移り、談林新風の俳諧に参加。1678(延宝6)年に処女撰集『江戸新道[しんみち]』を刊行以降、4年連続で編書を上梓するなど、活発な撰集活動を行った。江戸在住時代には芭蕉や其角らとも交流を重ね、軽妙な談林風の句作りを追いながらも蕉風に傾倒し、芭蕉一門の台頭の一翼を担ったと考えられている。

1682(天和2)年3月、華々しい活躍を続けていた江戸を去り、言水は京へ移る。上洛の背景は定かではないが、ひとつには京への強い憧憬があったとされる。ことばを巧みに使用し、機知に富んだ感受性豊かな句作りが言水の特色といわれるが、京移住後は独特の感性に京風の情緒が加わった佳句が見られるようになる。菜の花が今を盛りと咲き映える、春の河岸の風景を詠んだ冒頭の句も、淀川や桂川を人知れず流れる忘れ水に見立てるという、言水らしい眼目と艶やかな色彩を感じさせる一句となっている。 |
 |
 |
| 創業当時を今に伝える山中油店の店構え。昨年、京都市の景観重要建造物第1号に指定され、地域のシンボルとなっている。店の格子は、毎月一日建築用の菜種油で塗り替えが行われる。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 美しい色合いを味わう浅漬け。上賀茂では、ひな祭りのちらし寿司も菜の花で彩りを添える。 |
|
|
|
 |
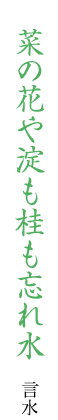 |
 |
 |
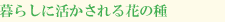 |
菜の花とは、アブラナ科栽培植物の花の総称であるが、一般には菜種と呼ばれるアブラナの花を指すことが多い。地中海沿岸が原産地とされ、中国・朝鮮半島を経由し、平安時代には日本に伝来していたと考えられている。菜の花の日本における歴史を辿っていくと、その種子から油を搾り利用するという、菜種油の姿が浮かび上がる。電気やガスが普及する明治まで、植物性の油はろうそくとともに灯り用の主な資材であった。室町時代まではシソ科の植物である荏胡麻[えごま]が主流であったが、油分が多く、灯火として優れた菜種の搾油が考案されると急速に普及したという。さらに大坂を製油の製造・販売拠点とする豊臣秀吉の政策を受け、搾油しやすく大量生産に向く菜種の栽培が奨励され、菜の花畑の春景が広がっていった。

菜の花の生産地京都で、創業以来200年の暖簾を守る山中油店は、今では数少ない油の専門店である。当時は主に灯明用の菜種油を取り扱っていたが、その価格は「お米1升100文、菜種油400文」と伝えられ、菜種油がいかに貴重なものであったかがうかがえる。その後、食用油として庶民が口にするのは明治に入ってからとされ、より食用に適するよう精製を加えたものが作られるようになった。山中油店の浅原孝さんによると、菜種油は他の油よりも耐熱安定性に優れ、油酔いもないことから揚げ物には最適という。菜の花の種から生まれる自然の滴は、時代に応じて用途を変えながらも、日本人の暮らしを支え続けている。 |
 |
 |
 |
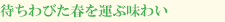 |
京都を南北に流れる賀茂川の上流、古くから洛中の野菜供給地である上賀茂周辺には、蕾のうちに摘んだ菜の花を塩漬けにする習慣が今も残る。この界隈の農家では、かつて油屋に菜種を売るための菜の花を栽培していたという。種子の収量を増やすため、春の近づきとともに伸びる主軸の先を間引いたものを、捨てるのがもったいないからと、自家用に塩漬けにしたのが菜の花漬けの始まりとされる。地域によっては、糠入りの布袋を添えて漬け込むところもあるが、独特の風味や緑の色合いを楽しむには、塩だけの浅漬けが好ましいという。作り方は、いたって簡素。畑から摘んできた3cmほどの花茎の先を一気に水洗いし、塩を振りギュッギュッと音がするほど力を入れてもんでいく。桶に入れ重石をした後は、1〜2日で食べ頃になる。蕾だけでなく、咲ききってしまう前の花びらも入れると、仕上がりの色も華やかになるのだそうだ。

この辺りには、作った野菜を大八車に積んで、京の町を売り歩く振り売りの伝統がある。新鮮な野菜とともに、農家が漬ける四季折々の漬け物も、食卓に旬を届けてきた。春一番に咲く菜の花のほろ苦い味わいは、底冷えの京都に春の訪れを告げる使者となっている。 |
 |
 |
| 京へ移った後も京俳壇の中心となって活動した言水は、「凩[こがらし]の果てはありけり海の音」の句で全国にその名を馳せ、「こがらしの言水」とまで呼ばれた。(『俳諧百一集』大阪市中央図書館蔵) |
|
 |
 |
|
|
 |