 |
 |
灸に使われるもぐさは「燃え草」が語源とされ、
火で病気の原因の邪鬼をいぶり出すといった
呪術的な意味があると伝えられる。
陰暦2月2日に灸をすえると
悪病災難を避け、1年を健康で過ごせるという
「二日灸[ふつかきゅう]」の習わしも残る。
江戸時代の俳人、
森川許六[もりかわきょりく]の句とともに
暮らしに根ざした灸の歴史をたどってみた。 |
 |
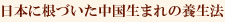 |
もぐさを肌にのせて火をつけ、温熱刺激によって不快な症状をやわらげるという灸。その起源は、約3000年前の古代中国にまで遡るといわれ、“気”というエネルギーの通り道である経絡[けいらく]と経穴[けいけつ](ツボ)の考えに基づいた、東洋医学の治療法のひとつである。日本へは562年、呉の智聡[ちそう]という人物が仏教の教典や薬書などとともに経絡経穴が描かれた『明堂図[みょうどうず]』をもたらし、これをもとにしてわが国の鍼灸術が始まったとされている。701(大宝元)年に制定された大宝律令の中には、医博士と並んで鍼[はり]博士という官職名が記されている。当時の鍼灸は灸治療が主体であったと考えられ、以降明治初期までの長きにわたり、灸は日本の医療法の中心に位置づけられ、庶民にとっての手軽な養生法としても広く普及していった。

灸は皮膚の上に直接もぐさを置き、それに火をつける点灸(直接灸)と、もぐさと皮膚の間に台紙やにんにく、しょうがなどを挟む温灸(間接灸)とに分けられる。点灸には、精製度の高い上質のもぐさが必要とされるが、日本人の職人気質は中国伝来の製造方法を本家を上回る水準にまで高め、自国の文化として定着させていった。江戸時代には日本からヨーロッパへと伝えられ、英語でもぐさを「MOXA」と表記することからも、日本の生活にとけ込んだ発展の歴史がうかがえる。 |
 |
 |
| 亀屋佐京商店の昔は、江戸時代を代表する浮世絵師 安藤広重(1797〜1858年)の『木曾街道六拾九次之内 柏原』の絵にしのぶことができる。休憩所で床几に腰を下ろし、一服する旅人のようすが興味深い。(中山道広重美術館蔵) |
 |
 |
収穫したヨモギを干し、石臼にかけ、唐箕にかけて精製するという工程によって、ヨモギの葉の裏にある白いうぶ毛(毛茸)が綿状のもぐさに変わる。
撮影協力:亀屋左京商店
(もぐさ製造は大変繊細なものです。見学希望の場合は必ず事前に承諾が必要です) |
 |
 |
| 『俳諧百一集』(1765(明和2)年刊)にある許六像。許六という号は、槍や剣術、書道など六芸すべてに優れていたことから、芭蕉が命名したといわれている。(大阪市立中央図書館蔵) |
|
|
|
 |
![灸[きゅう]の点[てん]ひぬ間も寒し春の風 許六](image/poet_text.gif) |
 |
 |
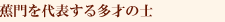 |
森川許六は、1656(明暦2)年に近江彦根藩士の家に生まれた。本名は百仲[ももなか]、通称は五介[ごすけ]といい、五老井[ごろうせい]、菊阿仏[きくあぶつ]の別号を持つ。1676(延宝4)年、許六21歳で井伊直澄に仕え、34歳の時には家督を継いで三百石を禄する藩士となり、武術の達人として武芸指南役を務めた。10代の頃より田中常矩[つねのり]の門人として俳句を学んだが、本格的に俳諧に傾倒していくのは、俳聖松尾芭蕉の句の深遠さに触れてからという。1692(元禄5)年藩士として江戸に赴いた機会には、かねてより敬愛していた芭蕉を訪ね、正式に入門を果たしている。許六は芭蕉十哲のひとりとして知られているが、十哲のうちではもっとも遅くに入門し、師である芭蕉と接していたのはわずか2年に過ぎない。しかし、狩野派の流れを汲む画人でもあった許六は、絵画の面では芭蕉の師となり、また芭蕉の句にしばしば画賛を行うなど、短期間の交流の中で師弟関係の絆を深めていった。さらに芭蕉の死後も、同門の去来らとともに蕉風の解明と普及に尽力した。

冒頭の句は、『韻塞[いんふたぎ]』(1697(元禄10)年李由共選)に収められた余寒を題材に詠んだ一句である。許六自身が「灸[やいと]の墨の干兼ねるに肌を着兼ね、(中略)余寒を残したる春風とハ云うべけれ。」と記しているように、もぐさの焼け残りをも季節の情趣としてとらえ、灸をすえた後の肌に感じる風に立春以降の寒さを表現している。 |
 |
 |
 |
 |
日本で灸が浸透した背景に、もぐさの原料に適したヨモギが採れたことがある。中でも、滋賀県内の最高峰、伊吹山[いぶきやま]に自生するオオヨモギが最良とされ、古くから効能の高い灸には伊吹産を用いてきた。安土城築城の頃、織田信長は伊吹山麓一帯に薬草園を開き、3千種もの薬草を栽培したが、ヨモギもその中のひとつであったという。

伊吹山のふもとに、かつて中山道の宿場町として栄えた柏原[かしわばら]という町がある。江戸後期には、街道に面して名物「伊吹もぐさ」を扱うもぐさ屋が並び、近江一にぎわったと伝えられる。不思議なことに、当時十数軒あったもぐさ屋は、ほとんどが「亀屋」の屋号を名乗っていたという。その理由を、1661(寛文元)年の創業以来、もぐさ一筋に商いを営んできた亀屋佐京商店の松浦達修さんはこう語る。「中山道を往来する旅人は、この柏原で競って良質のもぐさを手に入れていました。品質の悪いものを作れば亀屋すべてが困る。同じ屋号にすることで、品質向上のために牽制し合っていたのです」。互いに切磋琢磨し、地域名を冠する名産品に育てあげた手法には、近江商人の気風と才覚を感じとることができる。

時代は移り、伝統ある伊吹もぐさを今に伝える店は、亀屋佐京商店ただ1軒となっている。しかし、手間ひまを惜しまない家伝の製法は脈々と受け継がれ、現代人に癒しとぬくもりを届けている。 |
 |
 |
|
|
 |