|
|
 |
|
 |
 |
 |
| 鮭、野菜がたっぷりと入った栄養豊富な粕汁。身体を温め、冬の食卓に彩りを添える。 |
 |

三輪山を御神体とし、大物主神を祀る大神神社。毎年、全国の杜氏や酒造関係者が参列して、新酒の「醸造安全祈願祭」が行われている。 |
|
 |

今西酒造の大吟醸酒の袋搾り風景。酒が1滴1滴しずくとなって生まれ、袋の中には柔らかな粕が残る。 |
|
 |

もろみを入れた袋を酒槽に重ねていき、上からプレスをかける伝統的な搾り方。 |
|
 |

圧搾機に残った粕を、二人一組で効率よくはがしていく「粕剥き」作業。きれいな板状の酒粕がとれる。 |
|
 |

できあがったばかりの酒粕には、アルコール分の他、旨み成分も残り、華やかな香りがある。 |
|
 |
|
 |
 |
 |
| 風花が舞い、手足の先が凍えるほどの寒い日の夜、食卓に登場する汁物に「粕汁」がある。粕汁は、日本酒の醸造工程で得られる「酒粕」を使った代表的な料理。鮭や鰤などの魚とともに、大根、にんじん、ごぼう、こんにゃくなどを煮込んで作る、具だくさんの惣菜汁である。冷えた身体を芯から温め、酒好きにも料理好きにも愛される冬のごちそう。粕汁の暮らしとの関わりについて、酒粕の歴史や食習慣とともに探ってみた。 |
 |
 |
 |
 |
酒粕は、やはり日本酒と同じだけの歴史を持つ。古くは『播磨国風土記』(713年)に、日本酒の原型である米麹を用いた酒造りの記述が見られ、平安時代の『延喜式[えんぎしき]』(905〜927年)には、宮中における酒造法が詳しく記されている。副産物である酒粕も、その頃から野菜や魚を長期保存するため、粕漬けとして用いられていた。しかし、当時は濁り酒であったため、酒粕も搾った粕ではなく、酒の底に溜まる沈殿物であったと考えられている。さらに、庶民用の酒の原料にも使われ、冬季には身体を温める目的で飲まれていたという。“カス”とはいうものの、酵母のたんぱく質をはじめ、ビタミンBやミネラルなどが含まれる滋養食品。江戸時代には、「手握[てにぎ]り酒」「酒骨[さかぼね]」などの趣のある名で呼ばれ、広く庶民に親しまれてきた。

ひとくちに酒粕といっても種類があり、大きくは「板粕[いたかす]」と「踏み粕」に分けられる。発酵を終えたもろみを搾り機にかけ、液体(日本酒)と分離させて残った固形物が板粕で、粕汁や甘酒に使われる。また、板状なので焼いて食べることもできる。踏み粕は、この板粕をもう一度タンクに戻し、踏み込んで空気を追い出し、長期間貯蔵・熟成させたもの。黄金色に色づき、柔らかなため、こちらは主に粕漬けなどに用いられている。 |
 |
 |
 |
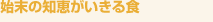 |
| 1月20日は「二十日[はつか]正月」と呼ばれ、元旦から続いていた正月行事が終わる節目の日である。かつては、正月の祝いとして、塩鮭や鰤などの年肴を一匹まるごと用意し、少しずつ切り分けて食べていた。この頃には、その魚もだんだんと身がなくなり、中骨や頭だけになってしまい、それを食べ尽くすことから「骨正月」ともいわれる。この日の献立は粕汁。残った骨や頭をだしにして、野菜といっしょに煮て食べる、祝い納めの風習である。日本酒を造る時に出た酒粕と、正月の残り物とでつくる質素な料理であるが、ハレの気分を追いやり、日常の暮らしへと戻っていく、けじめの食習慣となっていた。また、この日は新年から行事続きで働きづめの女性が、家事を休み里帰りする日でもあった。作り置きができ、温めなおして食べられる粕汁は、好都合の料理であったようだ。暦のうえでは大寒を迎え、1年で最も寒さが厳しい頃である。身体を暖め、栄養的にもすぐれた粕汁は、食材を無駄なく使いきるという、日本人の始末の知恵から生まれた、理にかなった食べ物なのである。 |
 |
 |
 |
 |
酒の神様として信仰の篤い大神[おおみわ]神社のお膝元、奈良県桜井市三輪で約300年続く造り酒屋を営む今西謙之さんによると、現在のような酒粕ができたのは、清酒造りの起源とされる室町時代、奈良・菩提山正暦[しょうりゃく]寺の酒造法からであるという。菩提[ぼだい]もと造りと呼ばれるその方法によって、もろみを搾って液体と固体に分け、液体を「清酒[すみさけ]」とした。残り粕は「奈良酒[ならさけ]」と呼ばれ、この土地の漬物に利用された。粕漬けを奈良漬というのは、当時の呼び名に由来している。

酒粕の出る量は、酒の造り方によって異なる。今西酒造では、本醸造酒などの場合、発酵を終えたもろみを圧搾機に入れ、約2日間かけて清酒と酒粕に分ける。この時の粕歩合[かすぶあい](もろみを搾ったあとに残る酒粕の割合)は、20〜30%。吟醸酒など、高級酒の粕歩合は40%以上にもなるという。搾り方も機械ではなく、昔ながらの袋しぼりが用いられる。粕歩合が高いものほど酒粕の水分も多いため、しっとりとした酒粕になる。特に大吟醸などは、粕の中に米の粒が残り、旨みが強く香りも豊かである。丹精込めて造られた大吟醸が出回る2月頃は、新酒を心待ちにする酒好きとともに、贅沢な粕が目当ての客も多いという。

酒造りに携わる杜氏[とうじ]や蔵人[くらびと]たちの手が白く、きめ細かなことはよく知られている。麹の中に含まれる成分に美白効果があるとされ、古くは米糠と同じように、酒粕を洗顔にも利用していたようだ。また、湿布ややけどの治療など、多くの民間療法にも用いられていたという。このように日本人は、“カス”を余すことなく暮らしに活かしてきた。一杯の粕汁の中にも、寒い季節を健やかに過ごす、先人の知恵が詰まっている。 |
 |
 |
|
|
|
 |