 |
| まっ暗な空に閃光が走り、霰[みぞれ]混じりの雷鳴が轟く。11月下旬、北陸地方に鳴り響く強烈な雷は「鰤起し[ぶりおこし]」と呼ばれ、長い冬の訪れと鰤漁の最盛期を告げる合図といわれている。荒れた海では、身が引き締まり脂ののった寒鰤が獲れる。さらに、土の中では地元産の青かぶらが丸々と太り、収穫を待つ。古都金沢には、今が旬の山海の幸を使った一風変わった漬け物がある。寒鰤をかぶらに挟んで麹に漬けた「かぶら寿し」。正月料理にも欠かせない、加賀ならではの逸品である。厳寒の地に伝わる、郷土の食文化を探ってみた。 |
 |
 |
 |
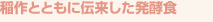 |
| かぶら寿しとはいうものの、魚介の具とすし飯を合わせた一般的なすしとは趣が異なる。今日のすしのルーツは、東南アジア山間部の淡水魚の保存方法を発祥とする「なれずし」とされるが、かぶら寿しもその一種。なれずしとは、貴重なたんぱく源である魚の保存性を高めるため、塩をあて米を加えて漬け込み、発酵させたものである。その歴史は古く、日本には中国大陸から稲作文化とともに伝来したといわれている。「なれ」は「馴れ」もしくは「熟れ」という漢字をあてるが、まさしく発酵によって魚が熟成していくさまを表した呼び名といえる。夏は高温多雨、冬は寒冷で雪深い北陸の気候は、酵母菌の発育を助け、雑菌の繁殖を防ぐなど、発酵食品に適した条件に恵まれ、酒・味噌・醤油をはじめとする深く豊かな味わいをつくり出してきた。真冬には雪に閉ざされ、野菜の収穫も魚の水揚げもない日が続くこの地方。かぶら寿しは、厳寒期の食卓を支える貴重な保存食として、土地に根づく発酵食文化の中で受け継がれてきたのである。 |
 |
 |
 |
 |
かぶら寿しの起源は定かではない。江戸時代後期に宮越[みやのこし](現金沢市金石[かないわ]町)の漁師が一年の豊漁と安全を祈る正月の儀式でふるまわれたとも、前田の殿様(藩主名不明)が深谷[ふかたに]温泉へ湯治にきた時の料理として出されたのが始まりとも言い伝えられている。記録としては、『金沢市史(風俗編)』に1757(宝暦7)年10代藩主前田重教[しげみち]の頃、中流家庭の客をもてなす料理として「なまこ、このわた、かぶら鮓」とあり、江戸時代には今のかぶら寿しとほぼ変わりないものが食べられていたと考えられている。また、庶民の食べ物が厳しく統制された藩政時代に、“鰤一本米一俵”といわれる高級魚の鰤をかぶらに隠して賞味しようとした、庶民の知恵から生まれたという説もある。いずれにしても寒鰤は、当時の特別な魚であったことがうかがえる。

魚を野菜ではさむ漬け物は、北海道で生まれたものとされる。江戸時代から明治のはじめにかけて、大阪から下関を経由して日本海を北上し、蝦夷(北海道)に至る航路は「北前船」と呼ばれ、復路、北陸には鰊[にしん]、鮭、昆布などが運ばれてきた。加賀は海上輸送路の中程にあり、文化交流もさかんであったことから、魚を野菜にはさんで食べるという独特な食べ方も北前船の影響を受けたと考えられる。かぶら寿しよりも庶民的な味として親しまれている「大根寿し」は、身欠[みが]き鰊を使ったものである。 |
 |
 |
 |
 |
重石をした樽が、工場の敷地一面を埋め尽くす。漬け物専門店「四十萬谷[しじまや]本舗」では、毎年冬の到来とともに、そんな光景が繰り広げられる。創業は1875(明治8)年。かつては家庭料理としてつくられていた郷土の味覚を今も守り続けている。

かぶら寿しは、材料を厳選することから始まる。鰤は1月〜2月に日本海で獲れる、脂ののった寒鰤にこだわり、塩漬け保存しておいたものを11月からの仕込みに用いるという。かぶらは、金沢近郊や能登で栽培される「百万石青首かぶら」を使用する。品種改良を重ねたこのかぶらは、鰤に負けない風味の強さとしっかりとした肉質が特徴。ほぼ2cm厚に切ったかぶらを塩漬けにしてから、下味をつけておいた鰤の薄切りを挟み込む。樽にそのかぶらを並べ、たっぷりの麹で漬け込み、発酵熟成させていく。手慣れた作業を怠りなく終えても、気温の状況や樽の置き場所ひとつで味が微妙に変わるという。熟成具合を見極めるのは、熟練の技を持つ職人の仕事。“生きもの”を扱う達人の眼が、伝統の味へと導いている。

泉鏡花が1920(大正9)年に故郷について書いた『寸情風土記[すんじょうふどき]』には、師である尾崎紅葉にかぶら寿しを贈り、大変喜ばれたという一節がある。さらに、「年の暮れに霰[みぞれ]に漬けて、早春の御馳走なり」と麹を霰に見立て、故郷の冬の味を表現している。鰤の旨味、かぶらと麹の甘味が調和した冬の金沢が誇る逸品。切り口の色彩の美しさも、その味わいに気品を添える。文豪をも魅了したかぶら寿しは、古都の美意識が息づく、味の芸術品なのである。 |
 |
 |
|